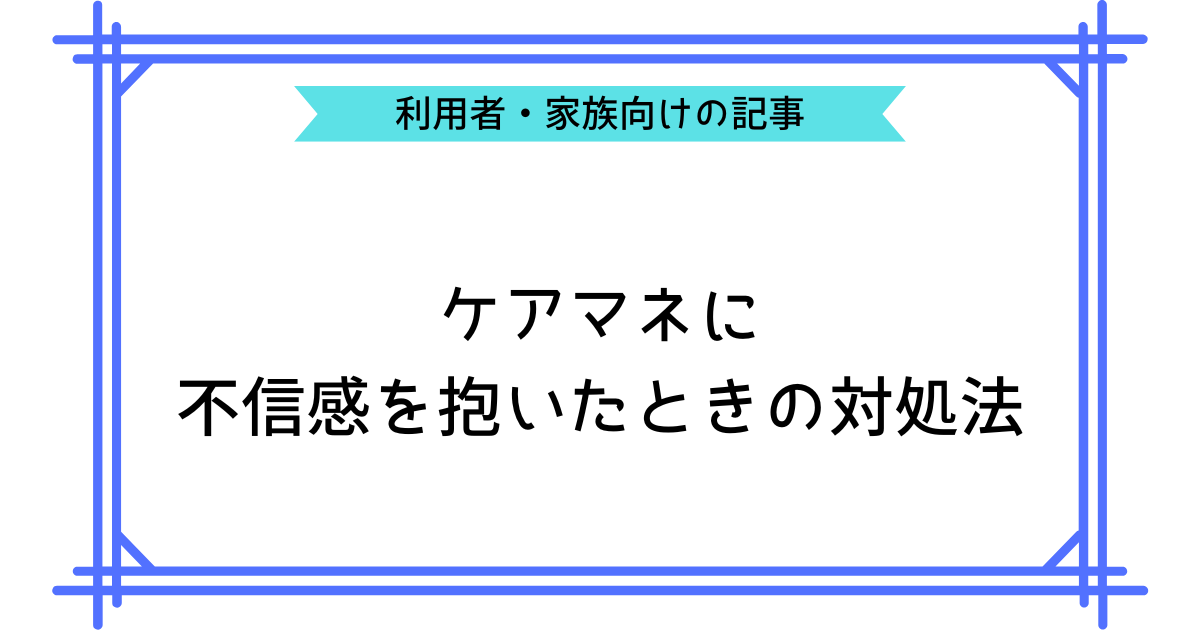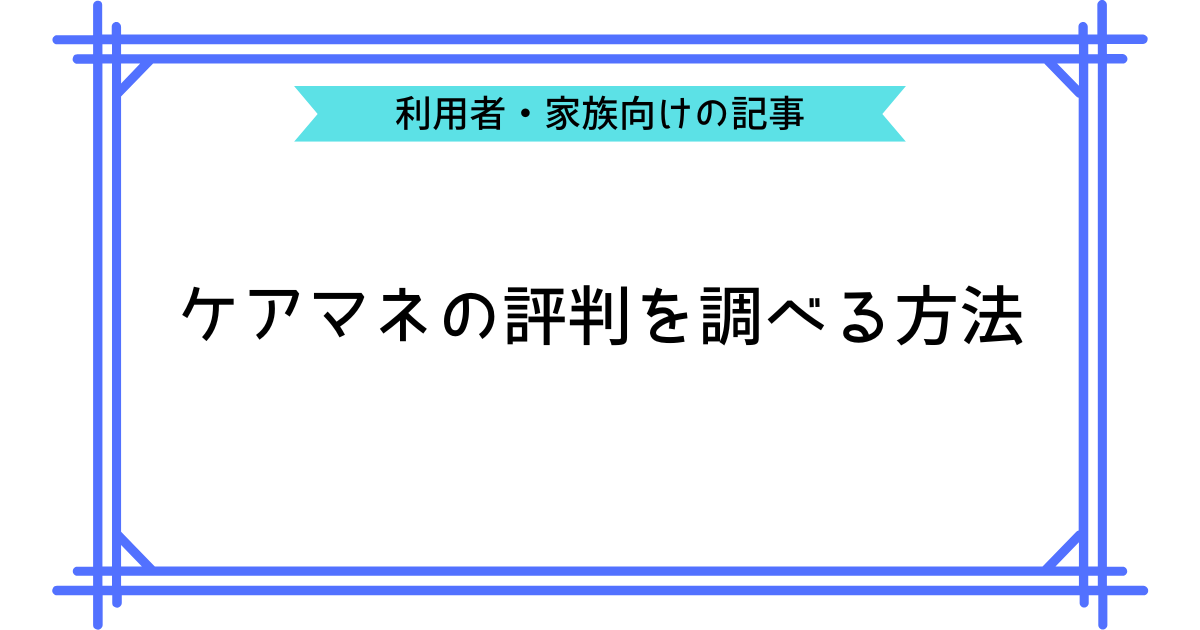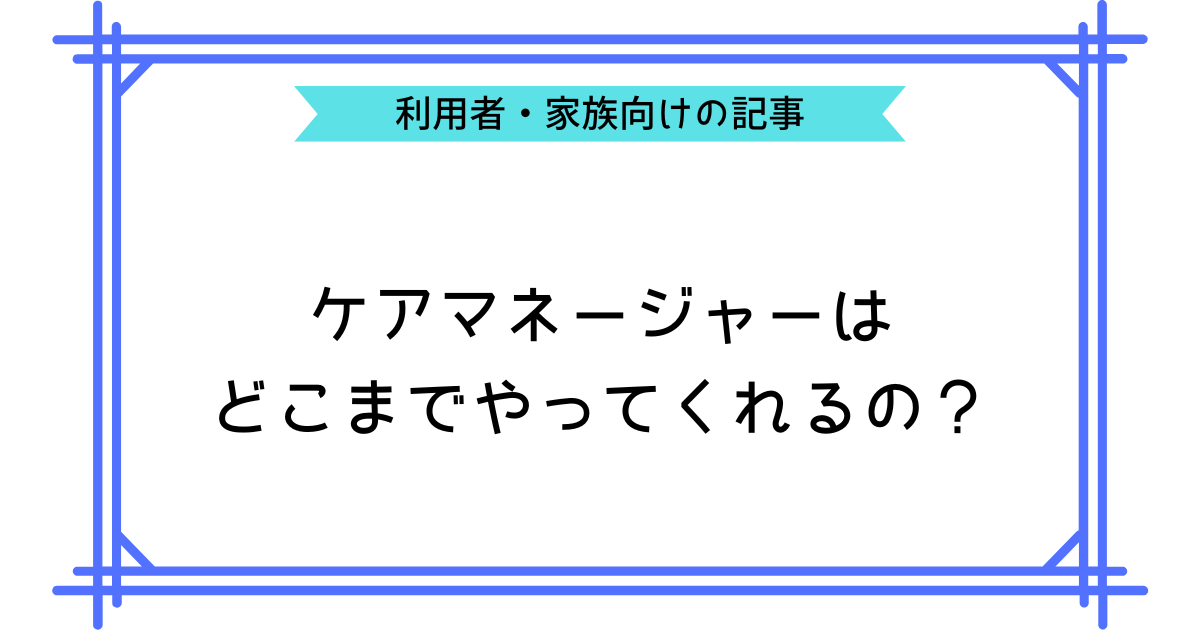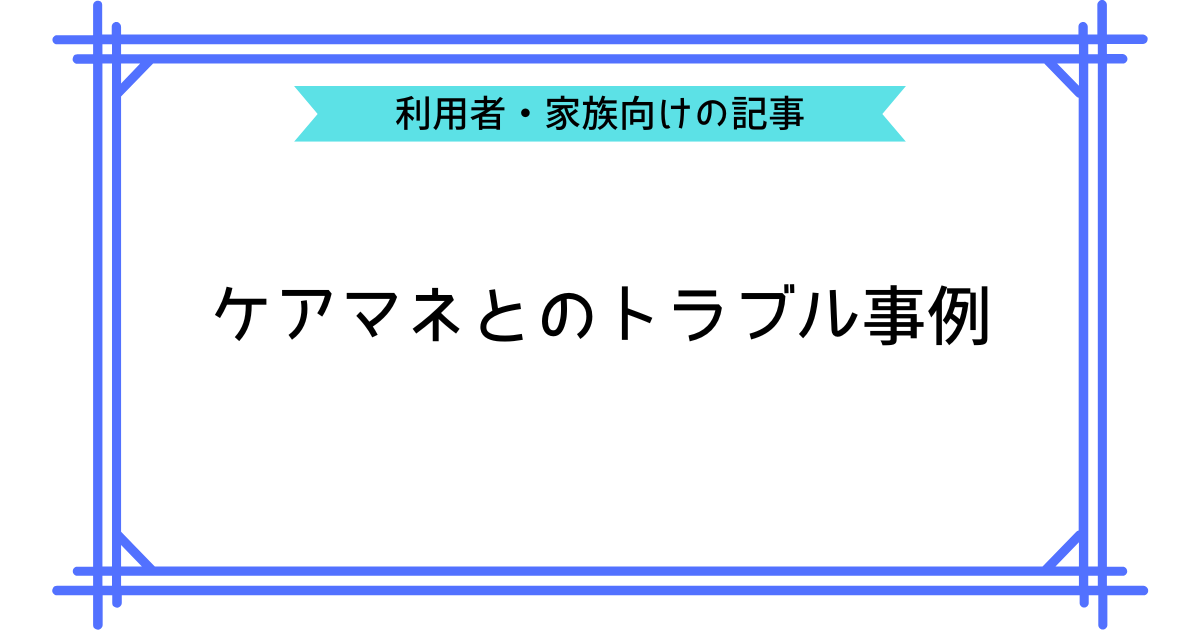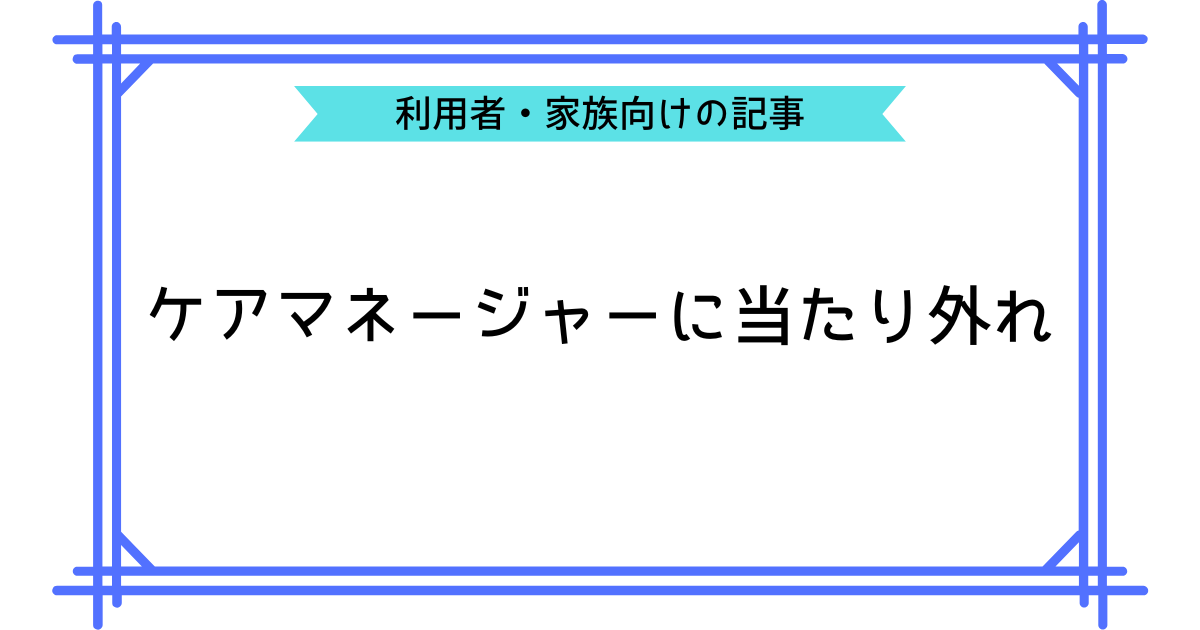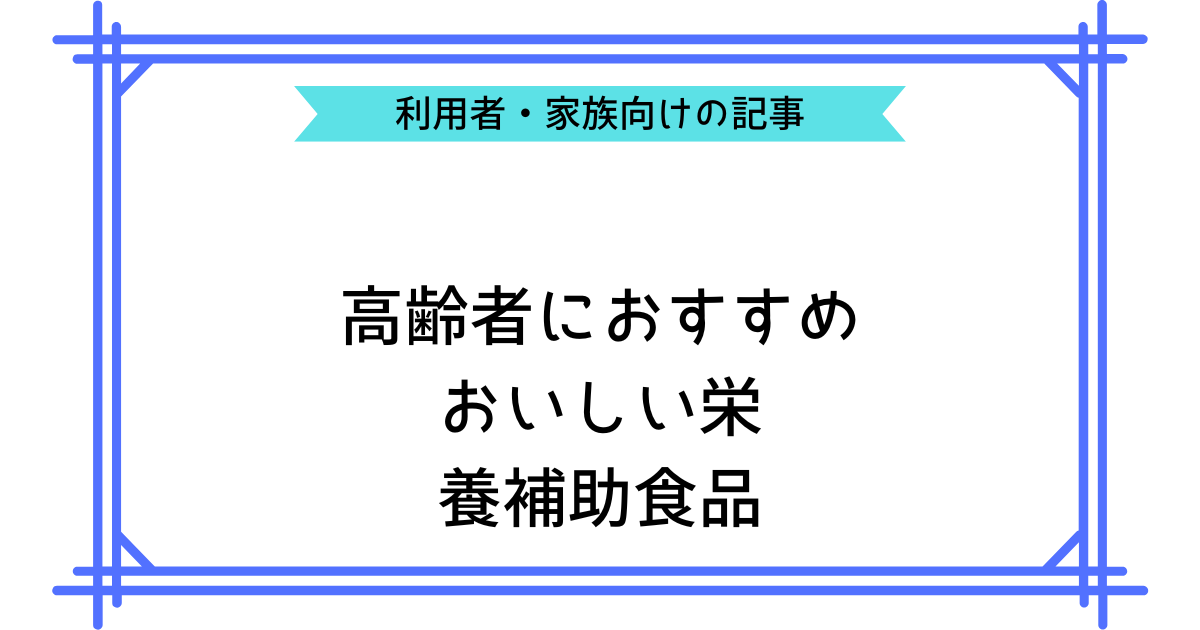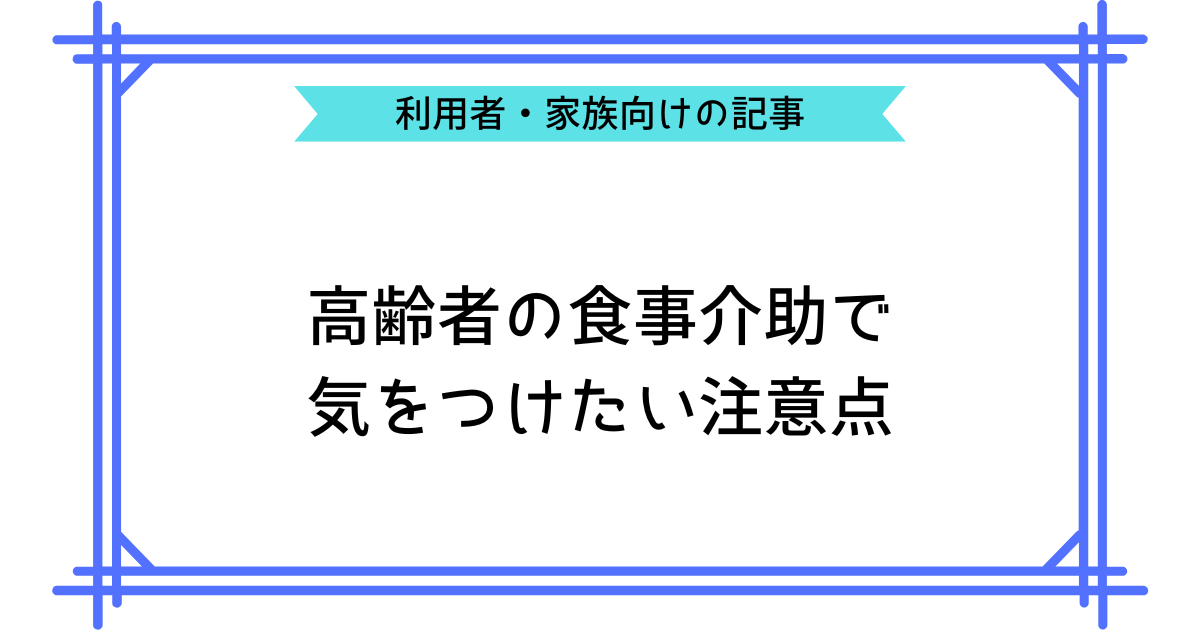ショートステイで認知症は進む?悪化する?不安を解消するための徹底解説
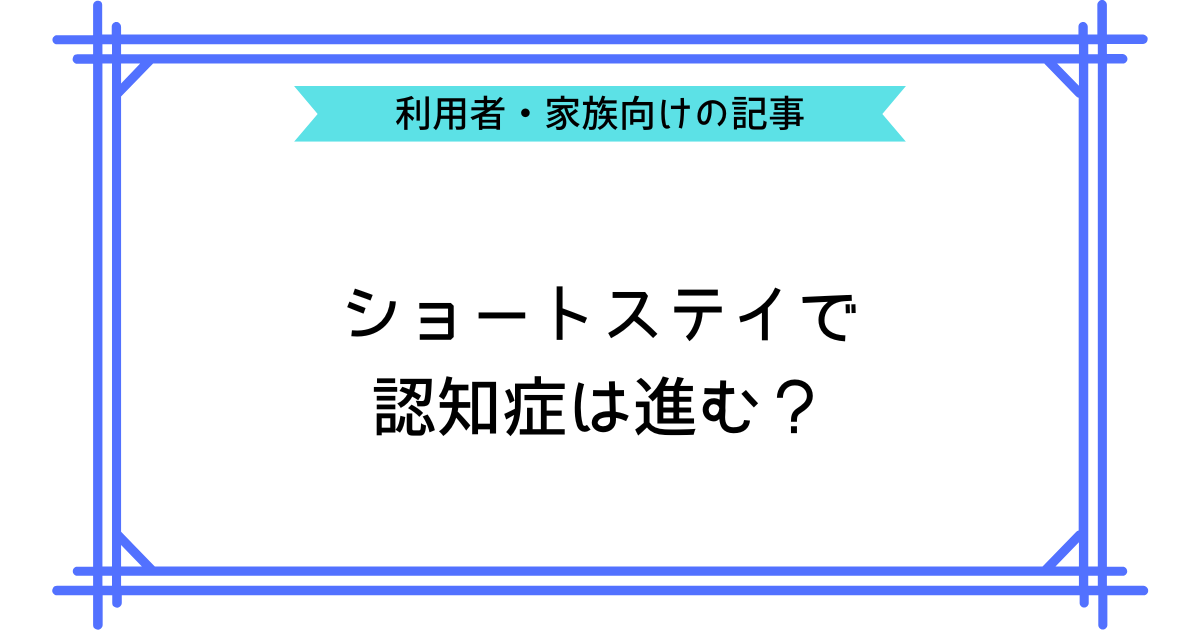
「ショートステイを利用したら、認知症が進むのではないか」「施設に預けると症状が悪化するのではないか」と不安に感じるご家族は少なくありません。
特に認知症の方は、環境の変化に敏感であるため、慣れない場所で過ごすことが混乱や症状悪化につながる可能性は確かにあります。
一方で、ショートステイはご家族の介護負担を軽減するだけでなく、利用者本人にとってもリハビリや交流の機会となり、認知症の進行を遅らせたり生活の質を向上させたりする効果が期待できるサービスです。
本記事では、ショートステイと認知症の進行の関係について、悪化するリスクとその理由、逆に良い効果が得られるケース、利用時の工夫や注意点を詳しく解説します。
ご家族が安心してショートステイを選択できるようにお伝えします。
ショートステイとは?認知症の方も利用できる介護保険サービス
ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)は、要介護認定を受けた方が一時的に施設へ宿泊し、介護や支援を受けるサービスです。
利用目的は大きく分けて2つあります。
- 家族の介護負担軽減(レスパイトケア)
冠婚葬祭や旅行、仕事、介護疲れによる休養などで一時的に介護が難しいときに利用する。 - 利用者本人のリハビリや機能訓練、生活リズムの安定
入浴・食事・排泄など日常生活の支援や、機能訓練を通じて生活能力を維持・改善する。
認知症の方でも要介護認定を受けていれば利用可能であり、実際には多くの施設で認知症高齢者の受け入れが行われています。
ショートステイで認知症が「進む」「悪化する」と言われる理由
「ショートステイを使うと認知症が進む」と耳にしたことがある方も多いでしょう。
その背景には、以下のような要因があります。
環境の変化による混乱
認知症の方は「見慣れた環境」「慣れた人との関わり」に安心感を持ちます。逆に、ショートステイでは初めての環境・新しい職員・初対面の利用者に囲まれるため、不安や混乱が強くなりやすいです。その結果、見当識障害(時間や場所が分からなくなる)が目立ったり、徘徊や不穏といった行動が出たりすることがあります。
家族と離れることによる不安
普段一緒に過ごしている家族と離れることで、「見捨てられたのではないか」と感じたり、不安や寂しさから情緒不安定になるケースもあります。これが一時的に認知症の症状を悪化させる要因となります。
職員や施設との相性
施設によっては認知症ケアに十分な経験を持つ職員が少ない場合や、利用者本人と雰囲気が合わない場合があります。コミュニケーション不足や支援方法のミスマッチが重なると、不安や混乱が強まり、症状が「進んだ」と見えることがあります。
ショートステイで認知症が悪化するのは一時的な場合が多い
ただし、ショートステイで見られる「認知症の進行」は一時的な症状の変化であることが少なくありません。
- 環境に慣れていない初回利用時に混乱が強く出る
- 利用中に一時的に不安や徘徊が増える
- 家族と再会後に落ち着きを取り戻す
このように、ショートステイの影響で認知症そのものが進行しているわけではなく、一時的な混乱やストレス反応として症状が強まっているケースが多いです。
数日から数週間で落ち着くことも多く、「進んだ」と感じても実際には元の状態に戻ることがあります。
ショートステイが認知症に与える良い影響
一方で、ショートステイは認知症に対して良い効果をもたらすケースもあります。
社会的交流による刺激
自宅では交流が限られがちな方でも、施設で他の利用者や職員と関わることで会話や活動が増えます。これは認知機能への刺激となり、症状進行を遅らせる効果が期待できます。
生活リズムの安定
食事・入浴・排泄などの生活習慣が一定のリズムで提供されるため、昼夜逆転や不眠などの改善につながる場合があります。
リハビリやレクリエーション
ショートステイでは機能訓練やレクリエーションが行われることが多く、体を動かしたり脳を使ったりする活動は、認知症の悪化防止に効果的です。
家族の介護負担軽減
介護する家族が休養を取れることで、介護の質が維持されるという間接的な効果もあります。家族の疲労が蓄積すると介護ストレスが利用者に伝わりやすく、結果として症状が悪化することもあります。ショートステイの活用は、その悪循環を防ぐ役割も果たします。
認知症の進行を防ぐショートステイ利用の工夫
ショートステイをより安心して利用するためには、事前準備と工夫が欠かせません。
事前に本人の情報を共有する
ケアマネジャーや施設に対して、利用者の生活歴・趣味・好み・不安要因などを伝えることで、本人に合った支援を受けやすくなります。
慣れた持ち物を持参する
普段使っている衣類や写真、馴染みの小物などを持参すると、利用者が安心しやすくなります。
短期間から始める
いきなり長期間の利用ではなく、まずは1泊2日や2泊3日からスタートし、少しずつ慣れていくのが望ましいです。
利用後のフォローをする
ショートステイ利用後に一時的に混乱が見られても、家族が安心させたりケアマネと情報共有したりすることで、症状が長期化するのを防げます。
ショートステイを利用するか迷ったときの判断ポイント
- 家族の介護疲れが強い → 介護継続のためにレスパイト利用を検討
- 在宅生活が不安定になっている → ショートステイで生活リズムを整える
- 本人が閉じこもりがち → 交流やリハビリを通じて刺激を与える
- 環境変化に弱いタイプの認知症 → 短期間・事前準備を徹底し、少しずつ慣らす
ショートステイ利用の目的を明確にし、「家族の休養」「本人の安定」「在宅生活の継続」のどれを重視するのかを整理してから活用すると良いでしょう。
まとめ
ショートステイを利用すると認知症が「進む」「悪化する」と心配する声はありますが、実際には一時的な混乱や環境変化への反応であることが多いです。
むしろ、ショートステイをうまく活用すれば社会的交流や生活リズムの安定、家族の介護負担軽減などのメリットも大きく、認知症の進行を遅らせる効果が期待できます。
大切なのは、利用前の情報共有・少しずつの慣れ・利用後のフォローです。
ケアマネジャーや施設と協力しながら、本人と家族にとって安心できるショートステイ利用を目指しましょう。