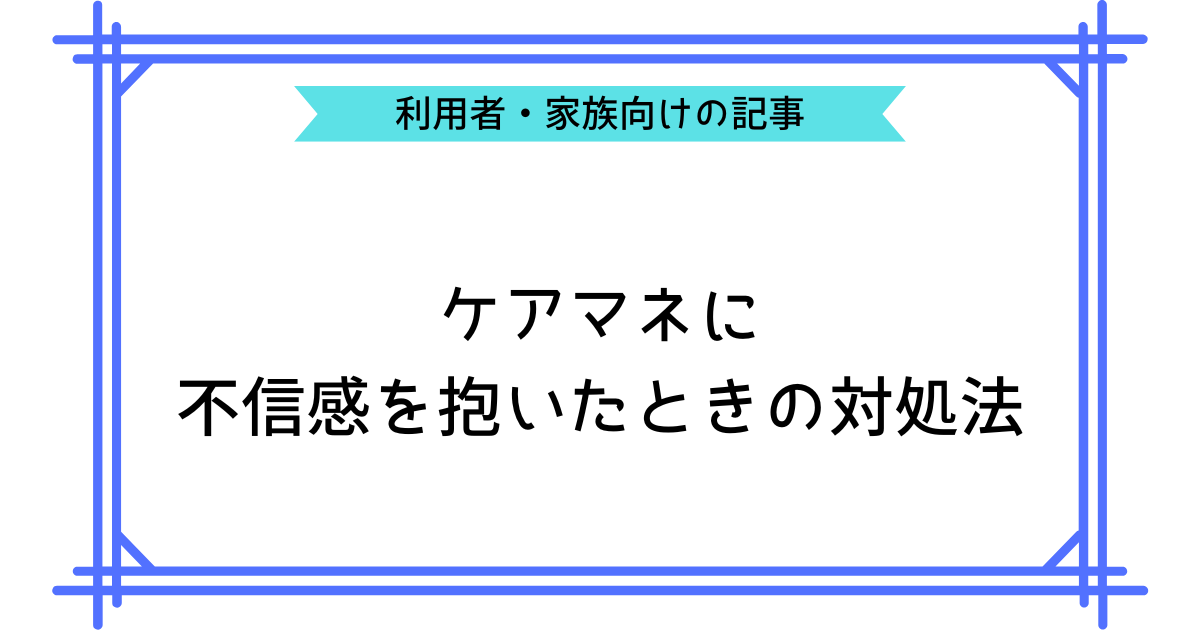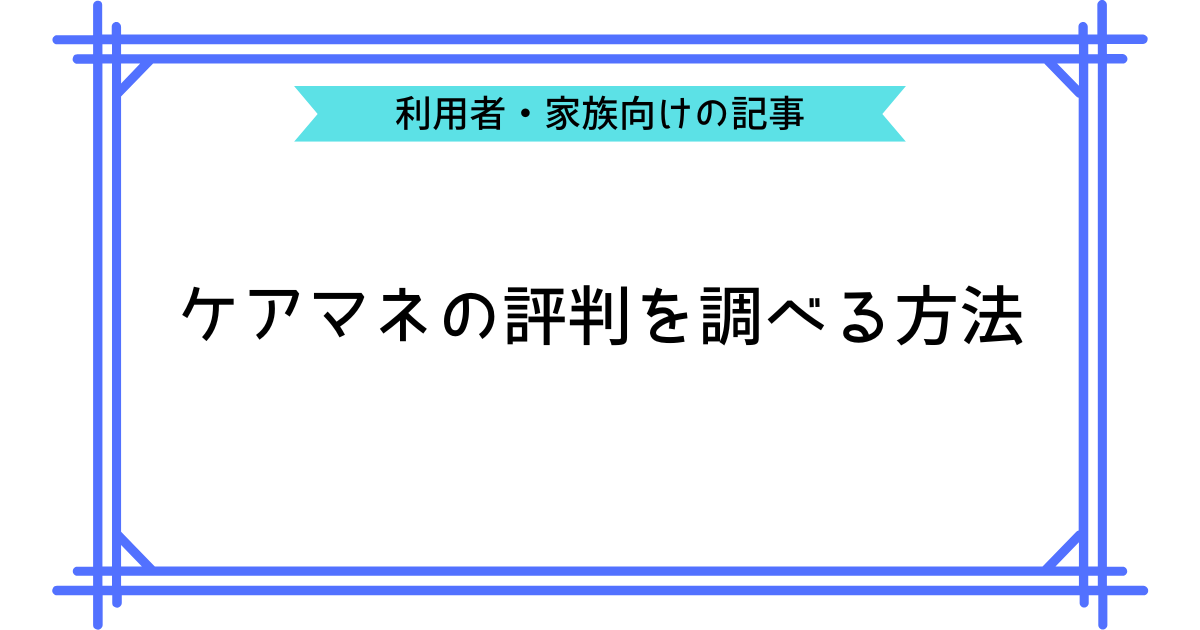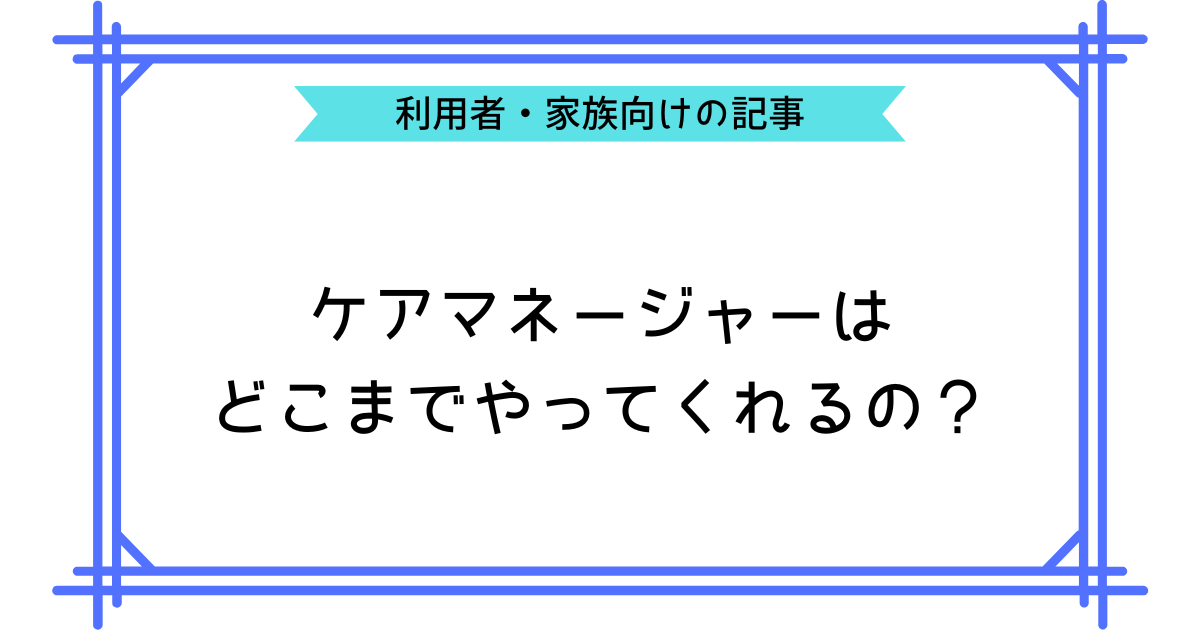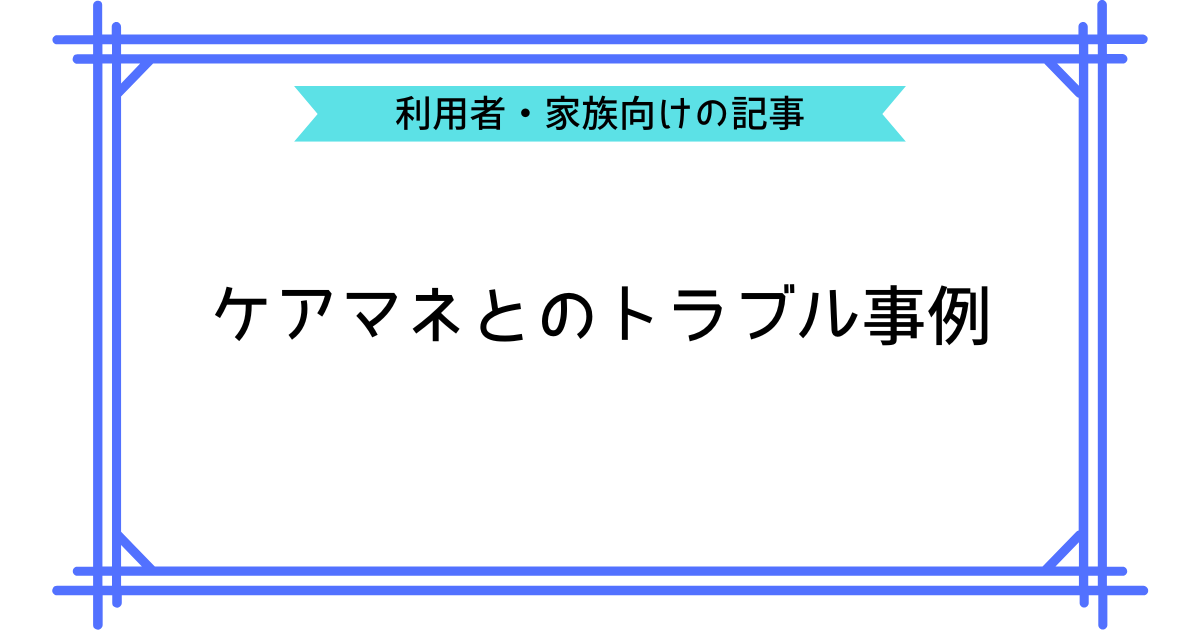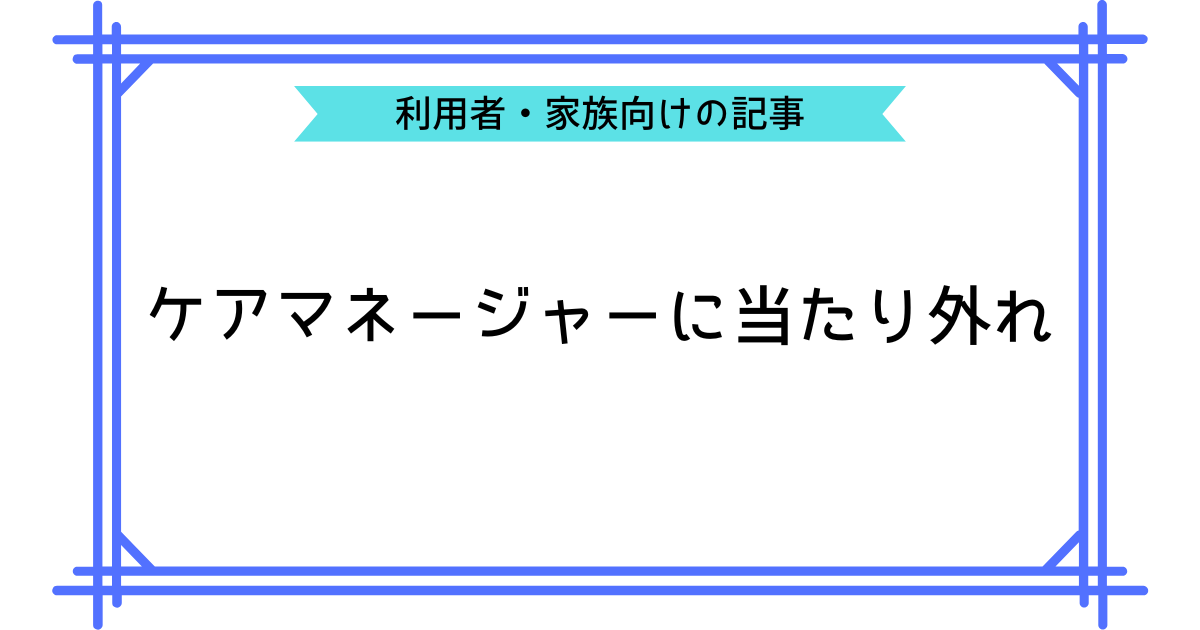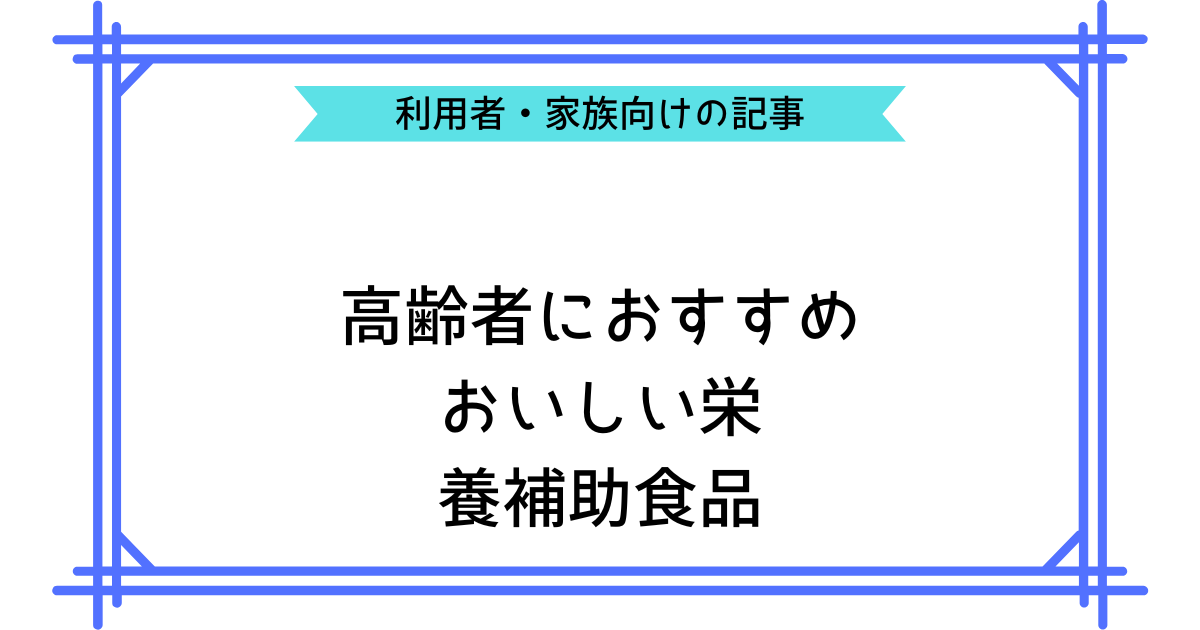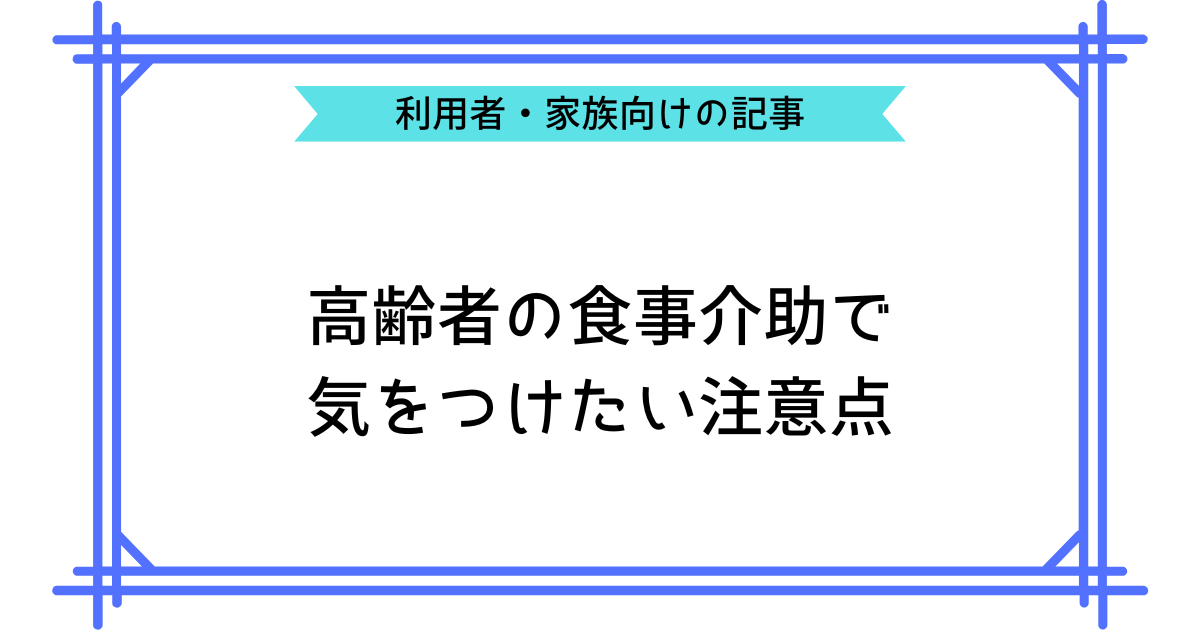とろみ剤の選び方とつける理由とは?おすすめランキング5も紹介
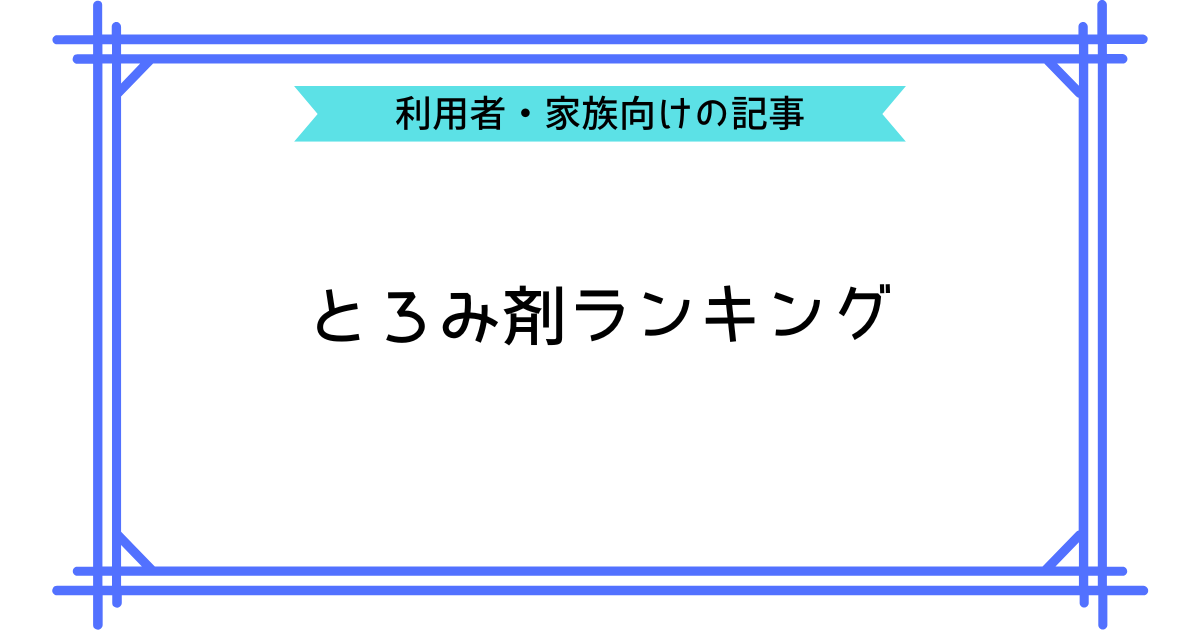
高齢者や嚥下機能が低下している方にとって、水分や食べ物をそのまま飲み込むのは誤嚥(ごえん)のリスクが高く危険です。
そんなときに役立つのがとろみ剤です。飲み物や食事にとろみをつけることで、飲み込みやすさが増し、誤嚥性肺炎の予防にもつながります。
しかし「とろみ剤は種類が多すぎて選び方が分からない」「どんな理由でとろみをつける必要があるのか知りたい」と悩む方も少なくありません。
本記事では、とろみ剤をつける理由や選び方のポイントを解説したうえで、実際に人気のあるとろみ剤をランキング形式で紹介します。
とろみ剤をつける理由
とろみ剤を使用する主な理由は「安全に食べ物や飲み物を飲み込むため」です。嚥下機能が低下すると、水やお茶のようにサラサラした液体は気管に流れ込みやすく、むせ込みや誤嚥につながります。
- 誤嚥性肺炎の予防:気管に入るのを防ぎ、肺炎のリスクを減らす
- 飲み込みやすさの向上:適度な粘度が舌や咽頭にとどまりやすく、飲み込みやすくなる
- 食事の楽しみを継続:とろみをつけることで安全に好きな飲み物や食べ物を味わえる
つまり、とろみ剤は「安全性」と「生活の質(QOL)」を守るために欠かせないアイテムです。
とろみ剤の選び方
とろみ剤を選ぶときには、以下のポイントをチェックしましょう。
使いやすさ(溶けやすさ)
飲み物や料理にサッと溶けやすいかどうかは重要です。ダマになりにくい商品は介護の現場でも重宝されます。
粘度の安定性
時間が経つととろみが強くなりすぎたり、逆に弱まったりする商品もあります。安定した粘度が保てるものを選ぶと安心です。
味や風味への影響
とろみ剤によってはわずかに苦みや違和感が残る場合があります。できるだけ「無味無臭」に近いものを選ぶと食事が楽しく続けられます。
用途や対象者に合わせる
- 飲み物中心 → 溶けやすいタイプ
- 食事全般に使用 → 粘度が安定するタイプ
- 医療現場 → エビデンスや使用実績のあるメーカー
利用シーンを想定して選ぶことが大切です。
おすすめのとろみ剤ランキング
1位:和光堂 とろみエール
大手ベビーフードメーカーの和光堂が展開する商品で、介護食にも広く活用されています。少量でもしっかりとろみがつき、飲み物にも料理にも使いやすいのが特徴。ダマになりにくく、ご家庭でも病院・施設でも人気があります。
2位:日清オイリオ トロミアップ パーフェクト
業界でもトップクラスのシェアを誇る日清オイリオのとろみ剤です。溶けやすく、しかも粘度が長時間安定するため、現場の介護職や看護師から高く評価されています。無味無臭で飲み物の風味を損なわない点もメリットです。
3位:明治 かんたんトロメイク
乳製品で知られる明治が手掛けるとろみ剤。特に「とろみの調整がしやすい」と評判で、初めてとろみ剤を使う方にもおすすめです。溶けやすさと安定性のバランスが良く、在宅介護でも施設でも安心して使用できます。
4位:森永乳業 クリニコ つるりんこ Quickly
森永乳業の介護食ブランド「クリニコ」から販売されている商品で、スピーディーにとろみがつくのが特徴。名前の通り素早く混ざり、粘度の調整もしやすいため、忙しい現場で特に便利です。
5位:ニュートリー ソフティアS とろみ食用
医療・介護分野で高い信頼を得ているニュートリーの商品です。安定性に優れ、温かい飲み物から冷たい飲み物まで幅広く対応可能。少量で十分な粘度が得られるため、コストパフォーマンスも高いのが魅力です。
まとめ
とろみ剤は、嚥下機能が低下した高齢者や病気のある方にとって、安全に食事や水分補給を続けるための必須アイテムです。
- つける理由:誤嚥性肺炎を防ぎ、飲み込みやすさを高めるため
- 選び方:溶けやすさ・粘度の安定性・味への影響・用途を基準に選ぶ
- おすすめ商品:和光堂、とろみアップ、かんたんトロメイク、つるりんこ、ソフティアS
ぜひ本記事を参考に、利用者や家族に合ったとろみ剤を選んでみてください。