介護保険の特定疾病とは?覚え方をわかりやすく解説
当ページのリンクには広告が含まれています。
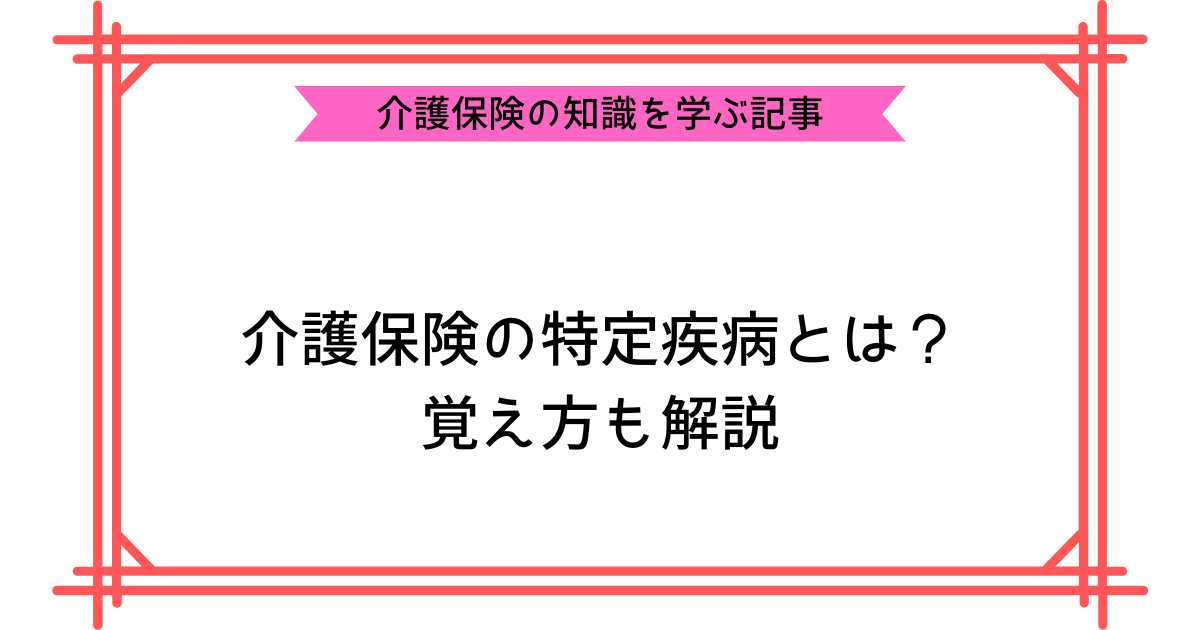
介護保険制度では、65歳以上の方は原因を問わず介護保険を利用できますが、40歳以上65歳未満の方は「特定疾病」による介護が必要な場合のみ介護保険の対象 となります。
そのため、ケアマネジャー試験や介護福祉士試験などでも頻出ポイントとなるのが「特定疾病の覚え方」です。
この記事では、特定疾病の定義・20種類の一覧・効率的な覚え方 をまとめました。
目次
介護保険における特定疾病とは?
介護保険制度でいう「特定疾病」とは、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が介護保険サービスを利用できる対象疾患のことです。
厚生労働省が定めており、老化に伴って発症しやすく、日常生活に介護が必要になる可能性が高い病気が選ばれています。
特定疾病の一覧(16種類)
介護保険で定められている特定疾病は 16種類 です。以下に整理しました。
- がん(医師が回復の見込みなしと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 末期腎不全
特定疾病の覚え方(ゴロ合わせ)
試験対策ではこの16種類をまとめて覚える必要があります。そこで便利なのが ゴロ合わせ です。
ゴロ合わせ例
「がん関す(筋)こう骨、認知・進行・小脳せき、早多糖脳へいまつ」
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨粗鬆症骨折
- 認知症(初老期)
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病合併症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 末期腎不全
少し強引ですが、リズムで覚えると記憶に残りやすいです。
分類で覚える方法
ゴロ合わせが苦手な方は、ジャンル分け で整理すると理解しやすくなります。
- がん系:がん(回復見込みなし)
- 骨・関節系:関節リウマチ、骨粗鬆症骨折、後縦靱帯骨化症、脊柱管狭窄症
- 神経系:ALS、進行性核上性麻痺など、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症
- 認知症系:初老期認知症
- 代謝・内科系:糖尿病合併症、末期腎不全、COPD
- 循環器系:脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症
- その他:早老症
系統ごとに覚えることで、イメージと結びつけやすくなります。
まとめ|特定疾病は「40〜64歳でも介護保険が使える条件」
介護保険における特定疾病とは、40歳以上65歳未満の人が介護保険を利用できる対象となる16種類の病気 です。
覚えるコツは、
- ゴロ合わせで一気に暗記する
- 系統ごとに整理して理解する
試験対策だけでなく、実務でも利用者の介護保険適用可否を判断するうえで必須の知識です。















