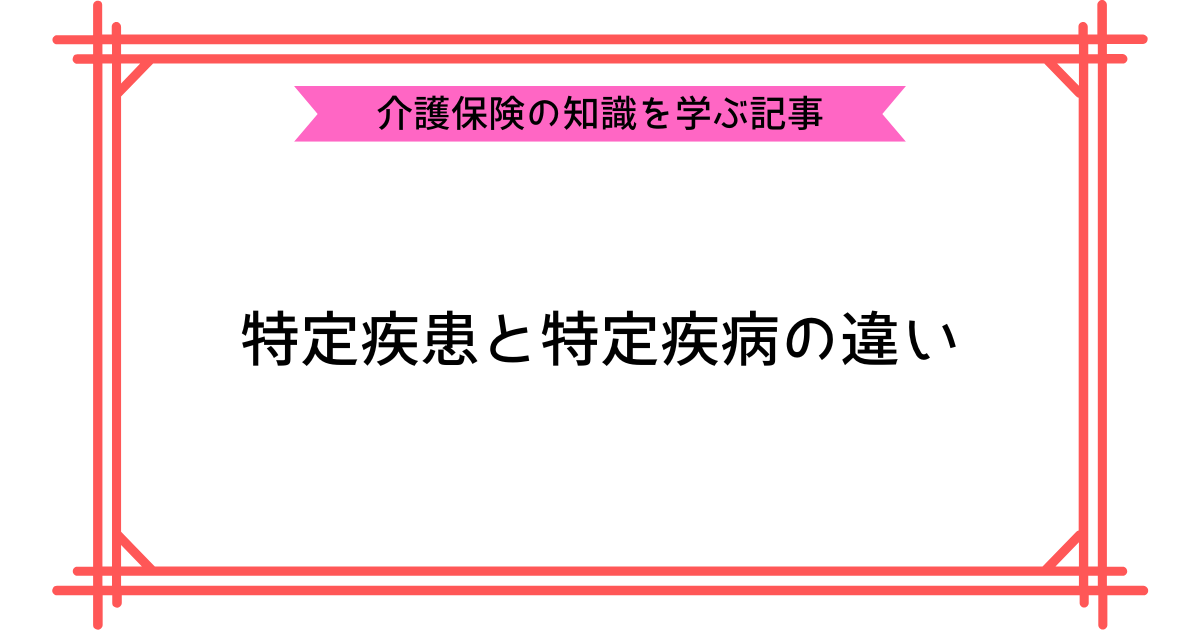主治医意見書とは?わかりやすく解説|介護保険の要介護認定に必要な書類
当ページのリンクには広告が含まれています。

介護保険を利用するためには「要介護認定」を受ける必要があります。その際に重要な役割を果たすのが 「主治医意見書」 です。
しかし、「主治医意見書ってどんな書類?」「誰が書くの?」「何に使われるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、主治医意見書の意味・記載内容・役割・注意点 をわかりやすく解説します。
目次
主治医意見書とは?
主治医意見書とは、介護保険の要介護認定を行う際に、かかりつけ医が利用者の心身の状態を医学的に記録する書類 のことです。
市区町村が介護保険の申請を受けると、必ず本人の「主治医」に意見書の作成を依頼します。
医師が記入した主治医意見書は、認定調査の結果と合わせて審査判定に使われ、要介護度を決定する重要な資料となります。
主治医意見書に記載される内容
主治医意見書には、利用者の医療的な状態が詳細に記録されます。主な項目は以下の通りです。
- 診断名(現在の病気や既往症)
- 心身の状態(歩行能力、認知機能、ADLの状況など)
- 日常生活における支障(排泄、入浴、食事など)
- 認知症の有無や行動・心理症状(BPSD)の有無
- 医療的管理の必要性(点滴、酸素療法、インスリン注射など)
- 今後の見通しや配慮すべき事項
この情報により、介護の必要度が客観的に判断されます。
主治医意見書の役割
主治医意見書は、介護保険制度における 「医学的な裏づけ」 としての役割を果たしています。
- 認定調査だけでは把握できない医学的な情報を補足する
- 医療と介護の連携を図るための基礎資料となる
- 要介護認定審査会で、医学的視点から要介護度を決める根拠となる
つまり、本人がどの程度介護を必要としているかを 医学と介護の両面から判断するための必須書類 なのです。
主治医意見書の注意点
- 主治医がいない場合:申請者が希望する医師に依頼できる
- 費用は不要:介護保険制度に基づく書類作成のため、本人が費用を負担することはありません
- 記載内容は介護度に大きく影響する:医師に自分の状態を正しく伝えることが大切
特に「普段は元気に見えるが、実際には生活で困っていることが多い」というケースでは、家族やケアマネジャーが情報を補足することが望ましいです。
まとめ|主治医意見書は介護保険の「医学的な証明書」
主治医意見書とは、要介護認定に必要な医学的情報を記録した書類で、利用者の主治医が作成します。
- 医師が診断名や心身の状態を記載する
- 要介護認定の判定に欠かせない資料になる
- 医療と介護の連携を支える役割を持つ
介護保険を利用する際には必ず必要になるため、かかりつけ医との連携を大切にし、正確な情報が記載されるように準備しておきましょう。