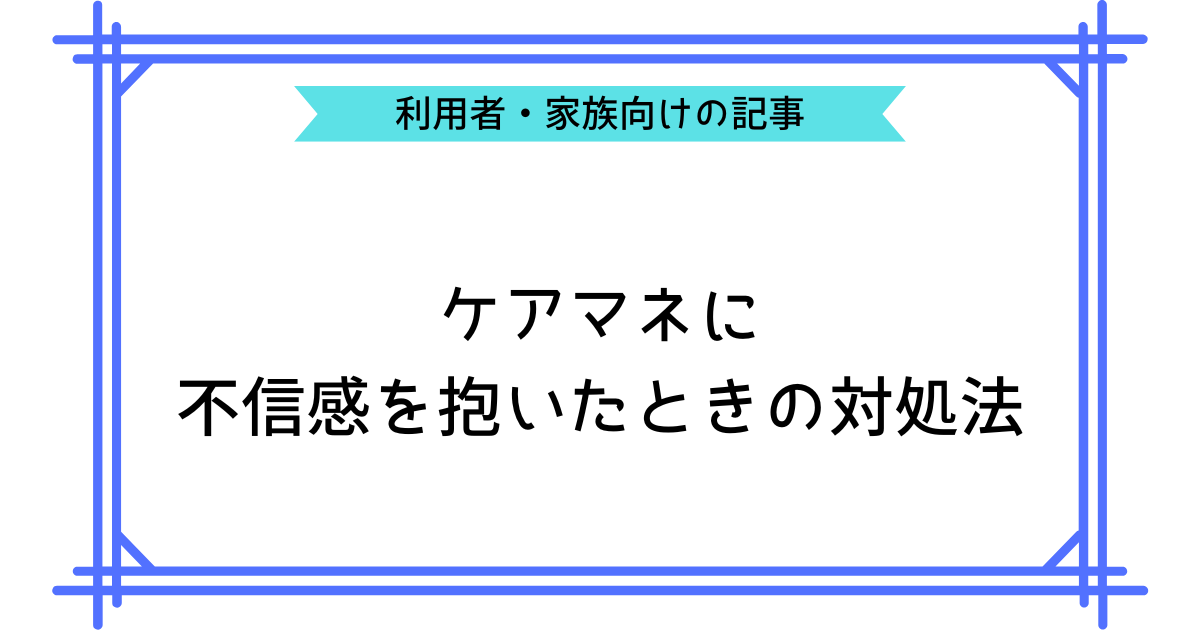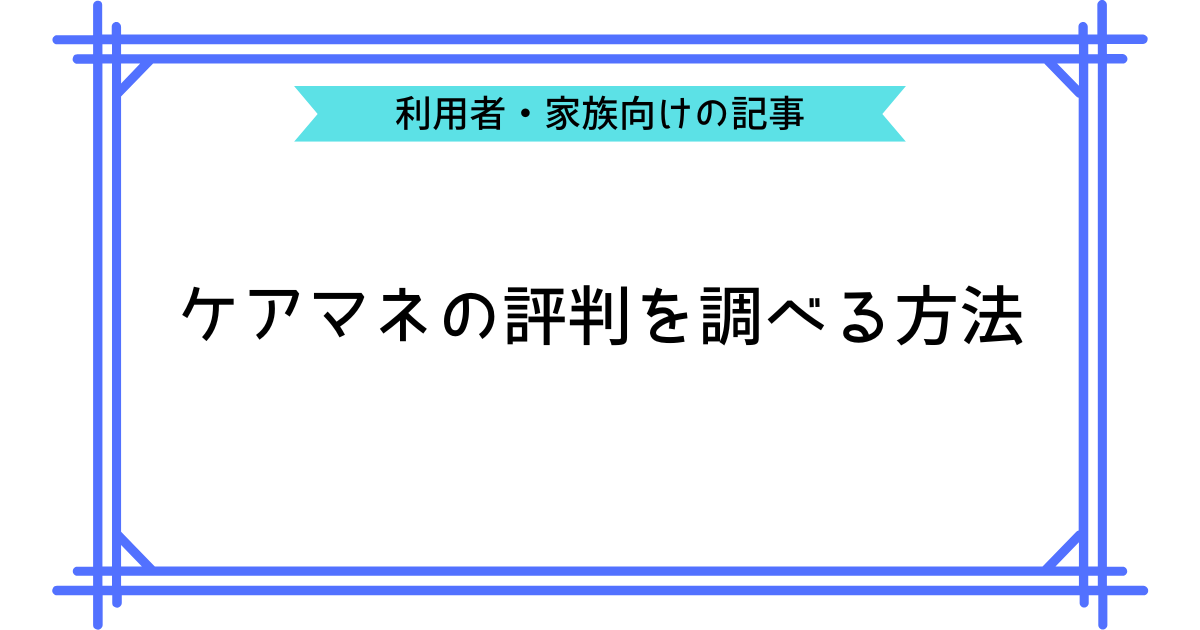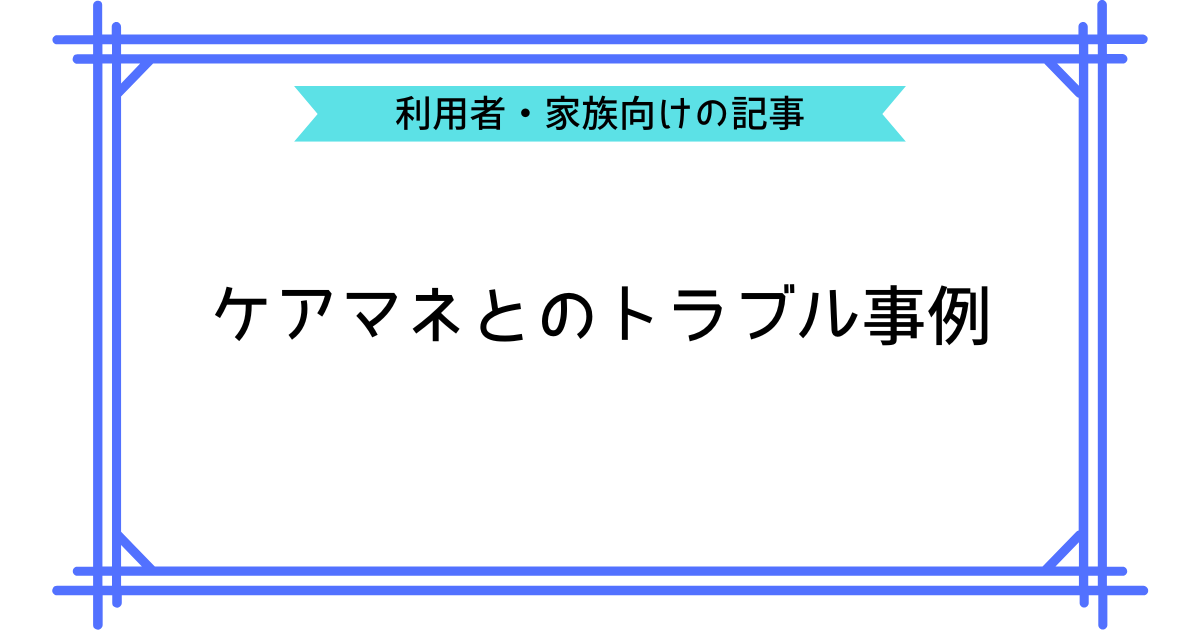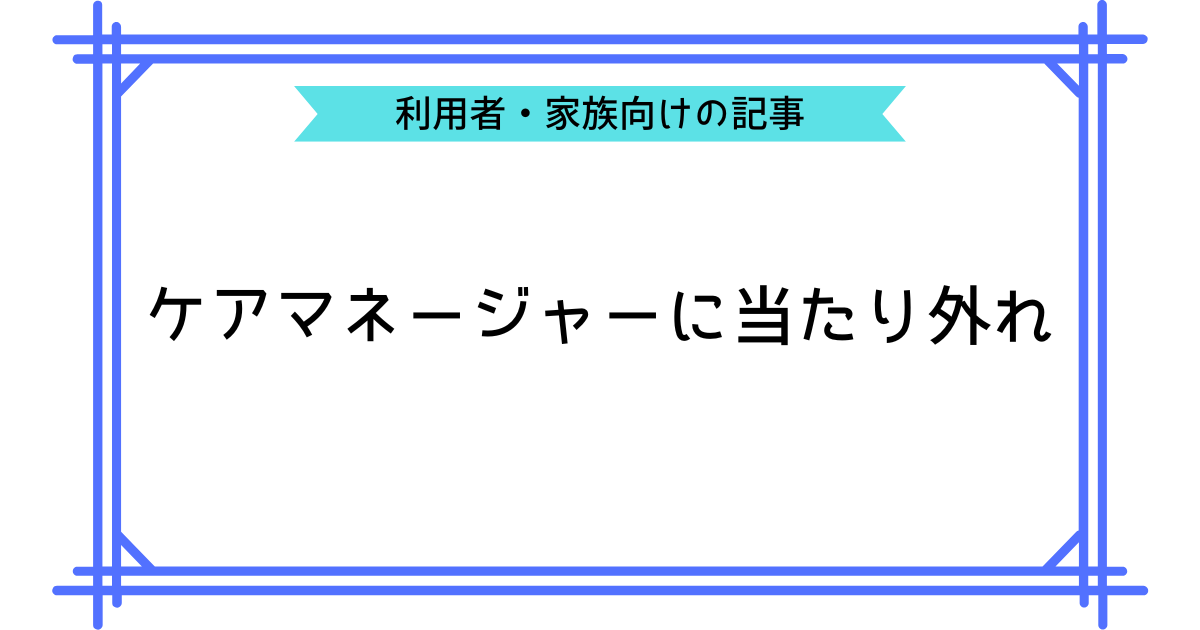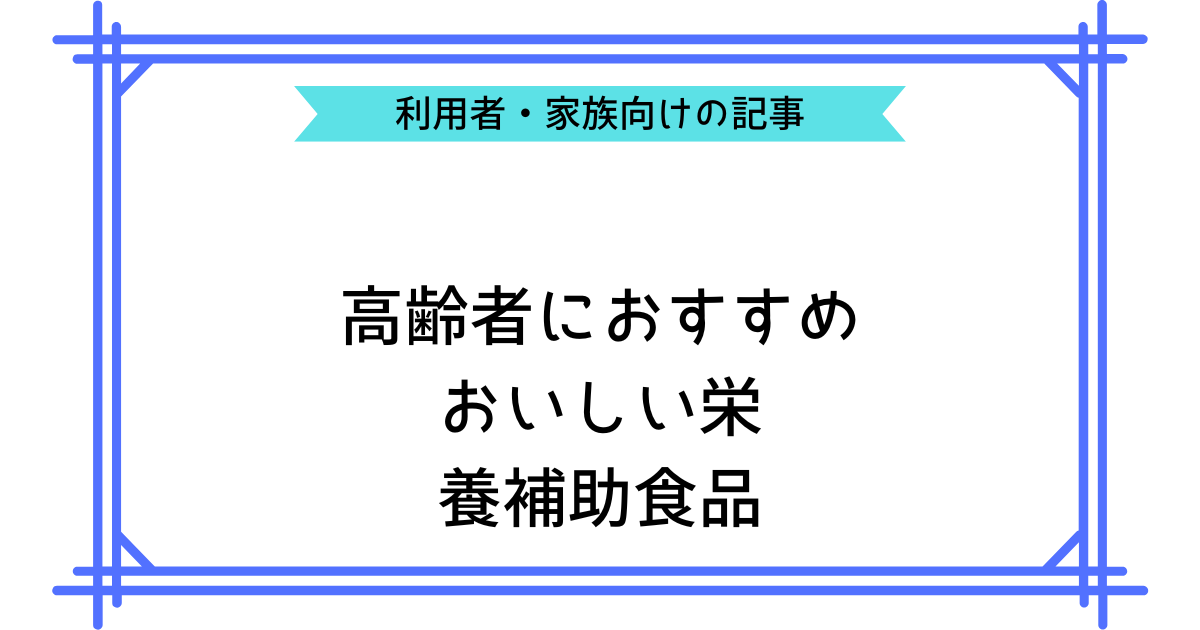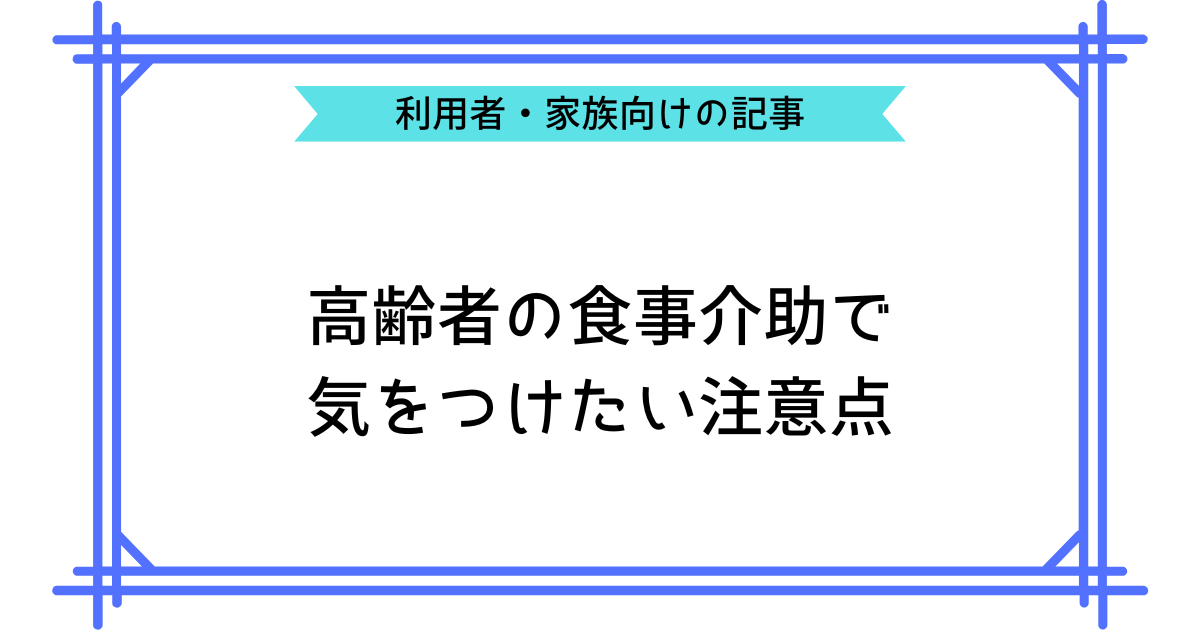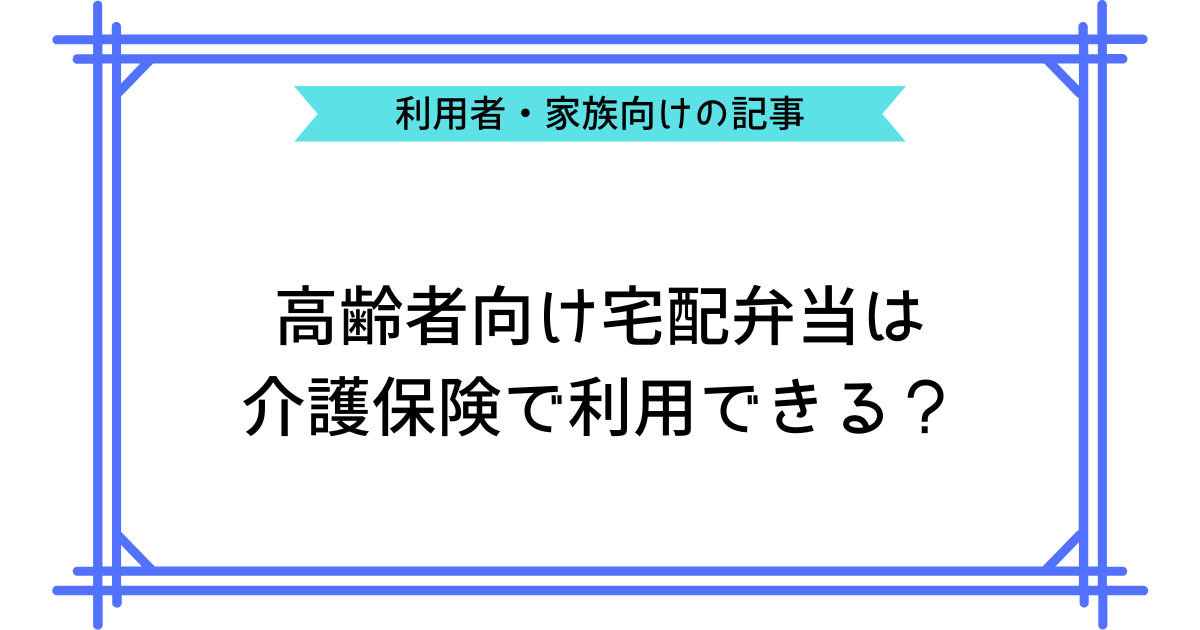ケアマネージャーはどこまでやってくれるの?できること・できないことを解説
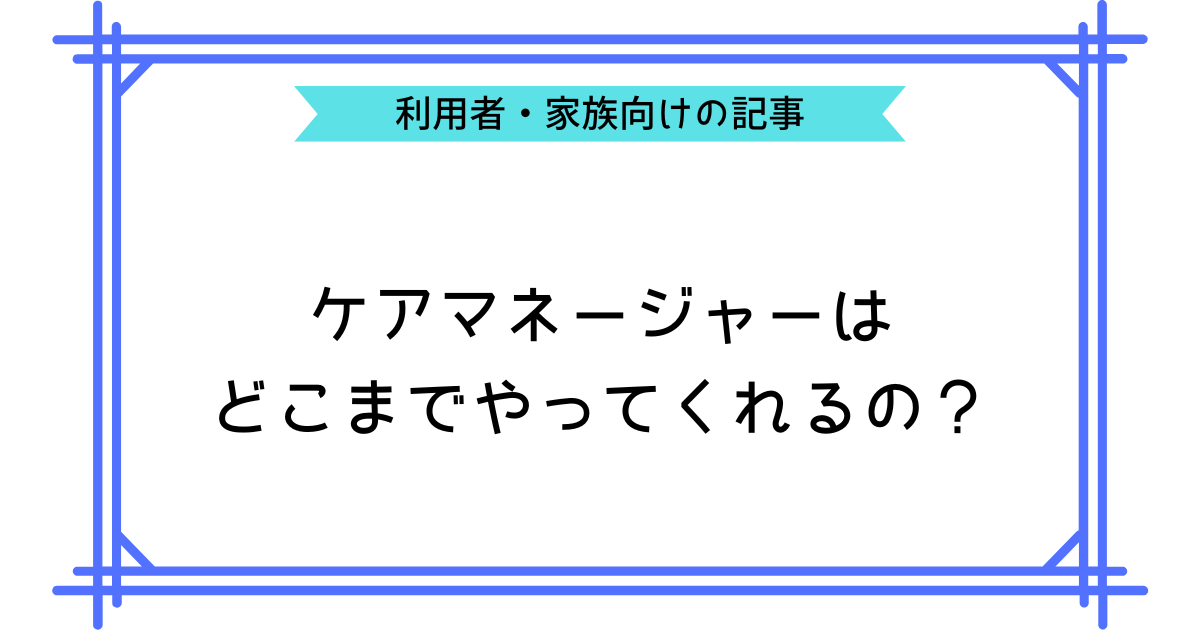
介護を始めたばかりのご家族やこれから介護サービスを利用したい方からよく聞かれる質問が「ケアマネージャー(介護支援専門員)はどこまでやってくれるの?」というものです。
ケアマネは介護保険制度の中心的な存在ですが、できることには範囲があり、すべてを任せられるわけではありません。
この記事では、ケアマネが実際にどこまでやってくれるのか、できることとできないことの線引きをわかりやすく解説します。
ケアマネージャーがやってくれること
ケアプラン(介護サービス計画書)の作成
ケアマネの最も大切な仕事は、利用者一人ひとりの状況に合わせたケアプランを作成することです。要介護認定を受けた方に対し、どのサービスをどのくらい利用するのが適切かを検討し、デイサービスや訪問介護、訪問看護、福祉用具レンタルなどを組み合わせてプランを立てます。
介護サービス事業者との調整
利用者とサービス事業者の橋渡し役を担います。例えば「週3回デイサービスを利用したい」「訪問介護を増やしたい」といった要望を事業所に伝え、利用開始に必要な契約や日程調整を行います。複数の事業者と連携するケースも多く、利用者や家族が自分で調整する手間を減らせます。
サービス担当者会議の開催
介護サービスを利用する際には、関わるスタッフ(介護職員、看護師、リハ職、相談員など)が集まってサービス担当者会議を開きます。ケアマネはこの会議を主催し、利用者や家族の希望を伝え、サービスの方向性を多職種と一緒に検討します。
モニタリング(継続的な見守り)
ケアマネは定期的に利用者や家族と面談し、サービスが適切に提供されているか、生活に変化がないかを確認します。体調の変化や家族の負担増などを把握し、必要に応じてケアプランを修正します。
介護保険に関する手続きのサポート
要介護認定の申請や更新手続き、主治医意見書の準備、介護保険サービスの利用開始に必要な書類のやり取りなど、制度上の事務的な支援も行います。介護保険に関して不安があれば、ケアマネに相談するのが基本です。
ケアマネージャーがやってくれないこと
直接的な介護サービスの提供
ケアマネは介護職員ではないため、食事介助や入浴介助、排泄介助といった介護サービスそのものを直接行うことはできません。これらは訪問介護員や施設スタッフの役割です。
医療行為
点滴、採血、注射、服薬管理などの医療行為は医師や看護師の専門領域です。ケアマネは医療職と連携はしますが、自ら行うことはできません。
金銭や財産の管理
利用者の年金や預金を預かったり、代わりに買い物や振込をすることはできません。これらは成年後見人や家族が担う領域であり、ケアマネが行うとトラブルにつながります。
家族に代わっての介護全般
「介護を全部任せたい」と思う家族もいますが、ケアマネはあくまで“計画と調整役”です。実際の介護はサービス事業者や家族が担います。ケアマネは必要な介護を組み立てる存在であり、“代理介護者”ではありません。
ケアマネに相談できること
- 「どの介護サービスを使えばいいかわからない」
- 「介護保険の申請をどうしたらよいか知りたい」
- 「急に介護が必要になり、何から始めればいいかわからない」
- 「デイサービスや訪問介護を増やしたい」
- 「介護費用がどのくらいかかるか見通しを立てたい」
このような疑問や不安は、すべてケアマネに相談可能です。ケアマネは“介護の総合窓口”といえる存在です。
ケアマネを活用するメリット
ケアマネを通じて介護サービスを利用することで、利用者や家族は自分で事業所を探したり、契約調整を行う負担を大幅に減らせます。
また、利用者の状態が変化したときにすぐプランを変更してもらえるため、柔軟で安心できる介護が実現します。
特に介護に初めて直面する家族にとって、ケアマネの存在は心強いサポーターです。
まとめ
ケアマネージャーは「介護サービスの設計と調整」をしてくれる専門職です。
ケアプラン作成、サービス調整、手続き支援、継続的なモニタリングなどを行ってくれますが、介護そのものや医療行為、金銭管理などはできません。
つまりケアマネは「介護の道案内役」として、本人と家族が安心して暮らせるよう支える存在です。
介護に不安があれば、まずケアマネに相談することが最初の一歩となるでしょう。