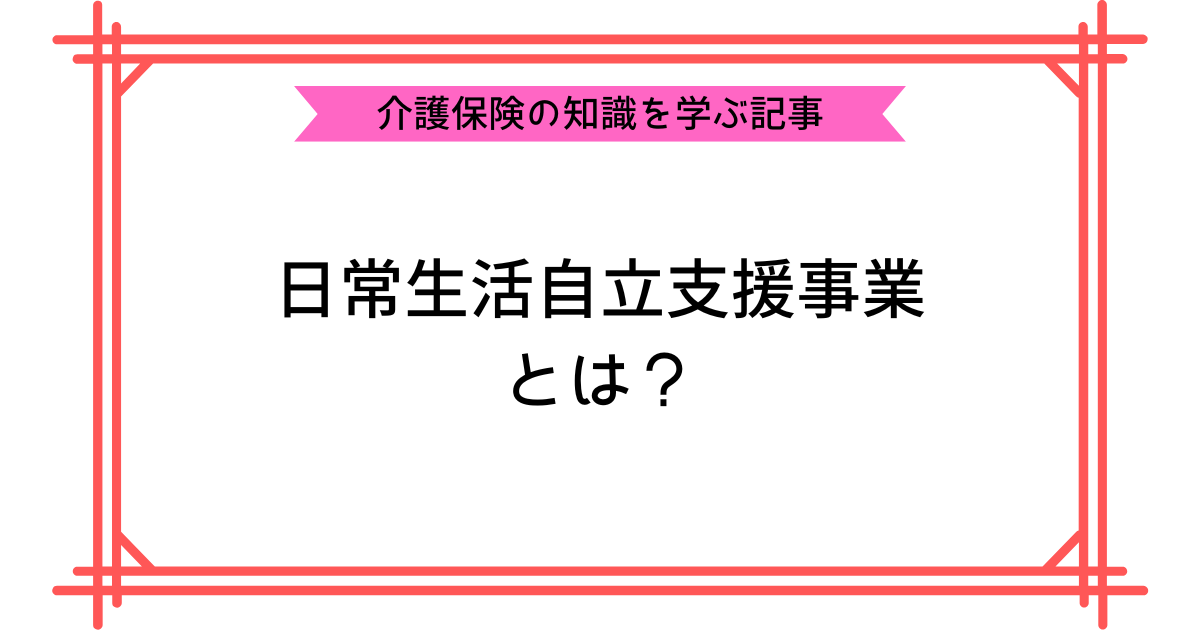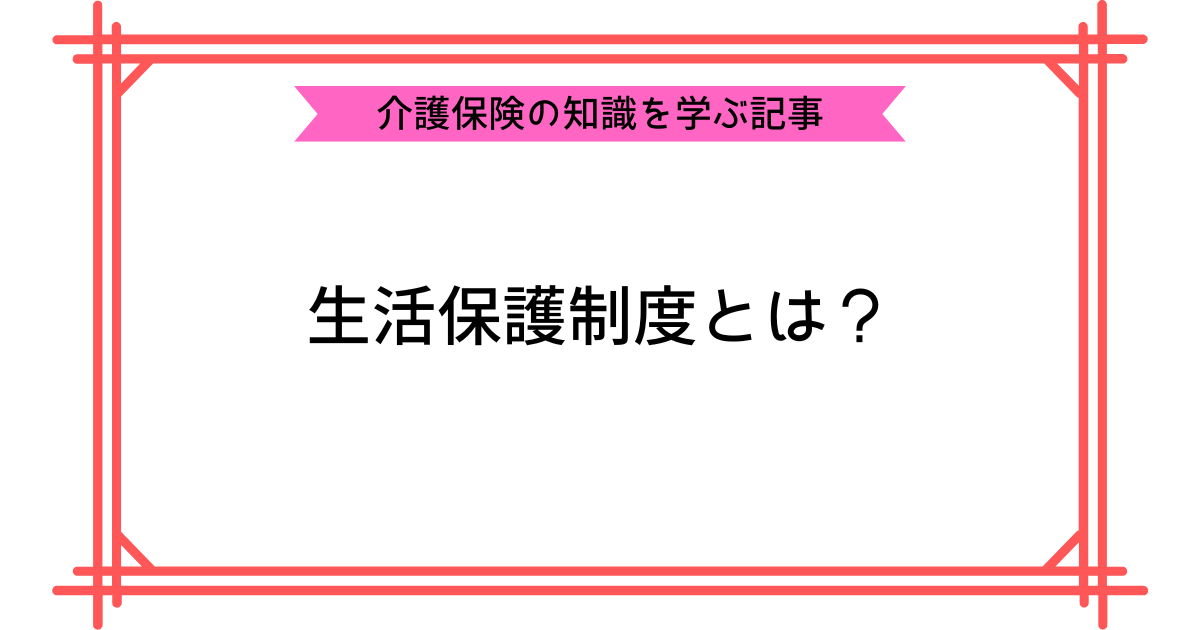生活困窮者自立支援法とは?一般人にもわかりやすく解説
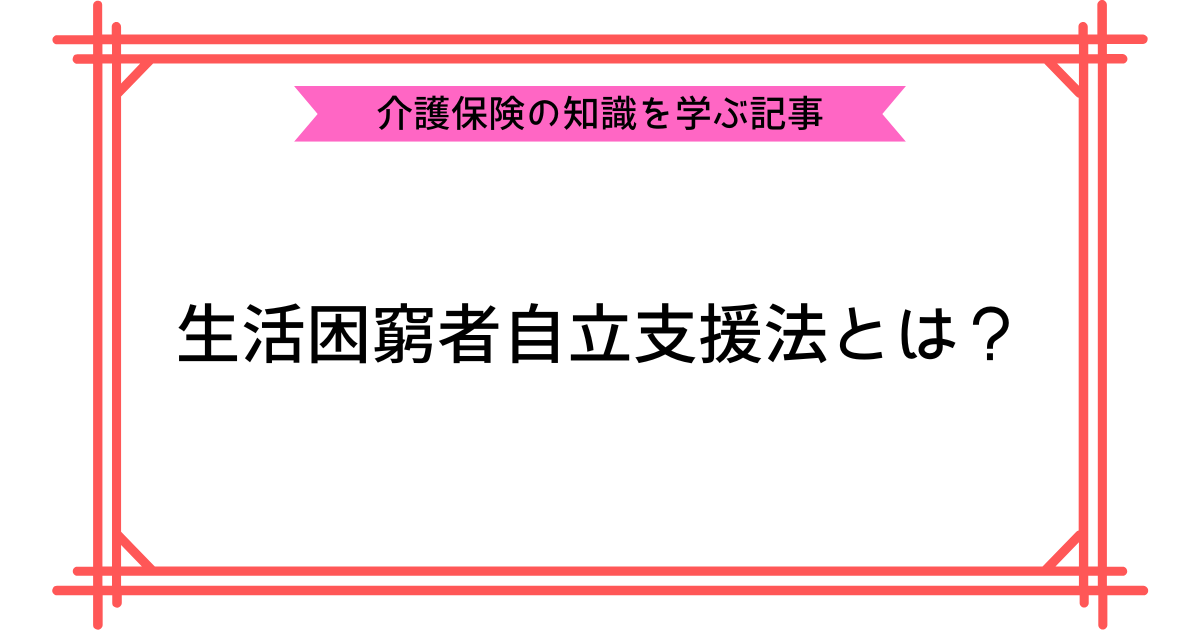
「生活が苦しくて働けない」「仕事を探してもなかなか見つからない」「家賃や生活費が払えない」――。
こうした問題に直面したときに頼りになるのが生活困窮者自立支援法です。
この法律は、生活保護を受ける前の段階で困窮している人を支援し、自立した生活に戻れるようにサポートするための仕組みです。
本記事では、「生活困窮者自立支援法とは何か?」を、法律に詳しくない一般の方にも分かりやすく解説します。
制度の目的や内容、利用できる支援、生活保護との違いなどを整理して紹介します。
生活困窮者自立支援法とは?
制定の背景
2015年4月に施行された「生活困窮者自立支援法」は、生活保護に至る前の段階で困窮している人を支えるためのセーフティネットとして制定されました。
従来の制度では「生活保護に該当するかどうか」が支援の分かれ目でしたが、その前段階で「生活に困っているけれど、生活保護を受けるほどではない人」が支援からこぼれ落ちていました。
こうした課題を解決するために、生活困窮者を幅広く対象に支援する法律として整備されたのです。
生活困窮者自立支援法の目的
- 生活困窮状態からの脱却を支援
- 就労や社会参加を通じた自立を促進
- 生活保護に至る前にサポートする予防的な仕組み
- 誰でも相談できる「入り口の広い」支援制度の整備
つまり、「生活に困っているけど、どうすればいいか分からない」人を社会全体で支えることが目的です。
生活困窮者自立支援法で受けられる主な支援
法律に基づき、市区町村には自立相談支援機関が設置されています。
ここで相談すると、困っている状況に応じてさまざまな支援が受けられます。
1. 自立相談支援事業
相談員が生活状況を聞き取り、一緒に「自立に向けたプラン」を作成。就労、生活、家計、健康など幅広い分野をサポートします。
2. 住居確保給付金
失業などで住居を失う恐れがある人に、家賃相当額を一定期間支給する制度です。住宅を失うリスクを防ぎます。
3. 就労準備支援事業
長期間働いていない人や、すぐに就職が難しい人向けに、生活リズムを整えたり、就労に必要な基礎スキルを身につけたりする支援です。
4. 就労訓練事業(中間的就労)
すぐに一般就労が難しい人が、地域の企業や団体で就労体験をしながら働く力をつける取り組みです。
5. 家計改善支援事業
家計のやりくりに困っている人に対して、収支の整理や家計簿の作成を一緒に行い、借金や滞納の解決を支援します。
6. 一時生活支援事業
住まいを失った人に対して、シェルターや一時的な宿泊場所を提供し、生活再建につなげます。
生活困窮者自立支援法の対象となる人
- 失業して収入がなくなった人
- 非正規雇用で収入が安定せず生活が苦しい人
- 借金や家賃滞納で生活が立ち行かない人
- 引きこもりや病気で働けず収入が途絶えた人
- 生活保護を受けるほどではないが困っている人
つまり、生活に困っているすべての人が対象になり得るのが大きな特徴です。
生活困窮者自立支援法と生活保護の違い
- 生活困窮者自立支援法
- 「生活保護に至る前」の支援
- 自立を促すことが目的
- 就労支援や家計改善などが中心
- 原則として生活費全般の給付はない
- 生活保護
- 最低限度の生活を保障する制度
- 生活費や医療費などを包括的に支給
- 自立支援もあるが「最後のセーフティネット」
生活困窮者自立支援法は、生活保護に陥る前に「生活再建をサポートする制度」と位置づけられます。
利用するにはどうすればいい?
- 市区町村の自立相談支援機関に連絡
- 相談員による面談で状況を把握
- 必要に応じて「支援プラン」を作成
- 住居確保給付金や就労訓練などにつなげる
役所に直接行ってもよいですし、電話やメール相談が可能な自治体もあります。
生活困窮者自立支援法のメリットと課題
メリット
- 幅広い人が相談できる「入り口の広さ」
- 生活保護を受ける前の段階で支援が受けられる
- 就労支援だけでなく、住居・家計・生活全般を包括的に支援
課題
- 支援内容が自治体ごとに異なり、地域差がある
- 支援を受けても就労につながらないケースもある
- 制度自体が十分に知られていない
まとめ
生活困窮者自立支援法は、生活に困っている人が生活保護に陥る前に自立を目指すための支援制度です。
- 自立相談支援、住居確保給付金、就労支援、家計改善支援など幅広いサービスがある
- 生活保護との違いは「自立に向けた支援」が中心である点
- 誰でも相談できる身近なセーフティネットとして機能している
生活が苦しく「どうしたらいいか分からない」と思ったら、一人で抱え込まずに自立相談支援機関に相談することが第一歩です。