後期高齢者医療制度とは?一般人にもわかりやすく解説
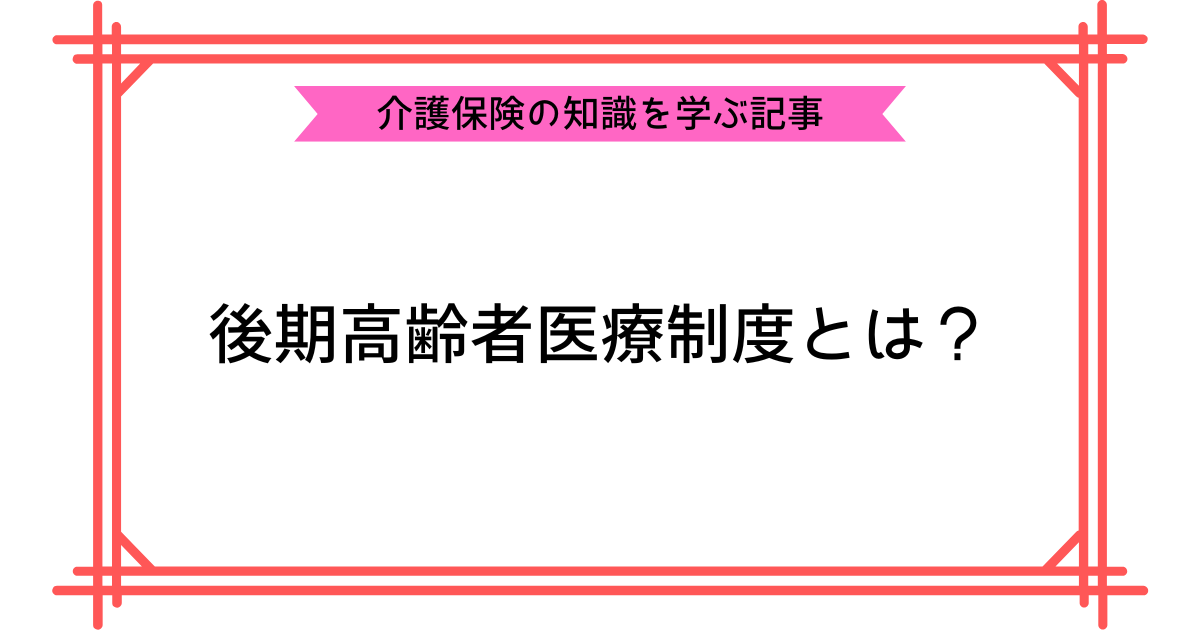
日本は世界でも有数の長寿国であり、高齢化が急速に進んでいます。その中で「後期高齢者医療制度」という仕組みを耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、「75歳以上はどうやって医療費を払っているの?」「高齢者医療費の自己負担はどのくらい?」といった疑問を持つ人も少なくありません。
本記事では、後期高齢者医療制度とは何かを、法律や制度に詳しくない方でも理解できるように分かりやすく解説します。
制度の概要や自己負担割合、加入方法、保険料の仕組み、注意点などを整理して紹介します。
後期高齢者医療制度とは?
制度の概要
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方(または65歳以上で一定の障害がある方)が対象となる医療保険制度です。2008年に創設され、従来の国民健康保険や被用者保険から独立した形で運営されています。
この制度の大きな特徴は、
- 高齢者の医療を社会全体で支える仕組み
- 都道府県ごとに設立された「後期高齢者医療広域連合」が運営
- 医療費の一部を本人が負担し、残りを公費と現役世代の保険料で賄う
という点です。
対象となる人
- 75歳以上のすべての方
- 65歳〜74歳で一定の障害があり、広域連合から認定を受けた方
これらの方は自動的に後期高齢者医療制度に加入し、それまで加入していた健康保険や国民健康保険から切り替わります。
自己負担割合はどのくらい?
医療機関で診察を受けるときの自己負担割合は、所得に応じて次のように決められています。
- 原則 1割負担
- 現役並み所得者は 3割負担
- 一定以上の所得者は 2割負担(2022年10月から導入)
つまり、同じ後期高齢者でも所得水準によって負担額が変わります。低所得者の方には軽減措置もあります。
保険料の仕組み
後期高齢者医療制度の保険料は、次の2つで構成されています。
- 均等割(定額部分)
加入者全員が一律で負担する部分。 - 所得割(所得に応じた部分)
前年の所得に応じて決まる部分。
保険料は、年金から天引きされる「特別徴収」が基本ですが、口座振替などで支払うことも可能です。
制度が作られた背景
日本の医療保険制度は「国民皆保険」であり、誰もがどこかの保険に加入しています。しかし、高齢化が進むにつれて高齢者の医療費が急増しました。
従来は国保や被用者保険で高齢者医療を賄っていましたが、制度の持続性に課題が生じたため、
- 高齢者の医療費を明確に分ける
- 現役世代と公費で支える仕組みを作る
という目的で後期高齢者医療制度が導入されました。
後期高齢者医療制度のメリット
- 高齢者の医療費が安定して保障される
- 所得に応じた負担で公平性が保たれる
- 公費(税金)と現役世代の支援で持続可能性を確保
制度の課題
一方で、後期高齢者医療制度には課題も指摘されています。
- 現役世代の負担増加
- 財政難による保険料の上昇リスク
- 「高齢者のみを切り離す制度」との批判
今後さらに高齢化が進む中で、持続可能性をどう確保するかが重要な課題です。
利用するときの注意点
- 必ず保険証を切り替える
75歳の誕生日を迎えると、新しい後期高齢者医療被保険者証が届きます。以前の保険証は使えなくなるため注意が必要です。 - 高額療養費制度が使える
自己負担が高額になった場合は「高額療養費制度」による払い戻しを受けられます。 - 医療費控除も利用可能
年間の医療費が一定額を超えた場合は、確定申告で医療費控除を受けられます。
まとめ
後期高齢者医療制度とは、
- 75歳以上の方や一定の障害を持つ65歳以上の方が加入する医療保険制度
- 所得に応じて1割〜3割の自己負担
- 保険料は均等割と所得割で構成される
- 現役世代と公費で支える仕組み
という特徴を持っています。
少子高齢化が進む日本において、この制度は高齢者の医療を守る大切な仕組みです。利用者本人や家族だけでなく、社会全体で理解しておくべき制度といえるでしょう。















