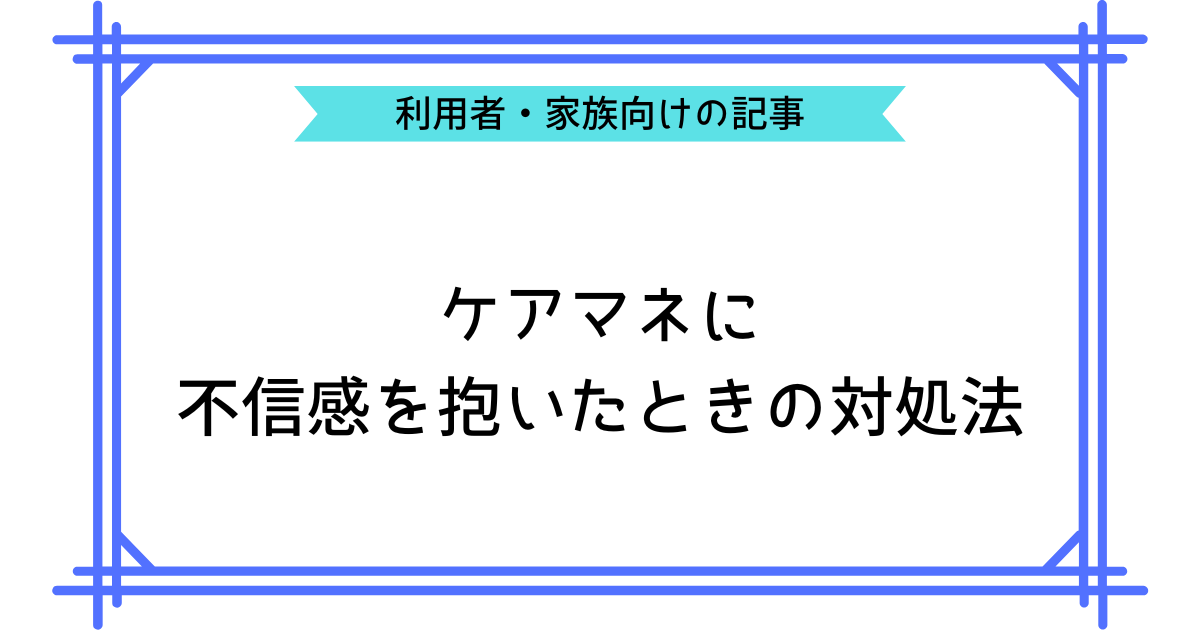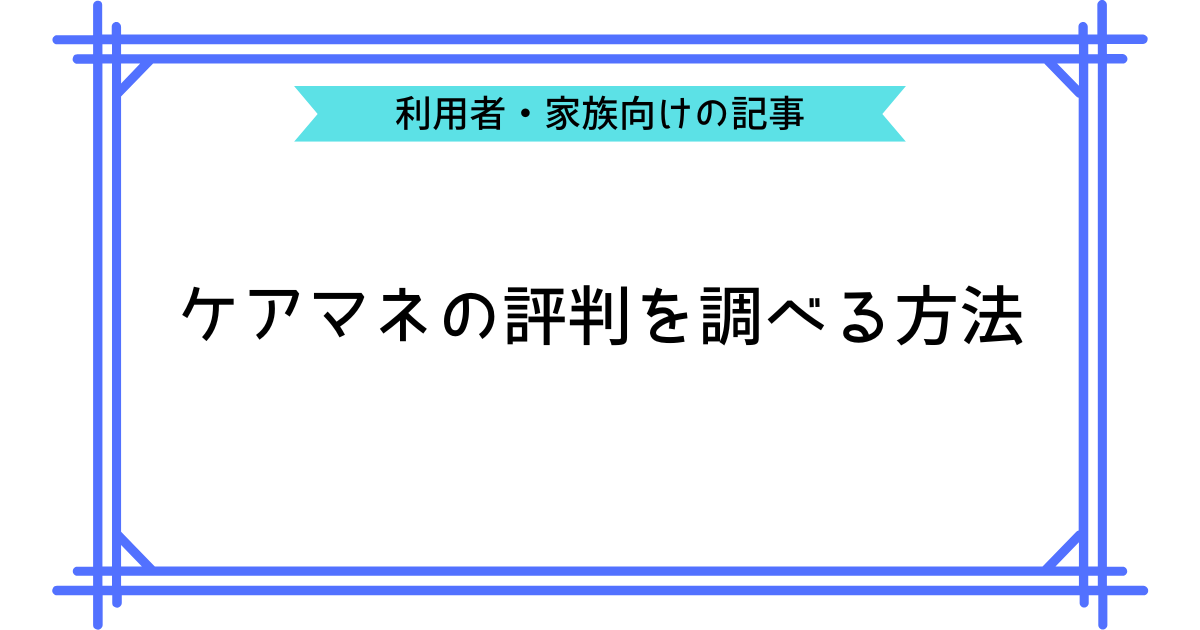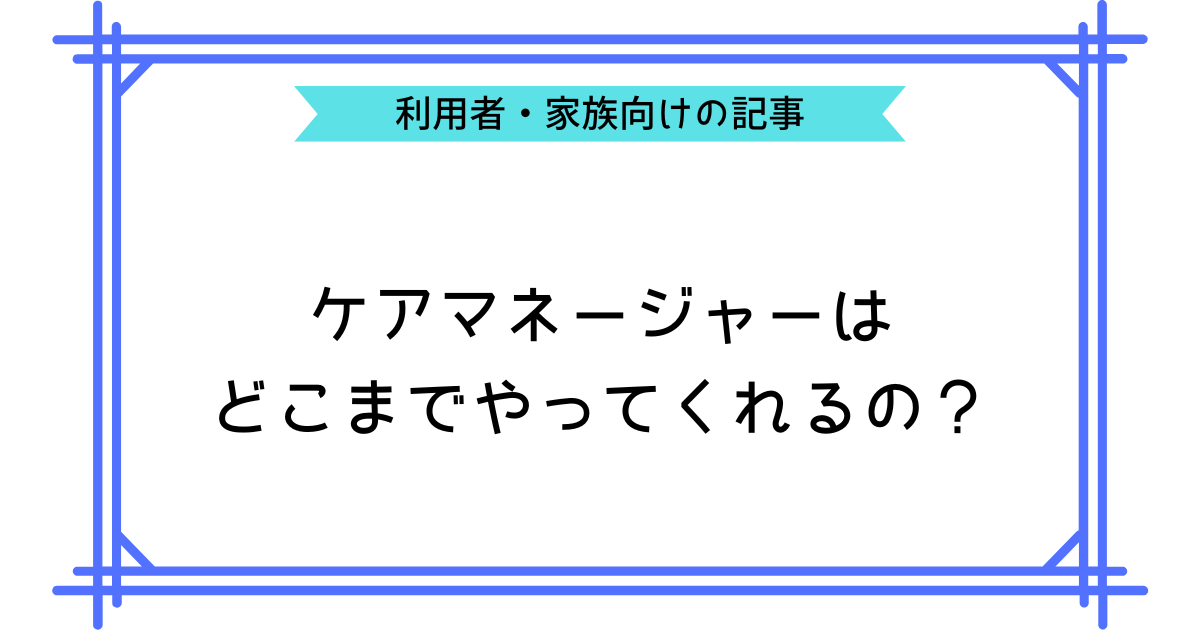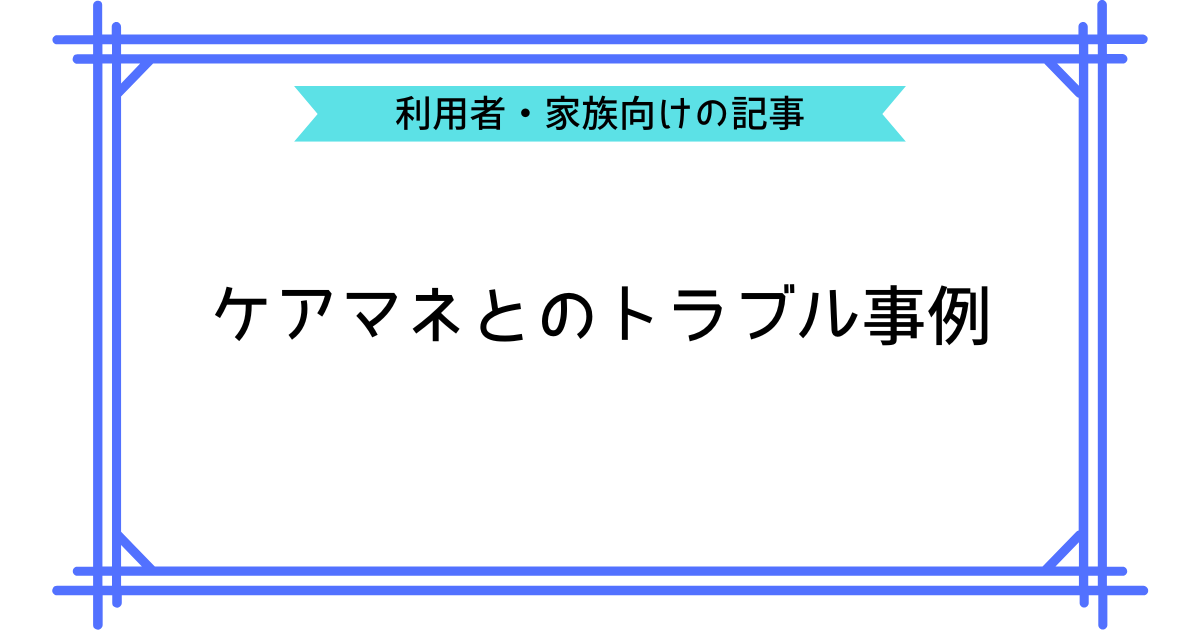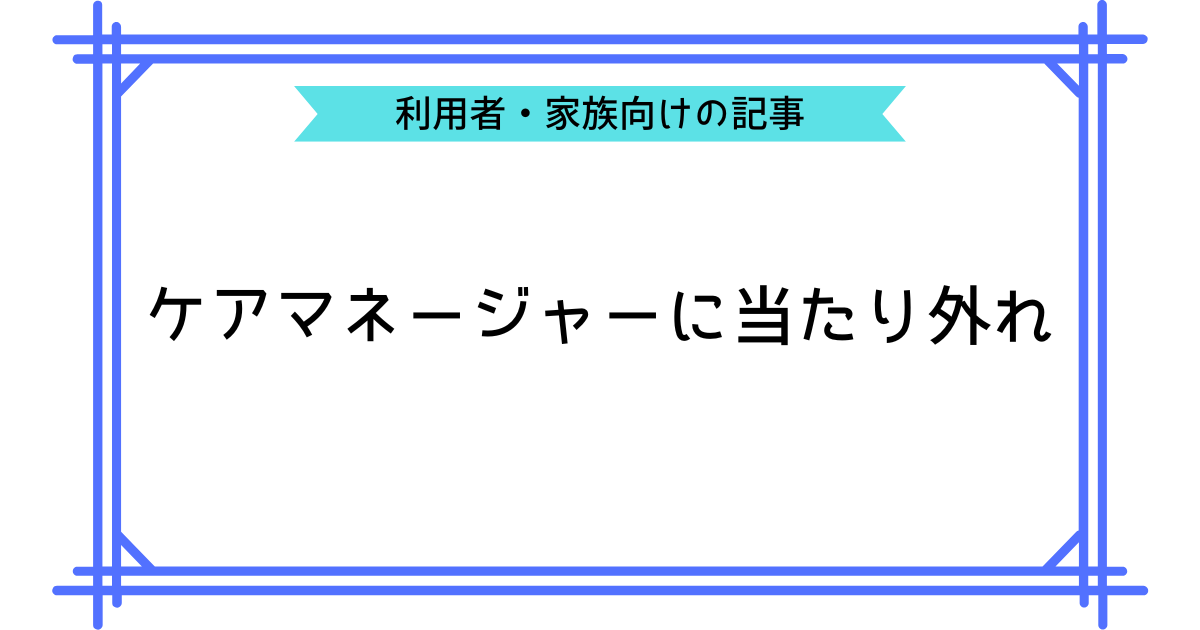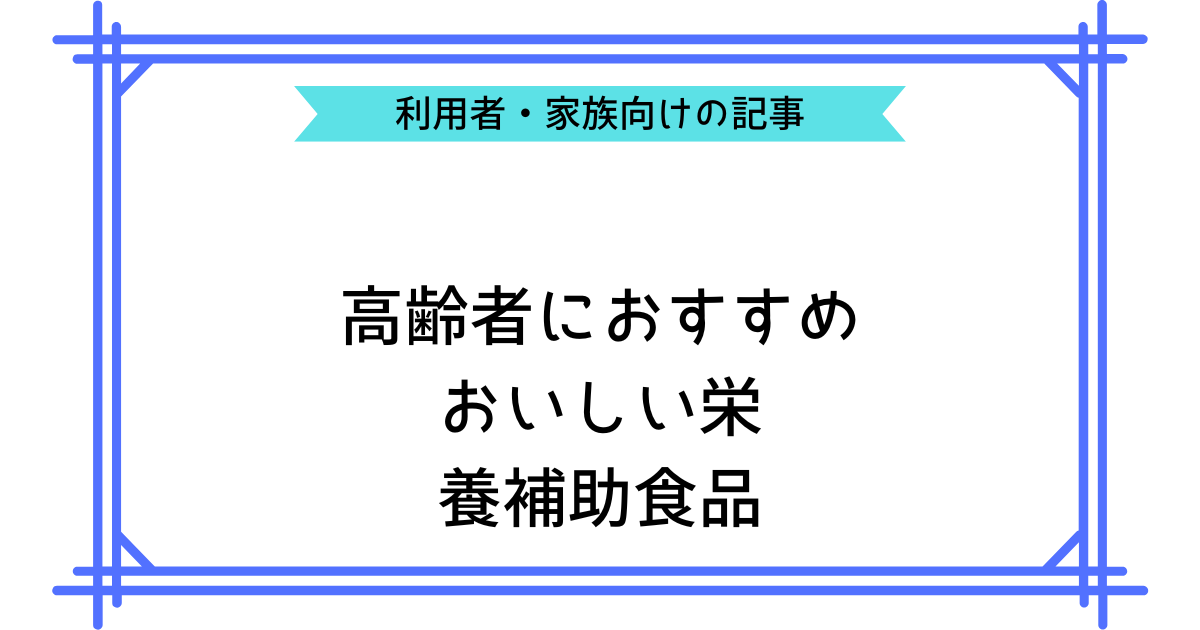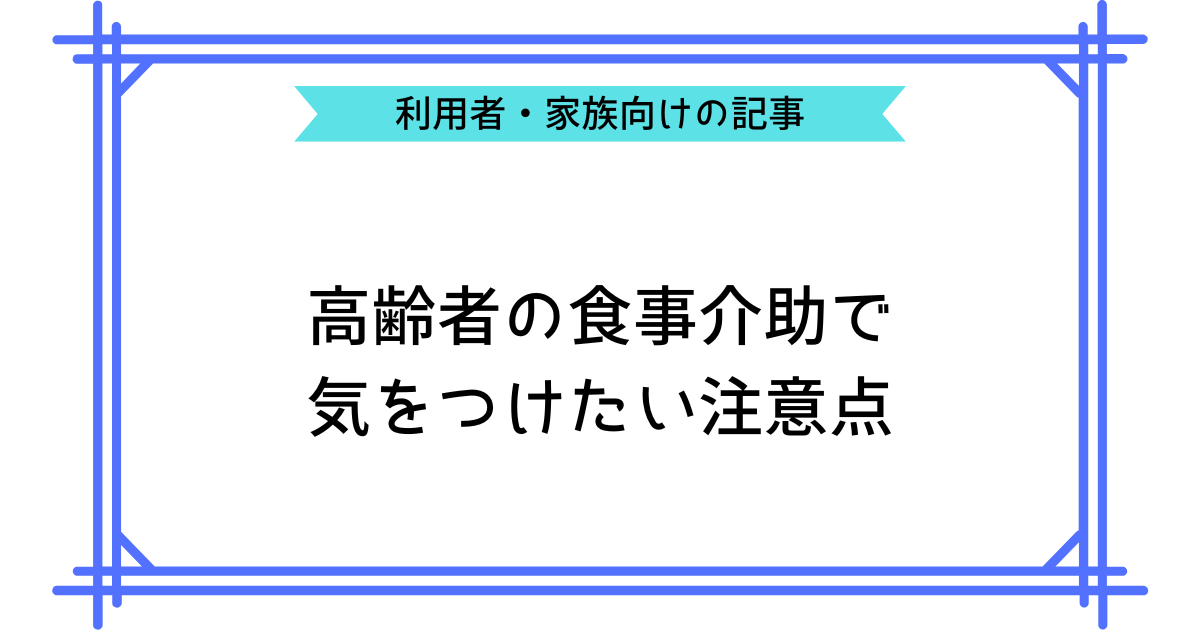区分変更のメリット・デメリットとは?家族が知っておきたいポイントを解説
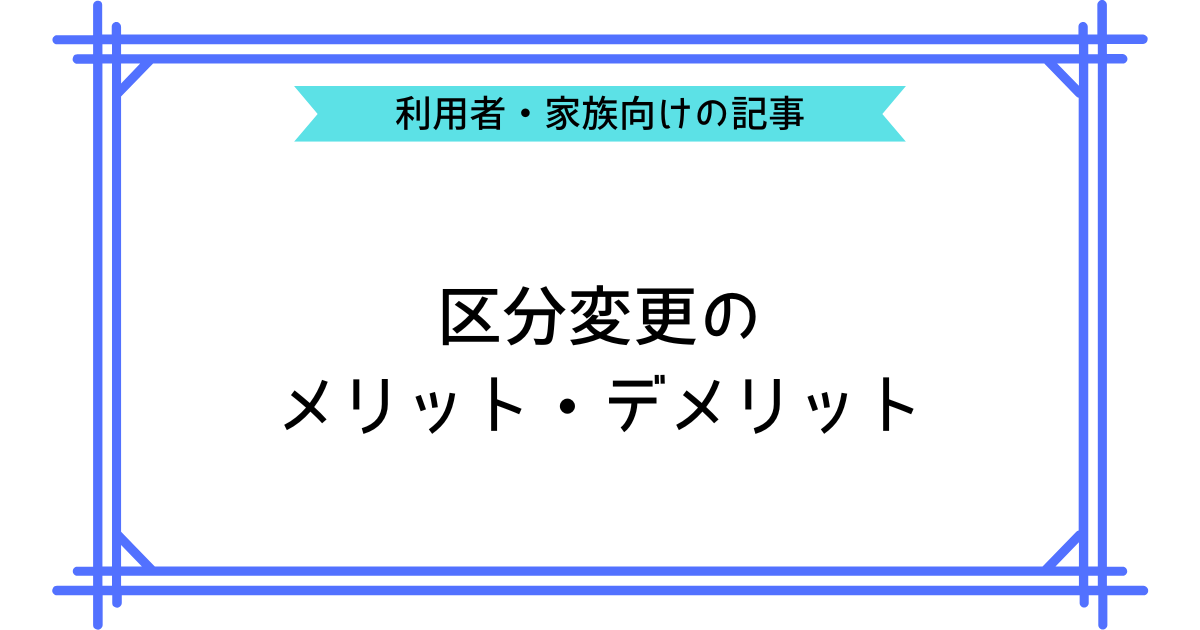
介護保険を利用していると、「区分変更をした方がいいのでは?」と考える場面が出てきます。
区分変更とは、要介護認定の区分(要介護1〜5、要支援1・2)を変更する申請 のことです。
体調の変化や生活状況に応じて申請できますが、メリットだけでなくデメリットもあるため注意が必要です。
この記事では、区分変更の仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説し、ご家族が安心して判断できるようサポートします。
区分変更とは?
区分変更とは、介護保険の認定を受けている方が 心身の状態が変化した場合に、要介護区分の見直しを申請する手続き を指します。
たとえば、要介護2だった方が体調悪化で介護量が増えた場合、「区分変更申請」を行うことで、より重い区分(要介護3など)に認定される可能性があります。
申請は 本人や家族、ケアマネジャーを通じて市区町村の介護保険担当課 に提出します。
区分変更のメリット
1. サービス利用枠が広がる
区分が重くなれば、介護サービスに使える 支給限度額が増える ため、必要なサービスをより多く利用できます。
例:デイサービス回数を増やす、訪問介護時間を延長するなど。
2. 本人の生活に合った支援が受けられる
状態の変化に応じて認定を見直すことで、実際の介護ニーズに合ったサービス を受けられるようになります。
3. 家族の介護負担が軽減
必要なサービスを追加できるため、介護を担う家族の身体的・精神的負担が減る ことにつながります。
4. 医療・介護の連携が強化される
認定区分が重くなることで、訪問看護やリハビリなど専門職の介入 が増え、医療との連携が取りやすくなります。
区分変更のデメリット
1. 認定調査で軽度になる可能性もある
申請したからといって必ずしも重い区分になるわけではありません。逆に 区分が軽く判定されるリスク もあります。
2. サービス内容が変わることがある
区分が変わると、これまで使えていたサービスの利用回数や時間数が調整される場合があります。
3. 手続きや調査の手間がかかる
申請から認定までは1か月程度かかるため、短期的にすぐサービスを増やしたい場合には不便 です。
4. 精神的負担が大きい
調査員の訪問や主治医意見書の準備などで、ご家族にとっても手続きが煩雑に感じられることがあります。
区分変更が必要になるケース
- 最近転倒が増え、介助量が大幅に増えた
- 認知症の進行で見守りが必要になった
- 入院後にADL(日常生活動作)が低下した
- 家族の介護負担が限界に近づいている
こうした場合、早めにケアマネジャーに相談して区分変更を検討 すると安心です。
区分変更の流れ
- 本人・家族またはケアマネを通じて市区町村に申請
- 認定調査員が自宅を訪問し調査
- 主治医が意見書を作成
- 介護認定審査会で判定
- 新しい認定区分が通知
まとめ
区分変更には、サービス枠の拡大や負担軽減といった大きなメリット がある一方で、認定が軽くなる可能性や手続きの煩雑さというデメリット も存在します。
ご家族にとって大切なのは、状態の変化を見逃さず、必要なタイミングでケアマネジャーや主治医に相談すること です。
区分変更を正しく活用することで、本人が安心して在宅生活を続けられ、ご家族の介護負担も軽減できます。