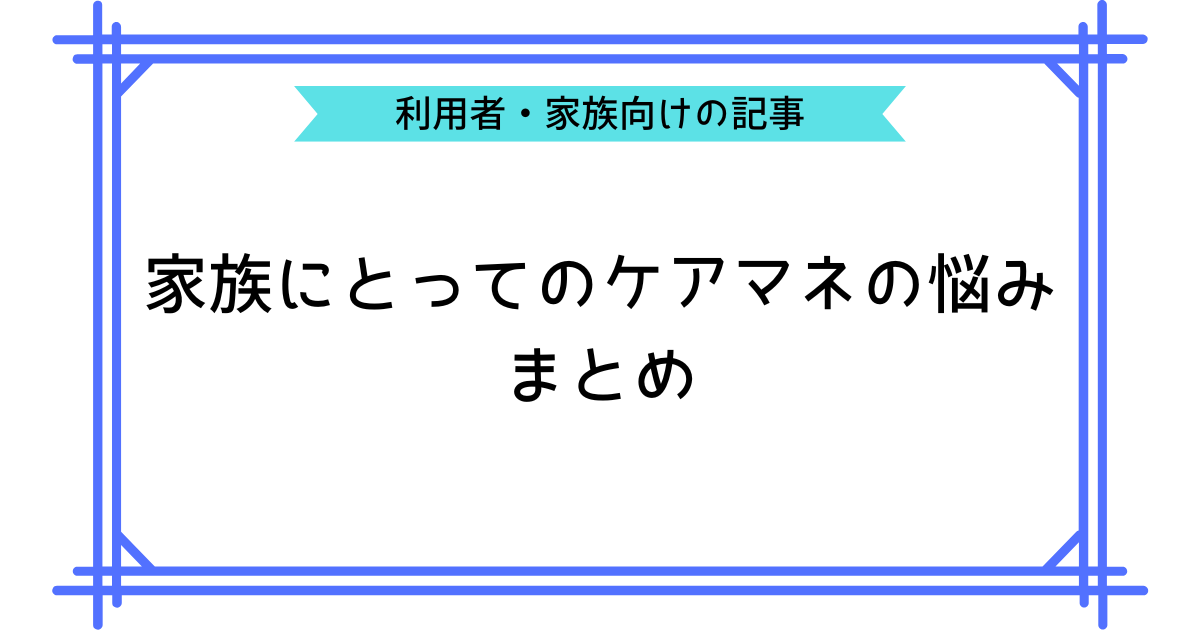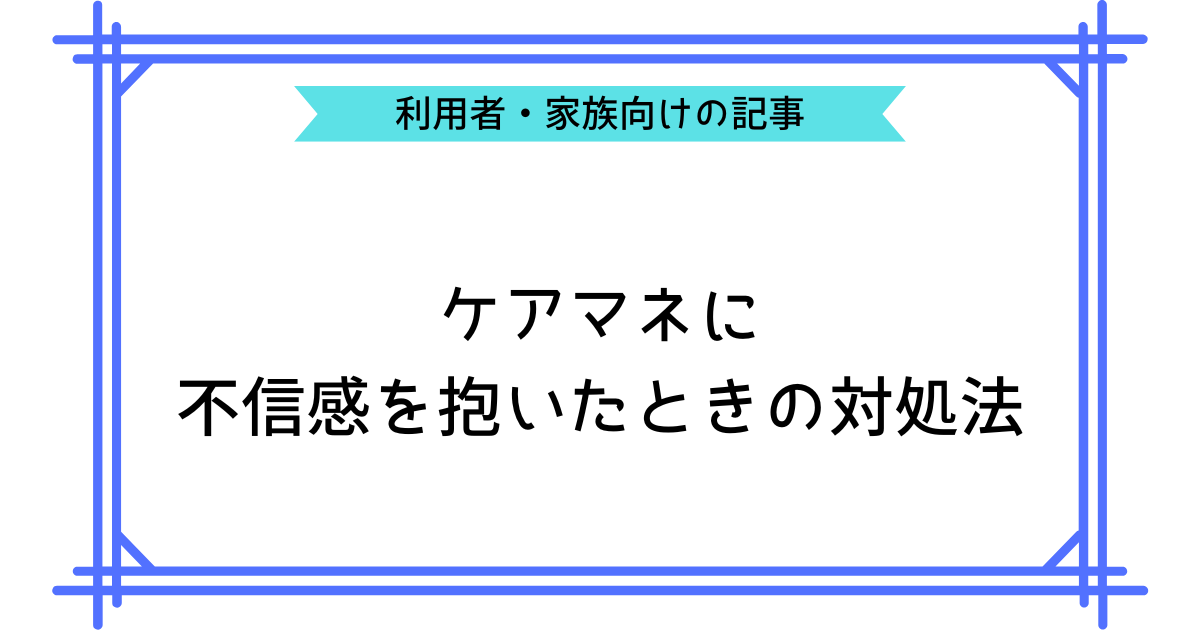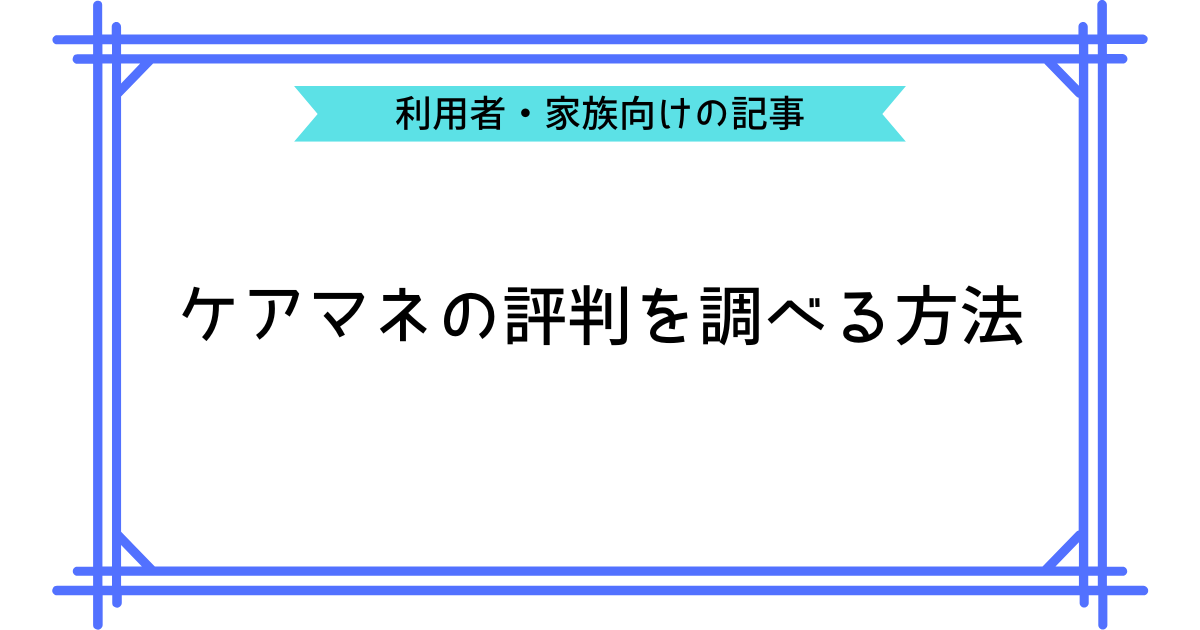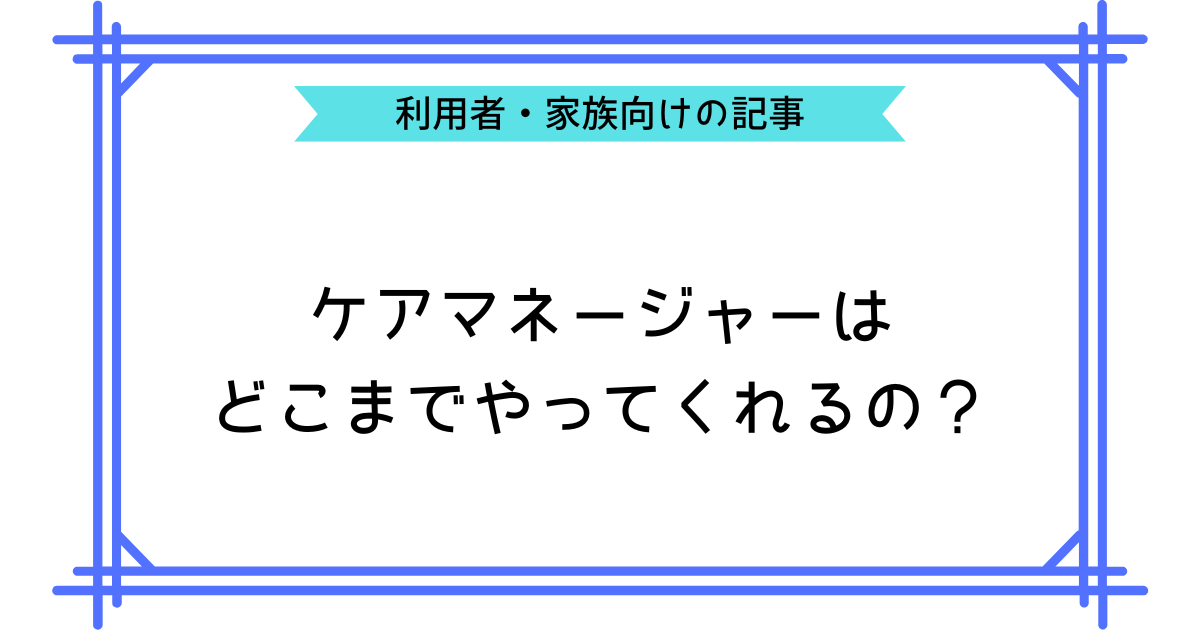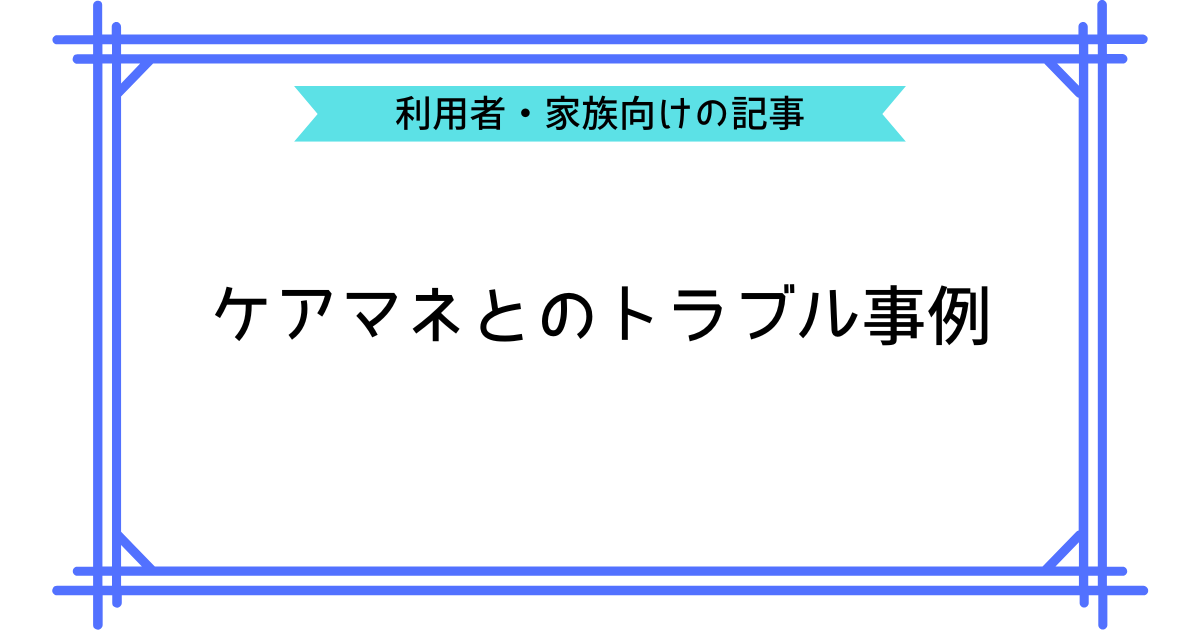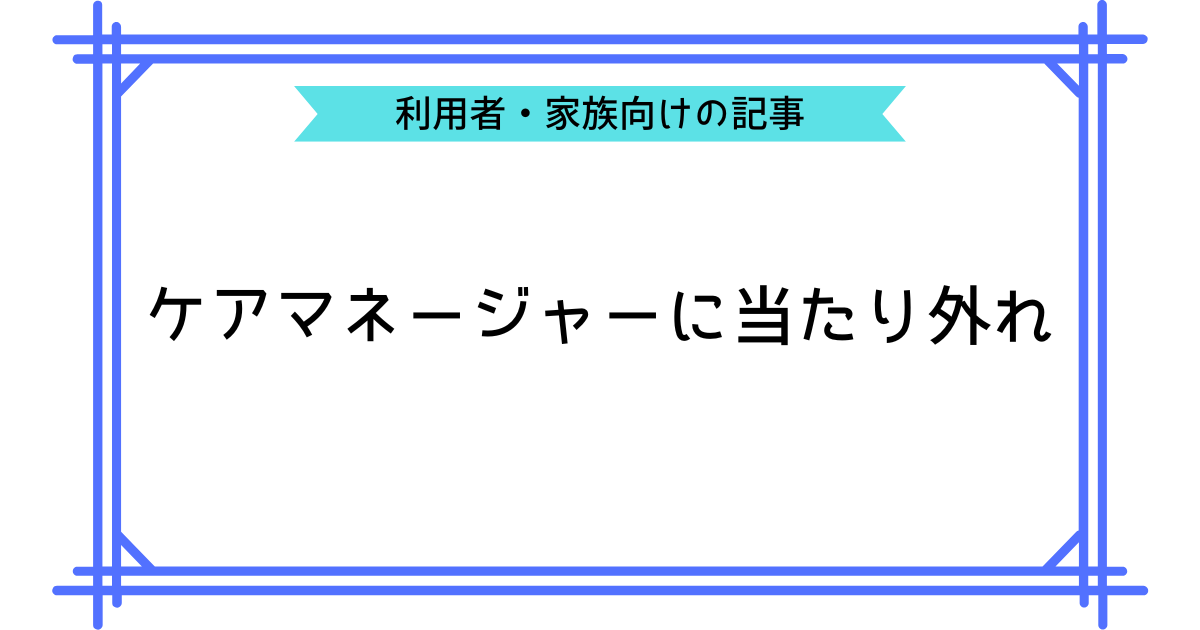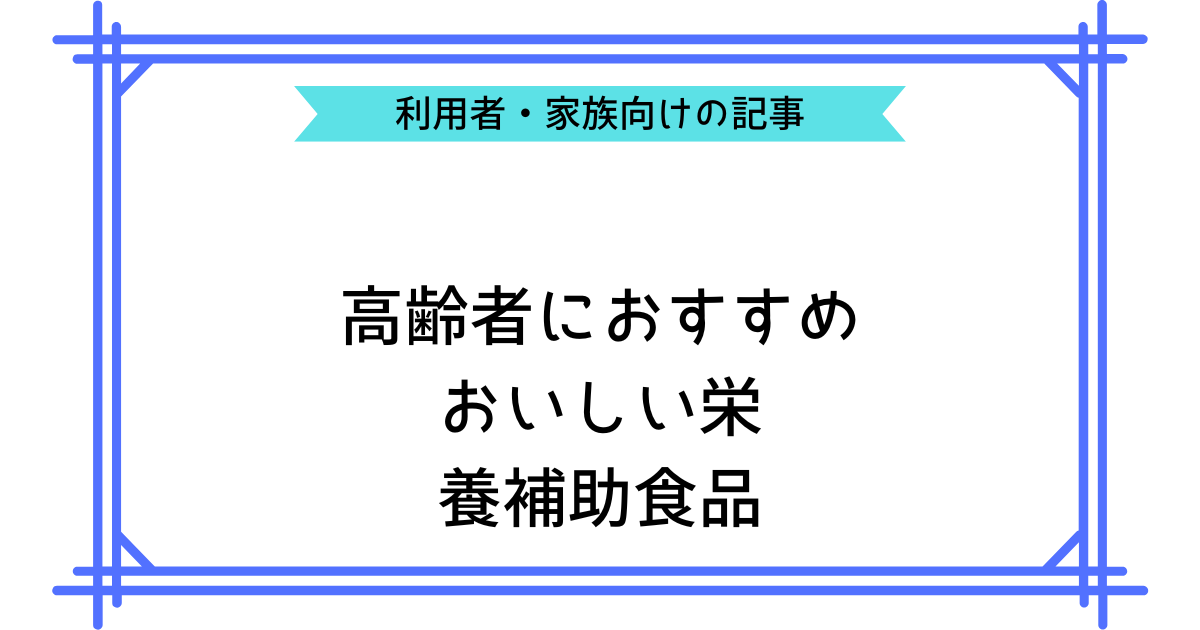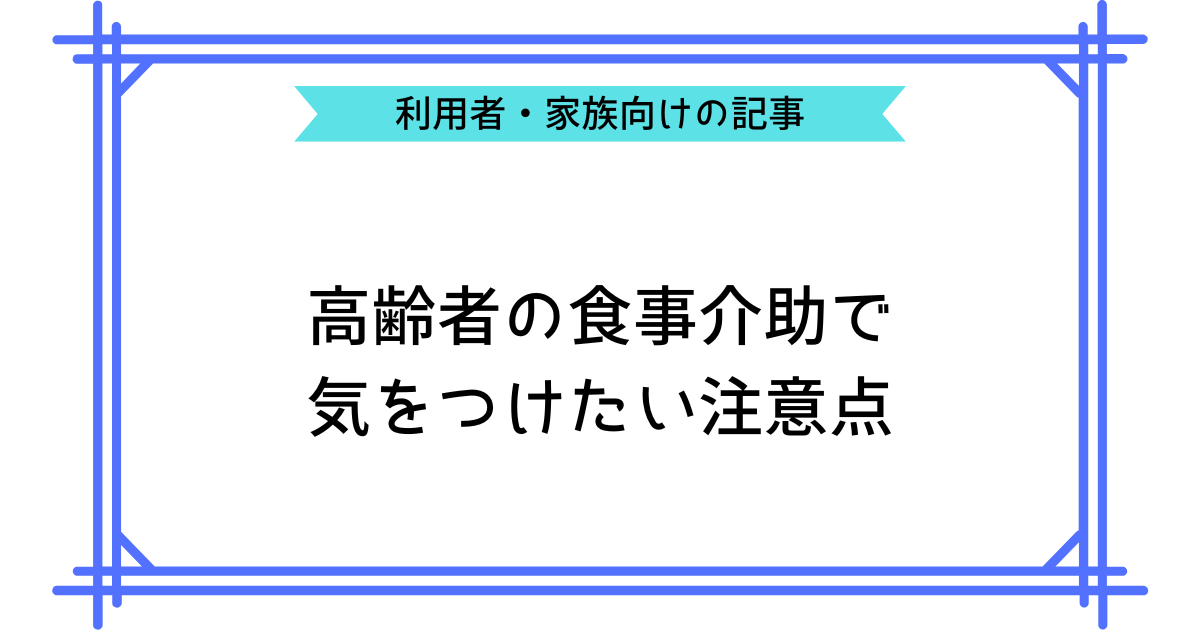ケアプランは誰が作る?ケアマネ以外が作ることも可能なのか?
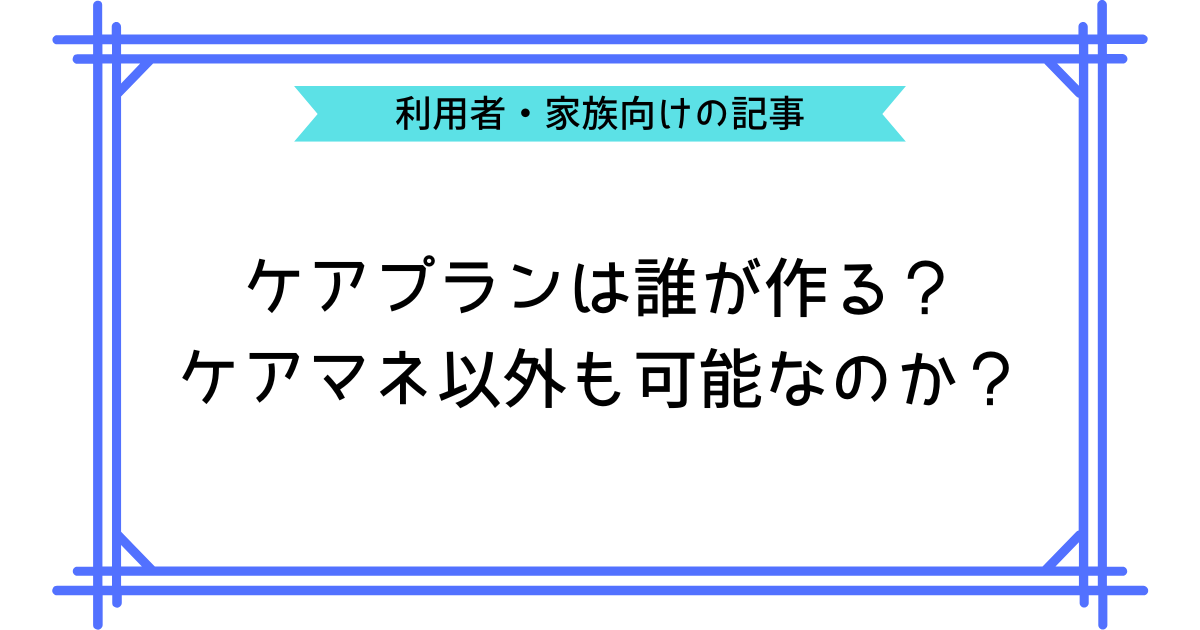
介護保険サービスを利用する際に欠かせないのが「ケアプラン(居宅サービス計画書)」です。
しかし現場では、「ケアプランって誰が作るの?」「ケアマネジャー以外でも作成できるの?」と疑問を持つ方も少なくありません。
利用者や家族の希望を反映させながら、介護サービスを組み合わせていくケアプランは、法律上のルールと実務上の工夫が求められる重要な書類です。
本記事では、ケアプランの作成主体や例外的なケース、注意点についてわかりやすく解説します。
ケアプランは誰が作る?原則はケアマネジャー
ケアプランは、介護保険法に基づき「居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)」が作成するのが原則です。
ケアマネジャーは、要介護認定を受けた利用者の心身状況や生活環境をアセスメントし、本人・家族の希望を踏まえて介護サービスを組み合わせ、目標を設定してケアプランを作成します。
また、サービス担当者会議を通じて多職種と意見交換を行い、ケアプランを最終化する役割も担います。
したがって、ケアプランはケアマネジャーの専門性と調整力を前提として作成されるものといえます。
ケアマネ以外が作るケースはあるのか?
要支援の方は地域包括支援センターが担当
要支援1・2と認定された方の場合、ケアプランは居宅介護支援事業所ではなく、地域包括支援センターの職員(主任ケアマネジャーなど)が作成します。こちらもケアマネ資格を持った職員が対応するケースが多いですが、包括の職員がチームで作成・管理する形となります。
利用者や家族が「自己作成」する場合
法律上は、要介護者本人や家族が自らケアプランを作成する「自己作成」も認められています。ただし実務上は非常にまれであり、専門知識や給付管理の知識が必要なため、多くの場合はケアマネジャーに依頼されます。自己作成した場合でも、サービス提供事業者との調整や保険者への提出といった事務手続きは避けられません。
施設サービス利用時のケアプラン
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設に入所する場合は、施設ケアマネジャーがケアプラン(施設サービス計画)を作成します。利用者や家族の意見を取り入れる点は同じですが、居宅サービスのケアマネジャーではなく、施設側が主体となるのが特徴です。
ケアマネ以外が作成する際の注意点
自己作成プランの難しさ
利用者や家族がケアプランを自己作成する場合、アセスメントやモニタリングといった専門的プロセスを十分に踏めないことが多く、サービスの適切な利用や給付管理が難しくなります。また、介護保険制度上のルールを理解していないと、過剰利用や給付漏れにつながるリスクもあります。
施設サービスとの違い
在宅ケアプランと施設ケアプランは目的や運用が異なります。在宅では「生活を続けるための支援」が中心ですが、施設では「入所生活を円滑に送ること」が重視されます。ケアマネジャー以外が関与する場合でも、利用者の生活全体を見据えた支援が求められます。
法令・自治体ルールを確認すること
ケアプラン作成は介護保険法と厚労省通知に基づいていますが、自治体によって細かい運用が異なることがあります。ケアマネ以外が関与する場合は、必ず保険者(市町村)の確認が必要です。
ケアマネジャーが果たす役割の重要性
ケアマネジャーは、単に書類を作成するのではなく、利用者の生活全体をアセスメントし、多職種連携を調整するコーディネーターの役割を担っています。
もし自己作成を選んだ場合でも、専門職の助言やサポートがないと質の高いケアプランを作るのは困難です。
現場では「ケアマネは必要ない」と考える利用者や家族も一定数いますが、介護サービスを安心して継続するためには、ケアマネジャーの存在が不可欠といえるでしょう。
まとめ
ケアプランは原則としてケアマネジャーが作成しますが、要支援者の場合は地域包括支援センターが担当し、自己作成や施設ケアプランといった例外も存在します。
ただし、自己作成は専門的知識や給付管理の難しさから現実的には少なく、多くの場合ケアマネジャーに依頼することが望ましいです。
ケアマネジャーは利用者や家族の希望を尊重しつつ、専門的な視点で最適なプランを作成・調整する重要な存在です。
したがって、制度を正しく理解したうえで「誰がケアプランを作るのか」を確認し、安心してサービスを利用できる体制を整えていくことが大切です。