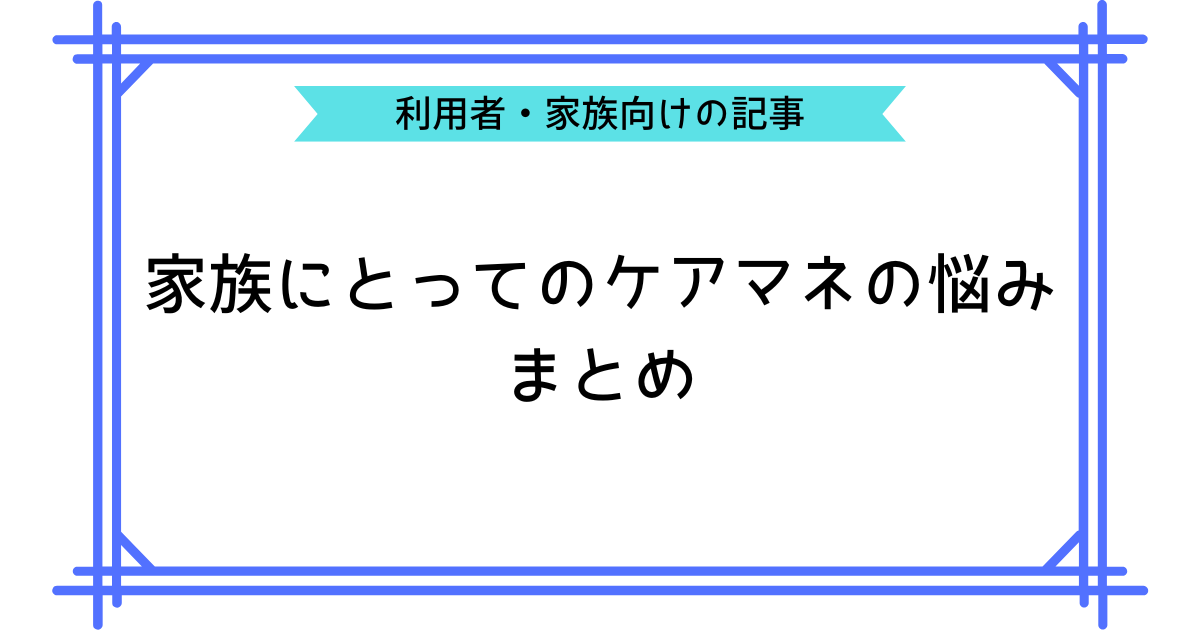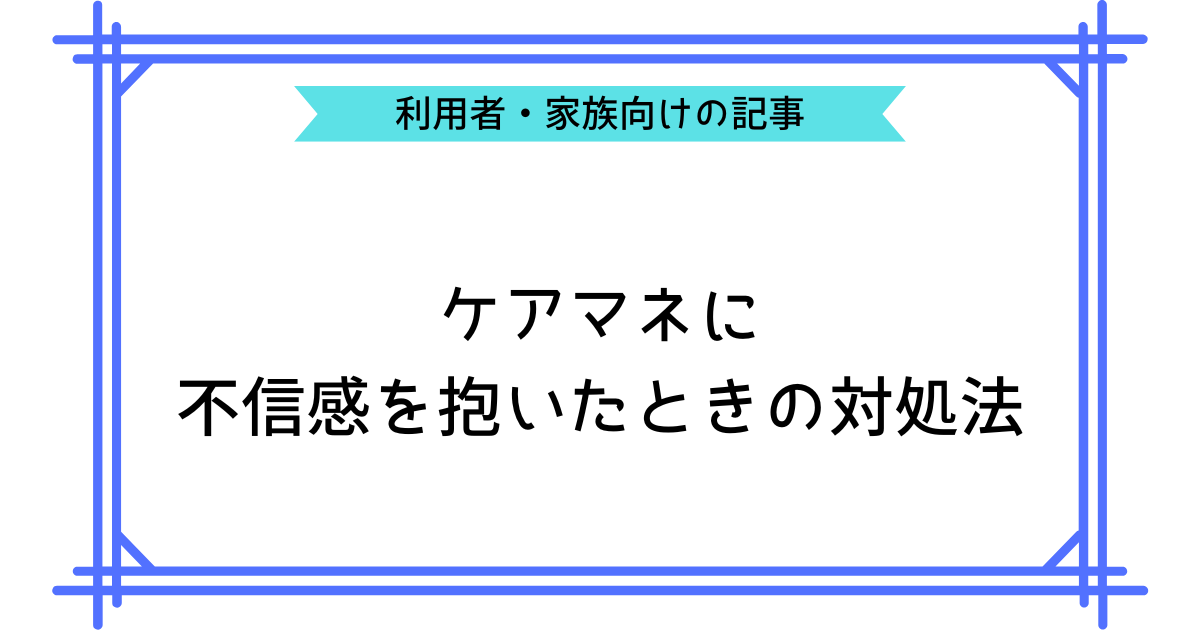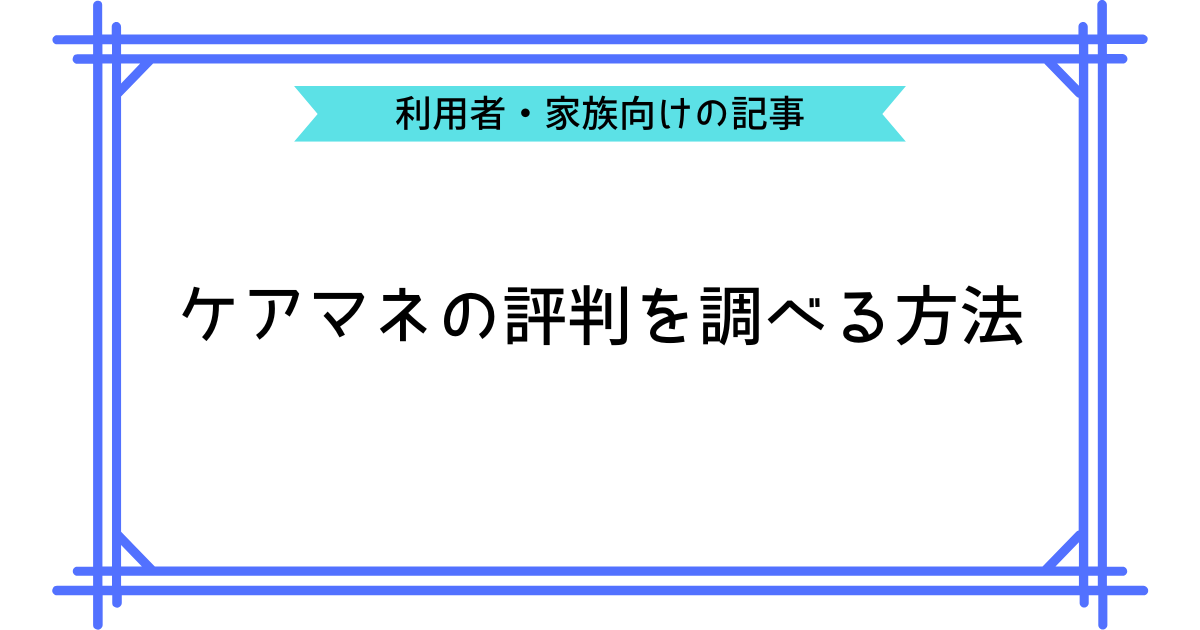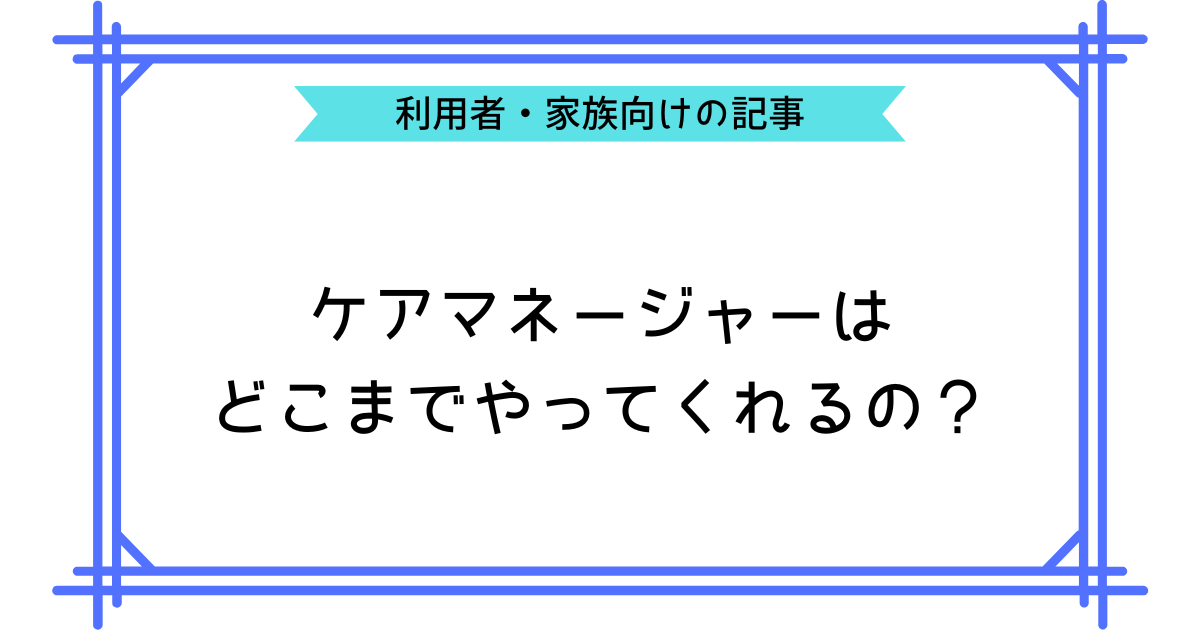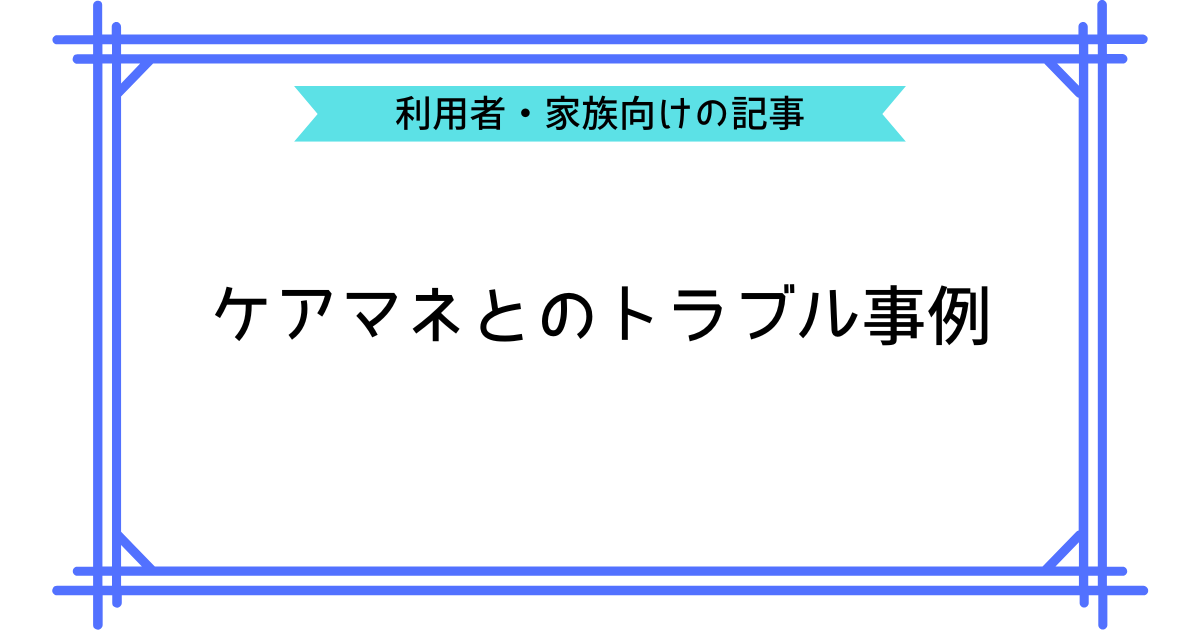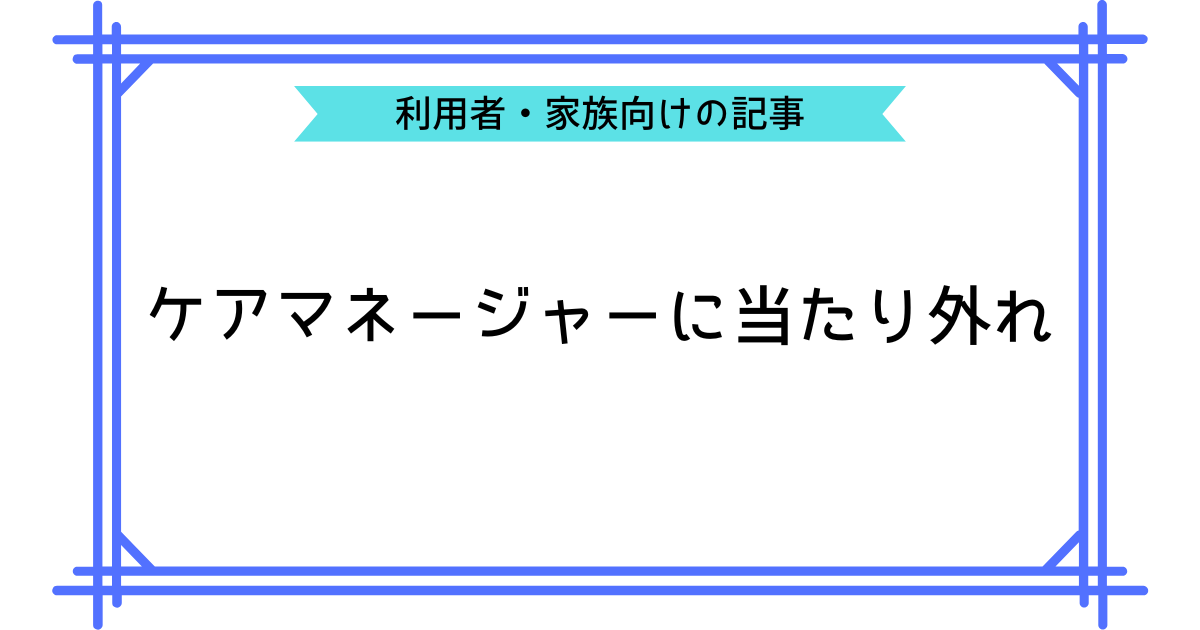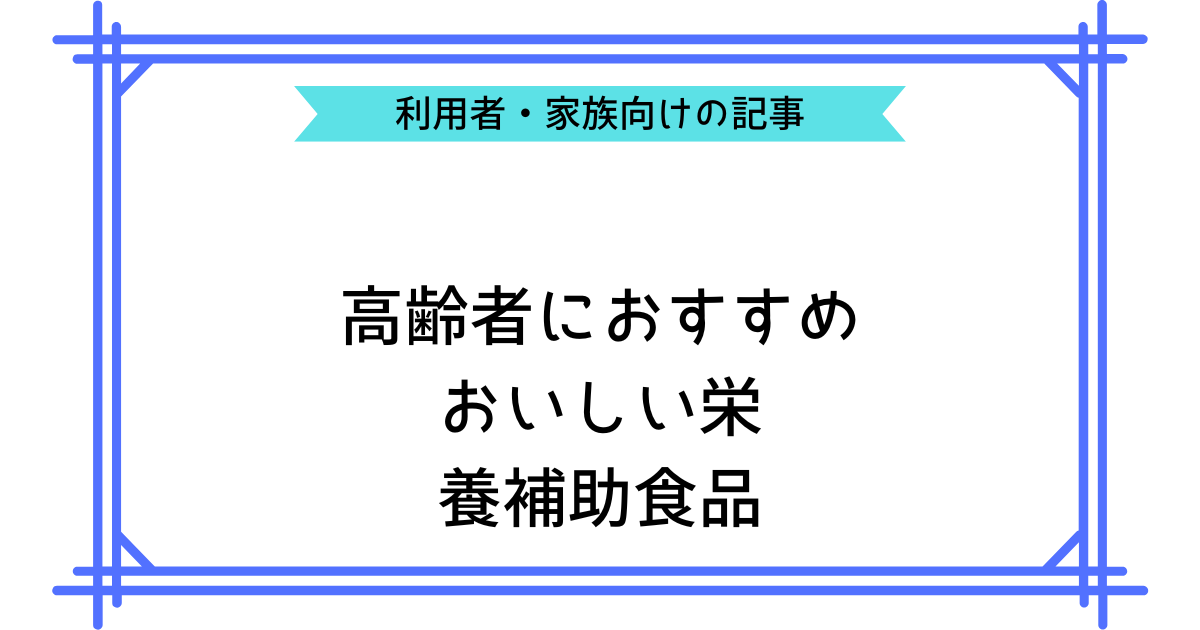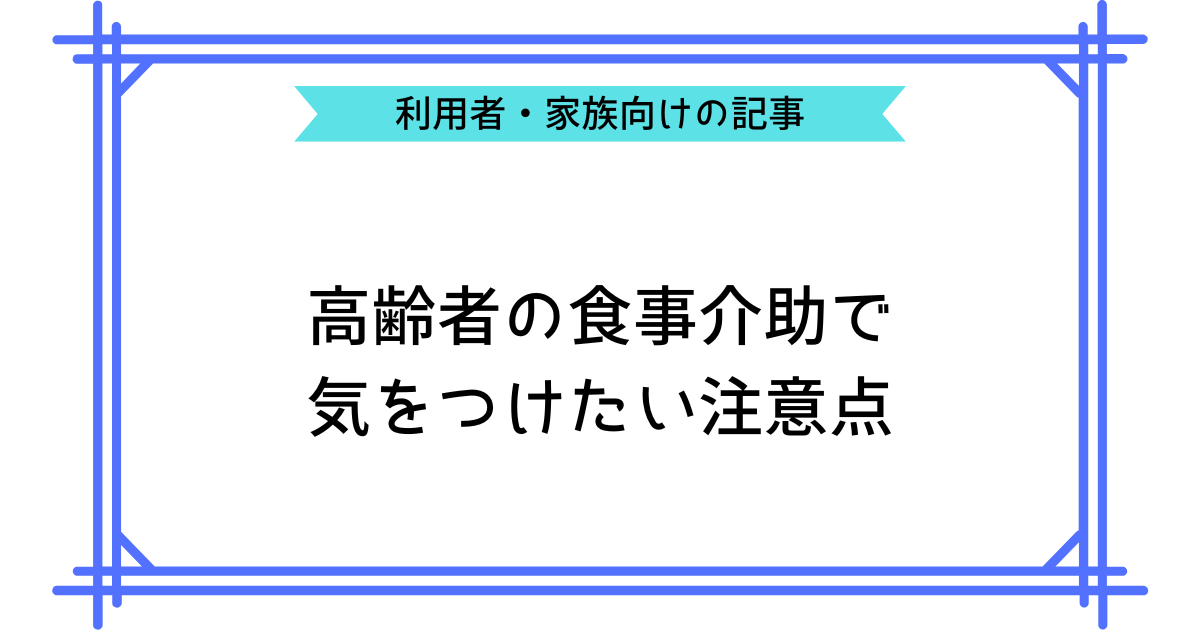ケアマネージャーがしつこい!そんな事例とそんな時の対処法を解説
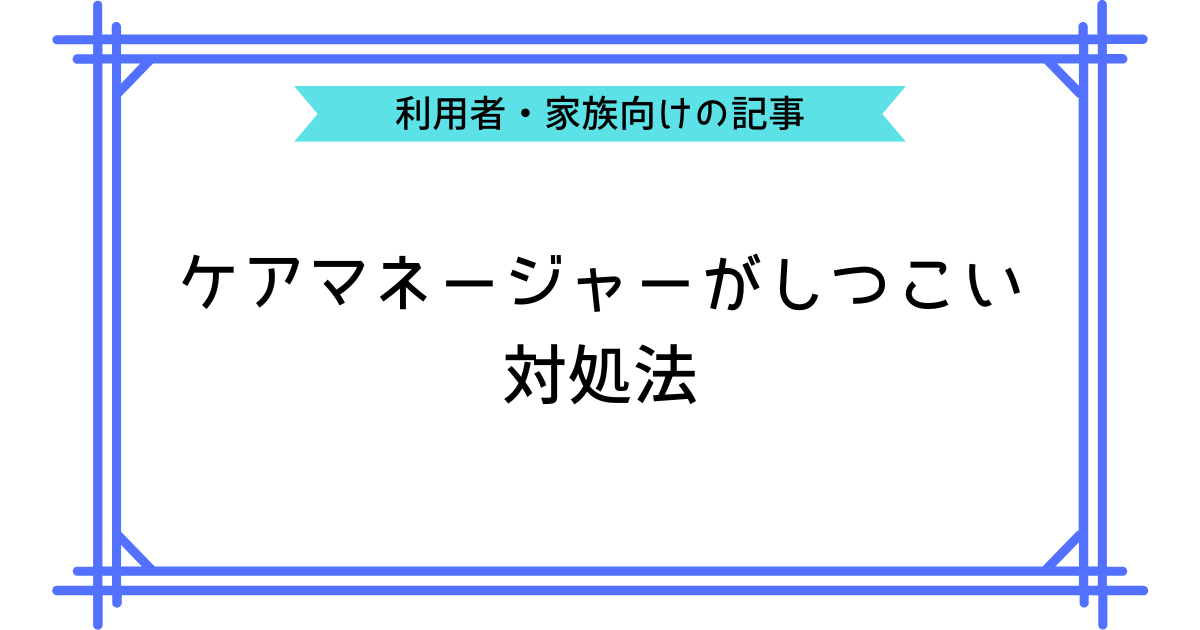
介護サービスを利用していると、ケアマネジャー(介護支援専門員)が定期的に自宅を訪問したり、電話連絡をしてきたりします。
本来は利用者や家族をサポートする立場ですが、中には「ケアマネがしつこい」「何度も連絡してきて疲れる」と感じるケースもあるでしょう。
では、なぜケアマネがしつこいと感じられるのでしょうか?
この記事では、よくある事例や背景、そしてそんな時の適切な対処法について分かりやすく解説します。
ケアマネージャーがしつこいと感じる主な事例
頻繁な電話や連絡が多すぎる
「ちょっとした体調変化でもすぐに電話が来る」「同じ内容を何度も確認してくる」といったケースは、家族にとって負担に感じられます。特に仕事や家事で忙しいときに連絡が重なると「しつこい」と思われがちです。
自宅訪問が多く対応が大変
ケアマネは制度上、月1回以上の訪問が必要ですが、それ以上に頻繁に来る場合もあります。「そのたびに家を片付けなければならない」「時間を拘束される」と感じると、煩わしさにつながります。
サービス利用の提案を繰り返す
「もっとデイサービスを増やしましょう」「福祉用具を使った方がいいです」といった提案が繰り返されると、「営業っぽい」「無理に勧められている」と不信感を持つことがあります。
個人情報や生活状況を根掘り葉掘り聞かれる
生活習慣や家族関係について詳細に質問されると「詮索されている」と感じる方もいます。ケアマネとしては必要なアセスメントでも、家族には「しつこい質問」と受け取られることがあります。
なぜケアマネージャーはしつこいと感じられるのか?
制度上の義務があるから
ケアマネは介護保険制度に基づき、定期的にモニタリングやケアプランの見直しを行わなければなりません。そのため、連絡や訪問の回数がどうしても多くなり、結果として「しつこい」と思われてしまうのです。
利用者の安全確保のため
利用者の体調や生活環境が変化していないか確認することは重要です。放置して状態が悪化すれば大きなリスクにつながるため、ケアマネは慎重に何度も確認する傾向があります。
サービス利用の実績や加算要件が関わることも
ケアマネがサービス利用を勧めるのは、利用者にとって必要と判断したからですが、事業所の加算算定の条件に関係する場合もあります。そのため熱心に提案されると「しつこい」と受け止められることがあります。
ケアマネの性格やスタンス
人によって連絡頻度や接し方に差があります。細かく確認したいタイプのケアマネだと、家族には過干渉のように感じられることもあります。
ケアマネージャーがしつこいと感じた時の対処法
連絡頻度や訪問回数について希望を伝える
「月1回の訪問で十分です」「電話は必要なときだけにしてください」といった要望をはっきり伝えることが大切です。ケアマネも利用者や家族の希望を尊重する義務があります。
連絡手段を工夫する
電話ではなくメールや連絡帳、LINEなどを活用できる場合もあります。「仕事中は電話に出られないのでメールでお願いします」と伝えれば、双方の負担を軽減できます。
必要性を確認する
「なぜその訪問が必要なのか」「どうしてそのサービスを勧めるのか」と理由を確認しましょう。納得できれば「しつこい」ではなく「丁寧な対応」と受け止められることもあります。
合わないと感じたらケアマネ変更を検討する
どうしても相性が合わずストレスを感じる場合は、同じ事業所内で別のケアマネに変更してもらうことも可能です。制度上、利用者が担当ケアマネを変更する権利は認められています。
ケアマネージャーとの関係を良好に保つために
ケアマネは利用者や家族を支える立場であり、本来は心強い存在です。しかしコミュニケーションの頻度やスタイルが合わないと「しつこい」と感じやすくなります。お互いの負担を減らすためには、率直に希望を伝え、調整することが大切です。
また、ケアマネにとっても「しつこい」と思われるのは望むところではありません。利用者・家族が意見を伝えることで、より快適で協力的な関係を築くことができるでしょう。
まとめ
ケアマネージャーが「しつこい」と感じられるのは、
- 電話や訪問が多すぎる
- サービス提案が繰り返される
- 詳しい質問が続く
といった事例が多く、背景には制度上の義務や利用者の安全確保があります。
対処法としては、
- 連絡頻度や訪問回数の希望を伝える
- 連絡手段を工夫する
- 必要性を確認する
- 相性が合わなければ変更を検討する
ことが有効です。
「しつこい」と感じたら我慢せず、率直に要望を伝えることが解決への第一歩です。利用者・家族とケアマネが信頼関係を築ければ、介護サービスはより安心で満足度の高いものになるでしょう。