ケアマネの業務上の制度の悩みまとめ|法的制限・基準・システム活用まで徹底解説
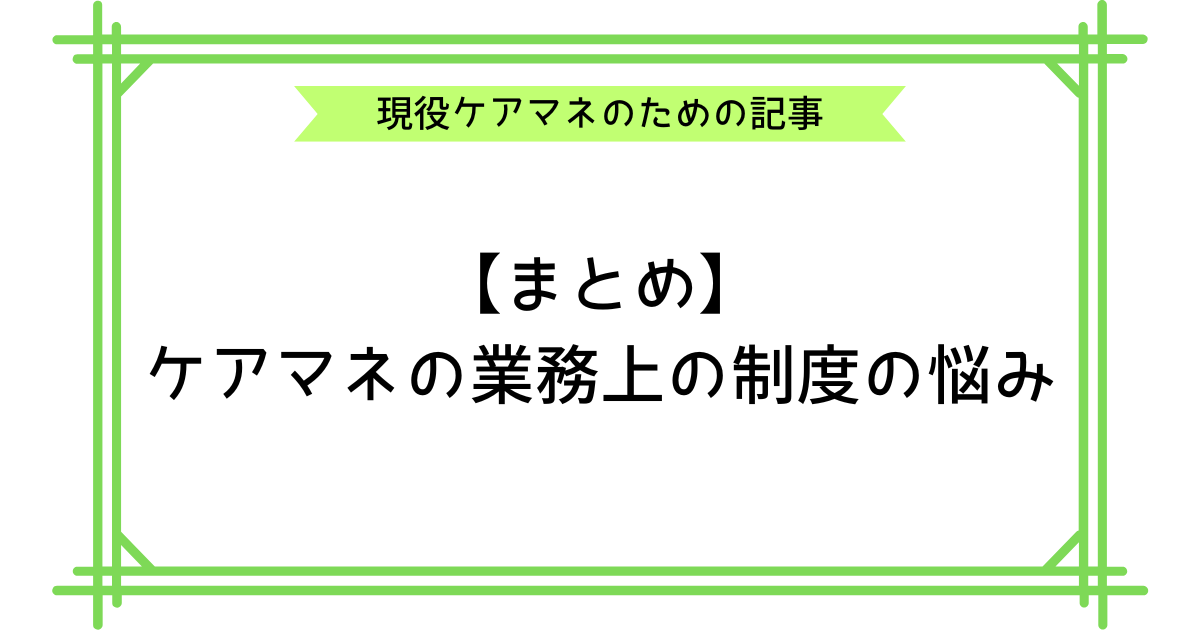
ケアマネジャー(介護支援専門員)の業務は、介護保険制度や関係法令に基づいて細かく制限や基準が定められています。
そのため、「これはやっていいのか?」「制度上はどうなっているのか?」と疑問や悩みを抱く場面が多々あります。
例えば事務員の配置基準、他職種との兼務、退職時の後任確保、通帳管理や服薬管理の可否などは、現場で頻繁に議論されるテーマです。
ここでは、ケアマネが直面しやすい業務上の制度的な悩みを整理し、具体的な記事リンクを紹介します。
居宅介護支援事業所における事務員配置基準
居宅介護支援事業所を運営する上で「事務員は必ず配置しなければならないのか?」という疑問はよくあります。実際には、制度上の配置基準がどうなっているかを確認しておくことが重要です。事務員の有無は業務効率やケアマネの負担にも直結するため、事業所ごとに工夫が求められます。
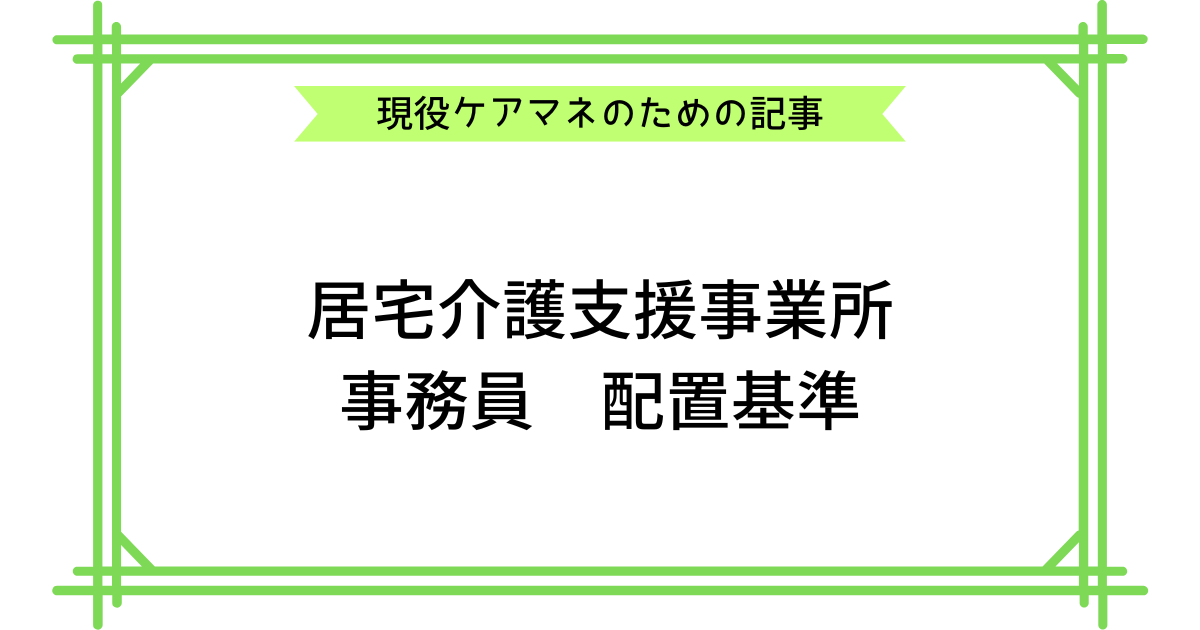
ケアマネと理学療法士・作業療法士の兼務は可能?
人材不足が深刻化するなかで「ケアマネとPT・OTを兼務できるのか」という問題が浮上します。介護支援専門員とリハ職の両方を資格取得している人もいますが、制度的に認められる範囲や注意点を理解しておく必要があります。現場のニーズに応えながらも法的リスクを避けるために、正しい情報を把握することが大切です。
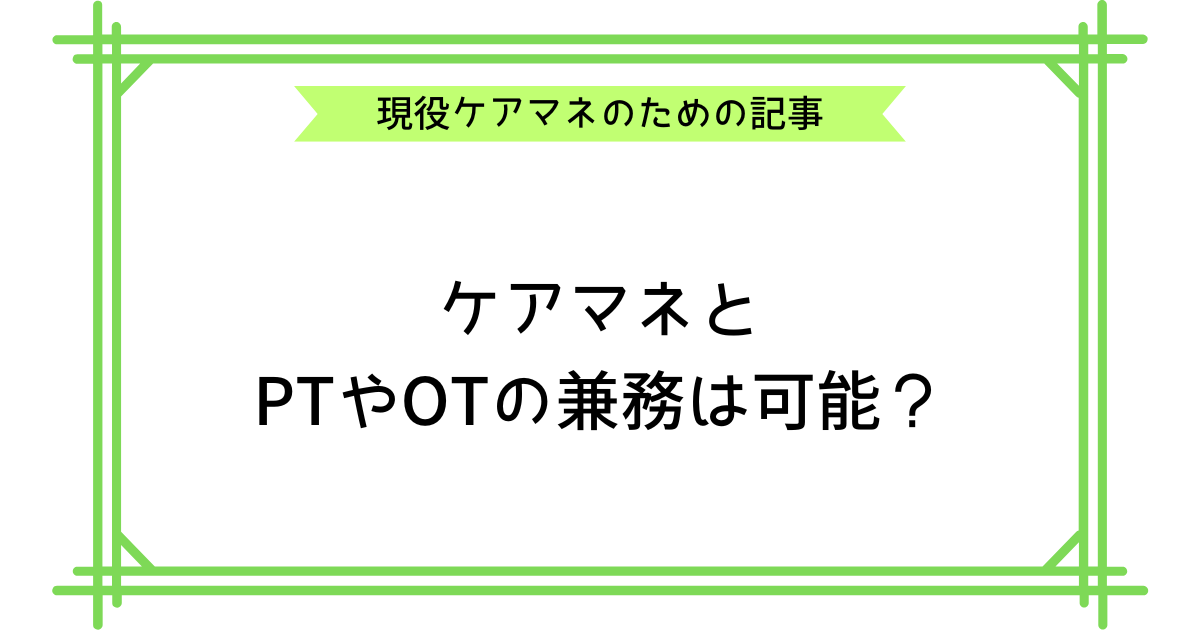
ケアマネ退職時に後任がいない場合の対応
ケアマネが突然退職した際、利用者のケアプラン継続に大きな支障が生じることがあります。後任がいないときは「地域包括支援センターへの一時的な依頼」「他事業所との連携」など、制度上の対応が必要です。事業所としては、急な離職リスクを見据えた人員体制や引き継ぎの仕組みづくりが欠かせません。
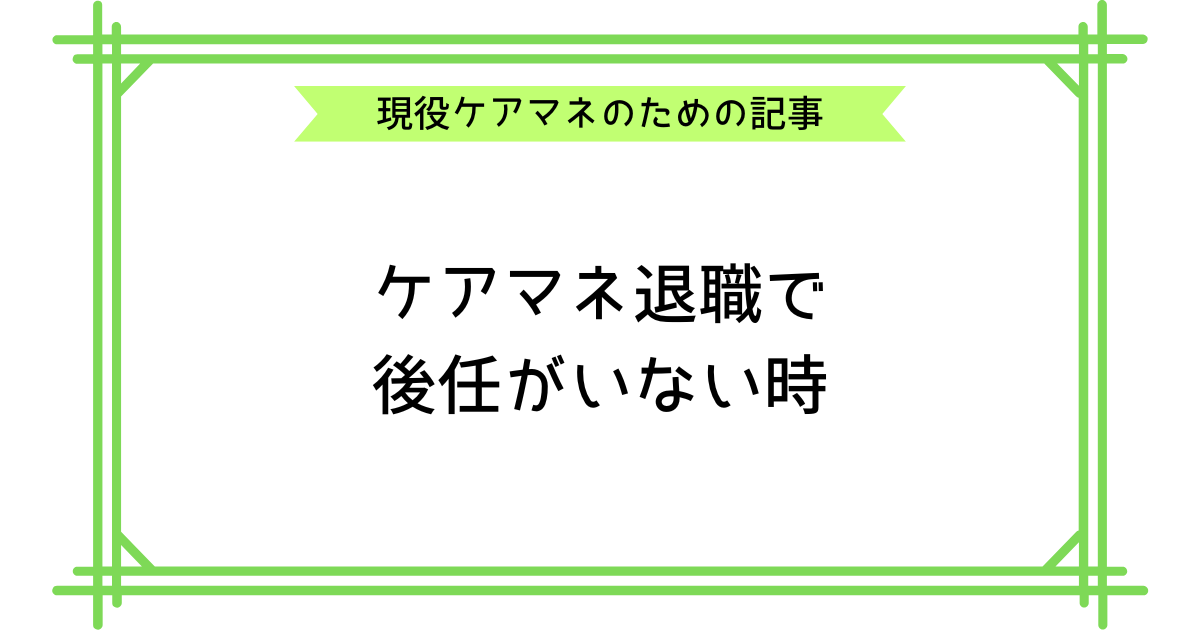
ケアマネは服薬管理をしてはいけない?
「服薬管理を手伝ってほしい」と利用者や家族から求められることはありますが、ケアマネは医療行為にあたる服薬管理を直接行うことはできません。法的に禁止されている背景を理解するとともに、訪問看護師や薬剤師といった他職種と連携することが現実的な解決策となります。
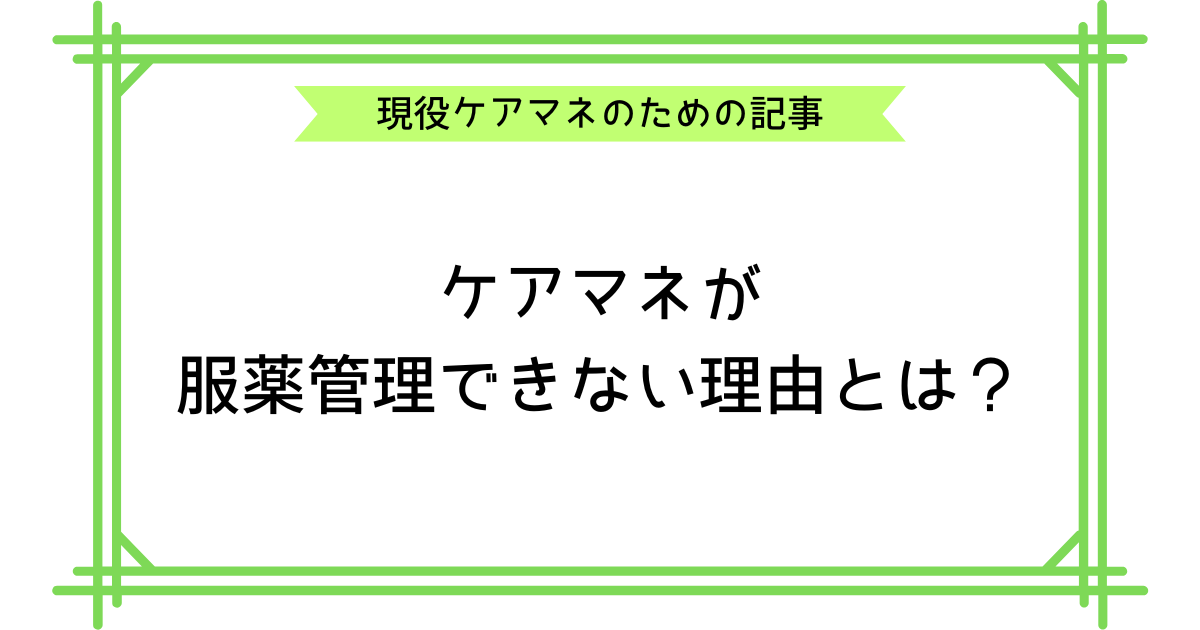
ケアマネと利用者のお金の関わり方
介護現場では「通帳を預かってほしい」「預金を引き出してきてほしい」と依頼されることがあります。しかしケアマネが直接お金を扱うことは、法的にも倫理的にも大きなリスクを伴います。正しい対応方法を知らないとトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
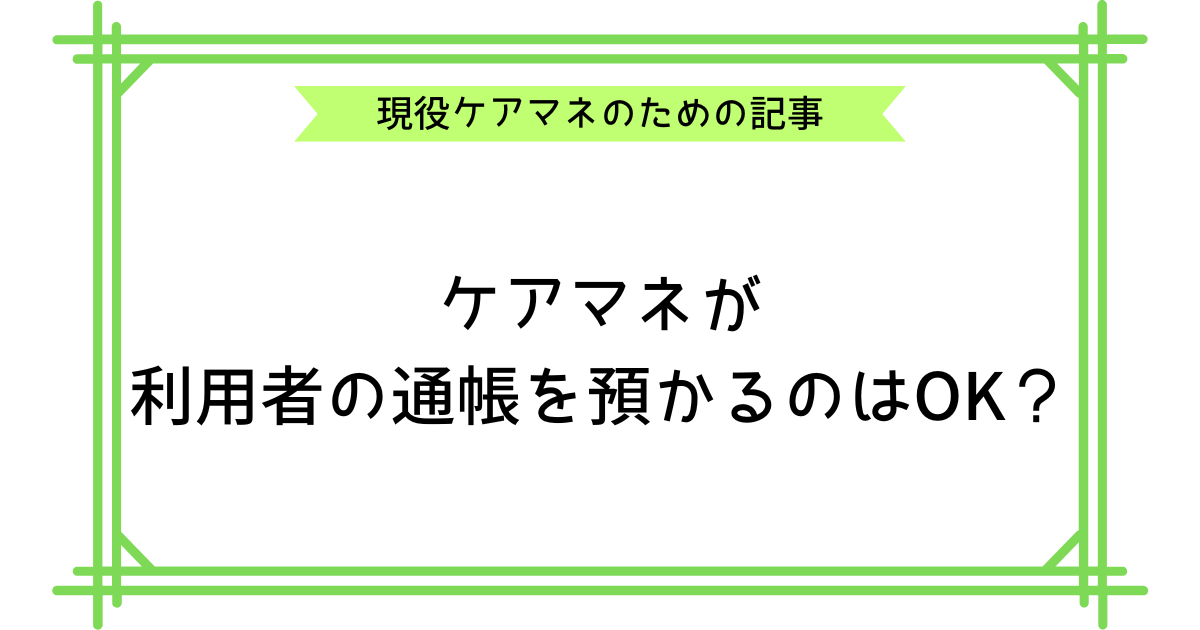
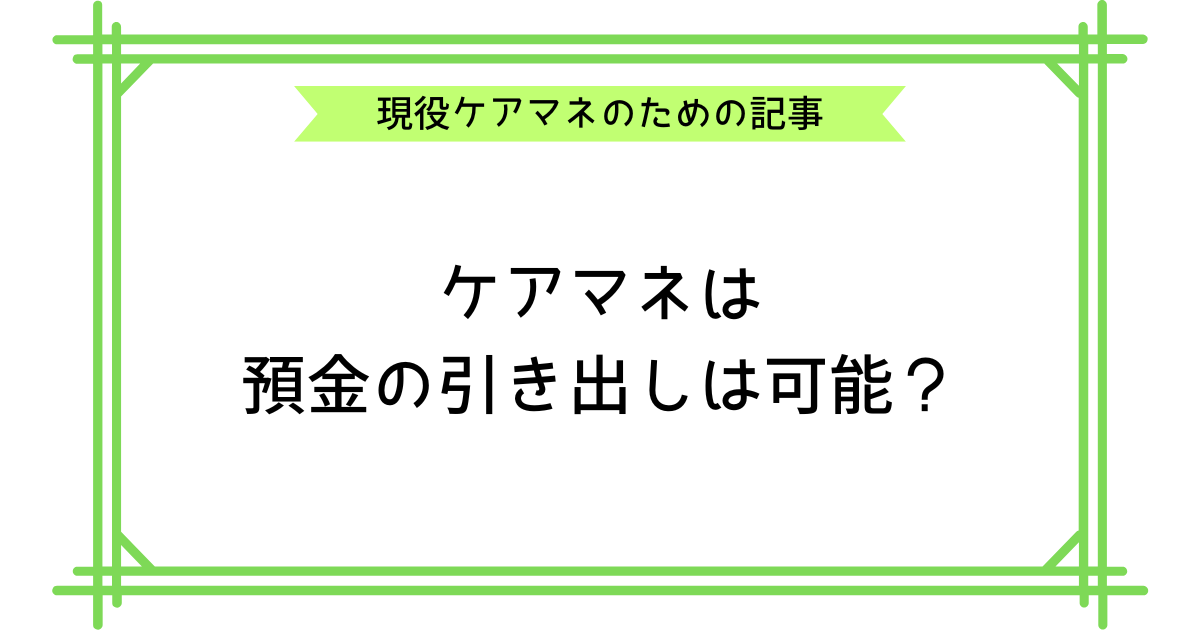
ケアプランデータ連携システムの活用
近年、ICT化が進む中で「ケアプランデータ連携システム」が注目されています。これを導入すると、事業所間での情報共有や書類作成の効率化が進む一方、操作や導入コストに課題を感じる声もあります。メリットとデメリットを正しく把握し、現場で活用できるかどうか判断することが重要です。
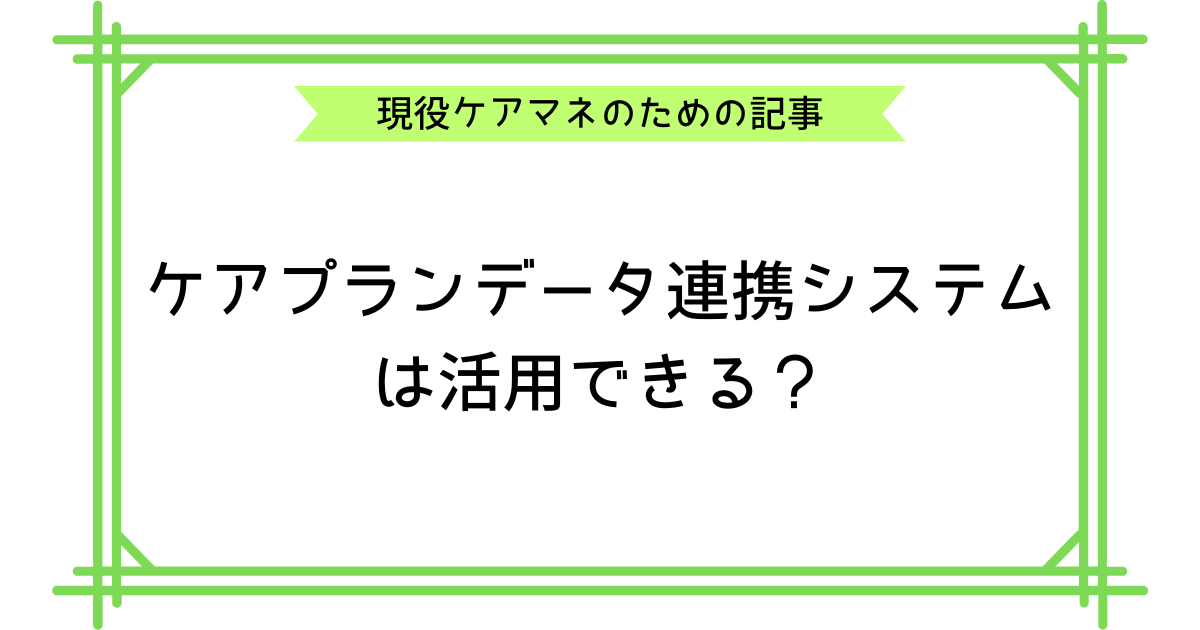
まとめ
ケアマネの業務は「できること」と「できないこと」が法令や制度で明確に区分されています。
事務員の配置基準、PT・OTとの兼務、退職時の後任確保、服薬管理や金銭管理の制限、そしてICT活用など、現場が直面する悩みは多岐にわたります。
本記事を通して、制度に基づく正しい知識を得ると同時に、リンク先の記事からさらに詳細な情報を確認してください。
制度を理解することで、ケアマネ自身も安心して業務に向き合うことができるでしょう。















