第1号被保険者と第2号被保険者の違いとは?わかりやすく解説
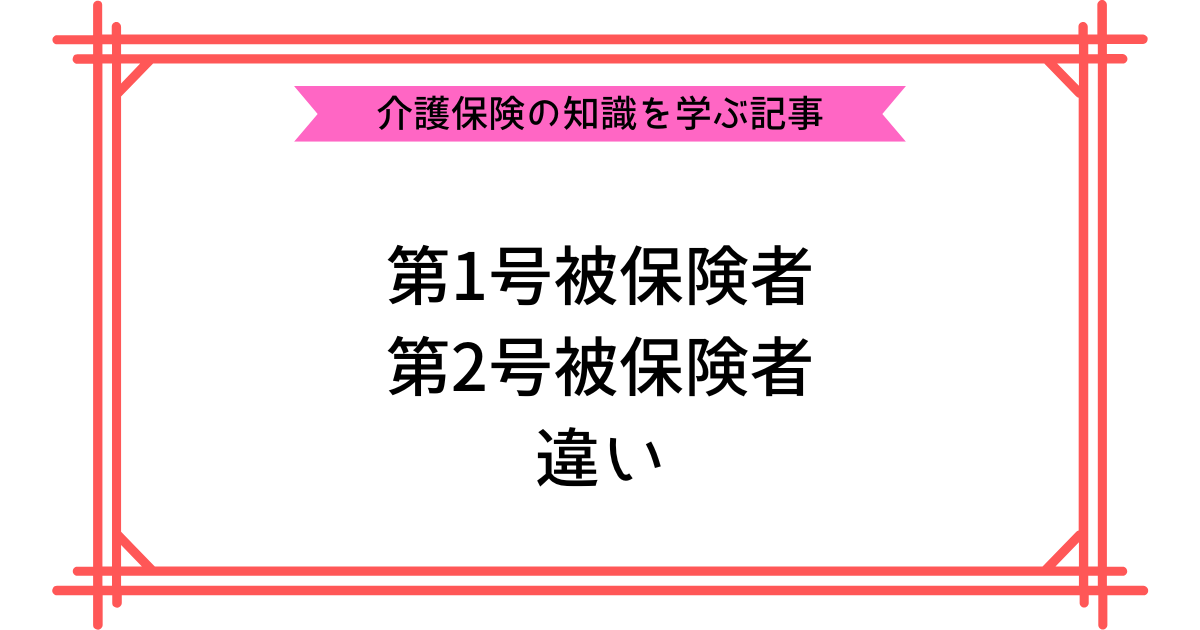
介護保険制度には「第1号被保険者」と「第2号被保険者」という区分があります。
しかし「名前は聞いたことがあるけれど、何が違うの?」「自分はどちらに当てはまるのか分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
実はこの違いを理解しておくことはとても重要です。なぜなら、保険料を支払う仕組みや介護サービスを利用できる条件が、この区分によって大きく異なるからです。
本記事では、第1号被保険者と第2号被保険者の違いについて、介護保険制度の仕組みや特徴を交えながら、わかりやすく解説します。
介護保険制度における被保険者とは?
介護保険制度は、加齢や病気などで介護が必要になったときに、介護サービスを利用できるように国民全員が支え合う仕組みです。
介護サービスを利用するためには、まず「介護保険の被保険者」となることが前提です。
被保険者は年齢によって 「第1号被保険者」 と 「第2号被保険者」 に区分されます。
第1号被保険者とは?
年齢区分
第1号被保険者は、65歳以上のすべての人です。国籍や職業に関わらず、日本国内に住んでいれば原則として対象になります。
保険料の支払い方法
- 原則として 年金から天引き(特別徴収)
- 一定条件下では 口座振替や納付書で支払う普通徴収 も可能
サービス利用の条件
- 要介護認定または要支援認定 を受ければ、原因を問わず介護サービスを利用可能
- 例えば、認知症、脳梗塞後遺症、骨折による寝たきりなど、加齢に伴う心身の状態変化が対象となります
特徴
第1号被保険者は、年齢だけでサービス利用が可能となるため、最も利用者数が多い層です。
第2号被保険者とは?
年齢区分
第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。つまり、会社員や自営業者、扶養家族などが含まれます。
保険料の支払い方法
- 医療保険の保険料に上乗せして徴収される仕組み
- 会社員であれば給与から天引き、自営業者は国民健康保険料と一緒に納付
サービス利用の条件
第2号被保険者が介護サービスを利用できるのは、加齢に伴う特定疾病が原因で要介護状態になった場合のみです。
特定疾病は16種類に限定されています。代表的なものは以下の通りです。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
- パーキンソン病
- 骨折を伴う骨粗鬆症
特徴
65歳未満でも、これらの特定疾病が原因で要介護状態となった場合に限り、介護保険サービスを利用できます。
第1号被保険者と第2号被保険者の違いまとめ
| 区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
| 保険料の徴収方法 | 年金から天引きが中心 | 医療保険料に上乗せ |
| サービス利用条件 | 原因を問わず、要介護・要支援認定で利用可能 | 特定疾病が原因の場合のみ利用可能 |
| 主な対象 | 高齢者 | 働き盛りの世代 |
なぜこの区分が必要なのか?
高齢化社会が進む日本では、介護サービスの需要が急速に高まっています。
65歳以上を一律にサービス対象とすると財政負担が増えるため、40〜64歳については「加齢が関与する特定疾病」に限定することで、制度の持続可能性を確保しています。
ケアマネジャーや家族が押さえておきたいポイント
- 申請条件の違いを理解する
65歳以上は原因を問わないが、40〜64歳は特定疾病が条件になる。 - 医師の診断が必要
第2号被保険者がサービスを利用する場合、特定疾病であることを医師が証明する必要があります。 - 保険料の負担方法が違う
本人や家族が混乱しないように、どのように徴収されているのかを確認しておきましょう。 - 制度の見直しが行われる可能性
高齢化が進む中で、将来的に対象年齢や条件が変更される可能性もあるため、最新情報に注意が必要です。
まとめ
第1号被保険者と第2号被保険者の違いを整理すると、
- 第1号被保険者:65歳以上。原因を問わず要介護認定を受ければ介護サービスを利用できる。
- 第2号被保険者:40歳〜64歳。介護サービスを利用できるのは特定疾病が原因の場合に限られる。
- 保険料の徴収方法も、年金天引きと医療保険料上乗せで異なる。
この違いを理解しておくことで、介護保険の仕組みを正しく活用でき、スムーズにサービスを利用できます。ケアマネジャーや家族も、利用者の年齢区分に応じた説明を行うことが大切です。















