ノーマライゼーションとは?わかりやすく解説|介護・福祉の基本理念
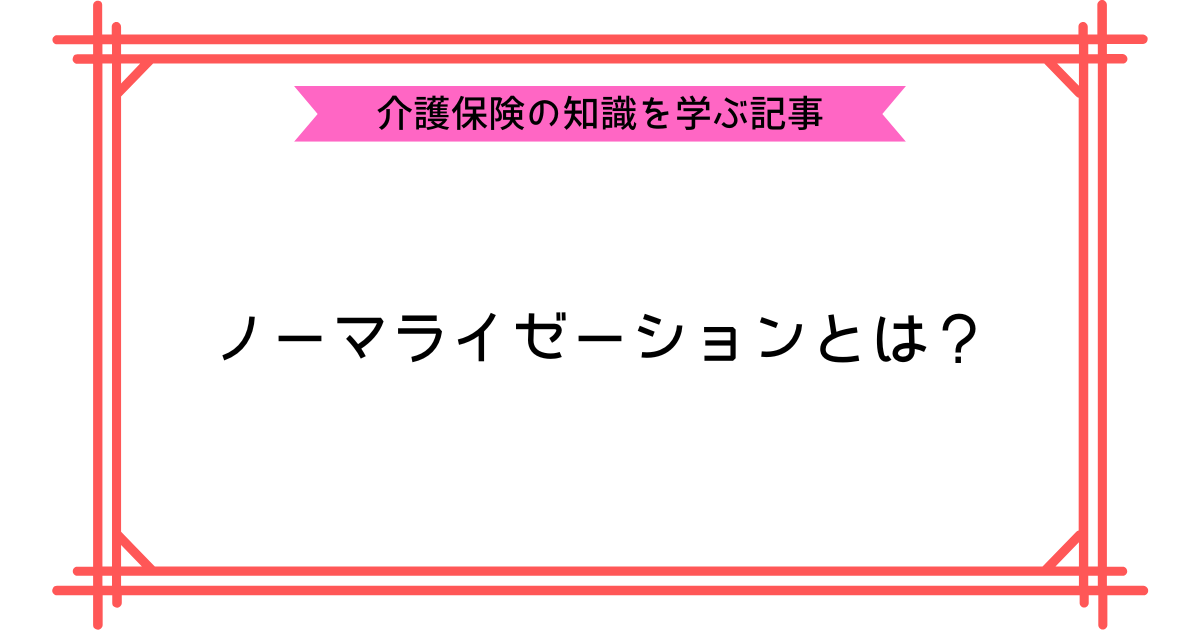
「ノーマライゼーション」という言葉を聞いたことはありますか?
介護や福祉の分野でよく使われる専門用語の一つですが、「意味がよくわからない」「バリアフリーと何が違うの?」と疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、ノーマライゼーションの意味・歴史・日本での展開・具体的な実践例 を、専門知識がない方にもわかりやすく解説します。
ノーマライゼーションとは?わかりやすく解説
ノーマライゼーションとは、障害の有無や年齢に関わらず、すべての人が「普通(ノーマル)」の生活を送れる社会を目指す理念 のことです。
言い換えると、「障害があるから特別な施設で暮らす」のではなく、「地域の中で他の人と同じように暮らせる」ことを大切にする考え方です。
単なる福祉サービスの提供にとどまらず、「社会の側が環境を整えることで、誰もが自分らしく生きられる社会を実現する」という理念として広く使われています。
ノーマライゼーションの歴史
ノーマライゼーションの考え方は、1950年代にデンマークで生まれました。当時、障害のある人は大規模な施設で隔離されることが一般的でした。
しかし、デンマークのバンク=ミケルセン氏らが「障害者も地域で普通の暮らしをする権利がある」と提唱し、地域社会で共に生きる仕組みづくりが始まりました。
その後、この理念はヨーロッパから世界に広まり、日本でも1980年代以降、介護や障害者福祉の基本理念として定着していきました。
バリアフリーやインクルーシブとの違い
ノーマライゼーションは似た言葉と混同されることがあります。
- バリアフリー:段差解消や手すり設置など、物理的・制度的な障壁をなくす取り組み
- インクルーシブ:障害の有無にかかわらず、同じ場で共に学び・働き・生活すること
これに対してノーマライゼーションは、「社会全体がすべての人にとって普通の生活を保障する」という理念であり、バリアフリーやインクルーシブ教育もその一部に含まれる大きな概念といえます。
日本におけるノーマライゼーションの展開
日本でも1981年の「国際障害者年」を契機に、ノーマライゼーションの理念が広まりました。その後、
- 障害者自立支援法(2006年)
- 障害者総合支援法(2013年)
- 共生社会づくりを推進する施策
などに反映され、「地域で暮らす権利」を重視する方向に進んでいます。
現在では高齢者介護の分野でも「地域包括ケアシステム」の理念の一部として取り入れられています。
現場でのノーマライゼーションの実践例
ノーマライゼーションは抽象的な理念ですが、日常の中で具体的に形にされています。
- 障害のある方が地域の一般住宅で生活し、必要な介護・看護サービスを受ける
- 高齢者が施設ではなく、自宅や地域で生活を続けられるように在宅介護を整備する
- 学校で特別支援学級と通常学級が交流・共同学習を行う
- 公共交通機関のバリアフリー化、ユニバーサルデザインの導入
これらはすべて「誰もが普通に暮らせる社会」を目指すノーマライゼーションの実践です。
まとめ|ノーマライゼーションは「誰もが自分らしく暮らせる社会」を目指す理念
ノーマライゼーションとは、障害や高齢といった特性に関わらず、すべての人が地域で普通に暮らせる社会を目指す理念です。
バリアフリーやインクルーシブ教育といった取り組みは、その理念を実現するための具体的な方法といえます。介護や福祉の現場で働く人にとってはもちろん、私たち一人ひとりが「共に生きる社会」を意識することが大切です。















