介護保険で使える20万円の住宅改修の制度について詳しく解説
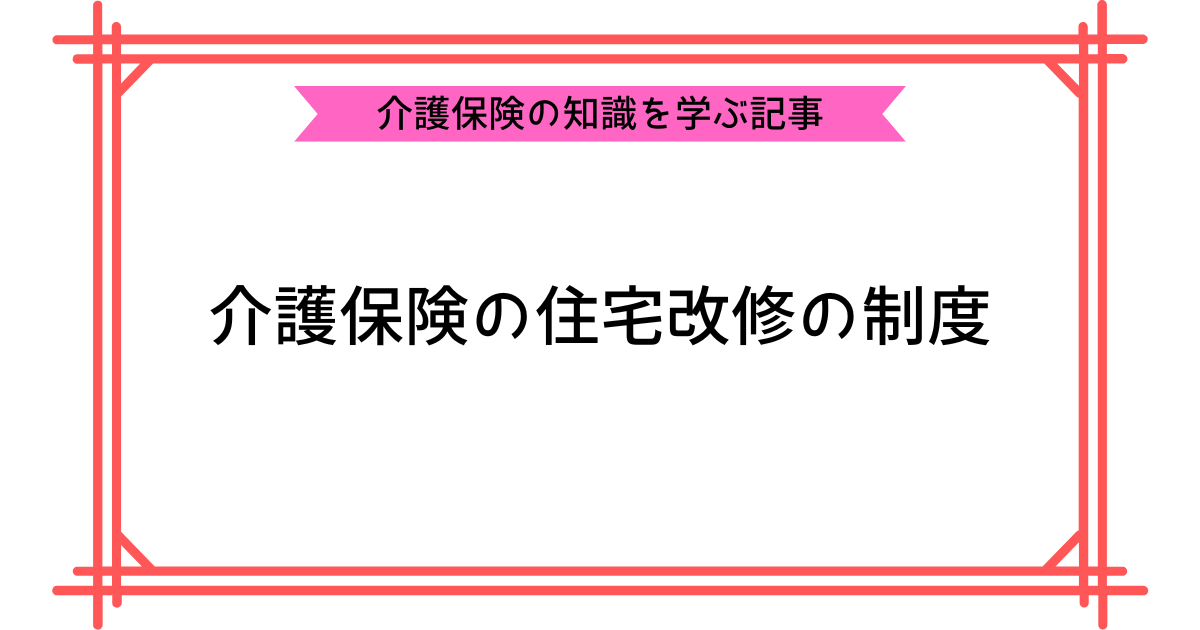
「手すりをつけたいけど費用が不安…」「玄関の段差が危ないけどリフォームは高そう…」
そんなお悩みを抱えているご家族に知っておいていただきたいのが、介護保険を利用した住宅改修制度です。
条件を満たせば、最大20万円までの工事費に対して9割(または8割・7割)の補助を受けられます。
この記事では、住宅改修制度の概要から対象となる工事内容、申請方法、注意点までをわかりやすく解説します。
住宅改修の制度とは?
介護保険の「住宅改修」は、要支援・要介護認定を受けた方が、自宅で安心して生活できるようにするための工事に対して補助を受けられる制度です。
上限は20万円まで(1人あたり一生涯で)。この20万円のうち、自己負担割合(原則1割)を差し引いた金額が介護保険から給付されます。
たとえば…
- 工事費が18万円 → 自己負担1割の方は 1.8万円、残りの 16.2万円が保険給付
- 工事費が25万円 → 上限20万円までしか給付対象にならず、超過分は全額自己負担
住宅改修の対象者は?
以下の条件すべてに当てはまる方が対象となります。
- 要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている人
- 自宅(本人の住居)で生活していること
- 介護が必要な理由で住宅の改修が必要と判断されていること
※施設入所中や入院中の場合は対象外です。
対象となる住宅改修の内容
介護保険の住宅改修として認められているのは、以下の6種類に限られています。
① 手すりの取り付け
- 廊下、階段、浴室、トイレ、玄関などに設置
- 転倒予防や移動の安定性確保のため
② 段差の解消
- スロープの設置、敷居の撤去、床のかさ上げなど
- 屋内外問わず対応可
③ 滑り防止・移動の円滑化のための床材変更
- 畳からフローリングへの変更など
- 浴室の床を滑りにくい素材に変更する工事も対象
④ 引き戸などへの扉の交換
- ドアを引き戸や折れ戸に変更
- 開閉の負担を軽減し、車いすでも通りやすくするため
⑤ 洋式便器などへの便器の取り替え
- 和式トイレから洋式への変更
- ただし単なる便器交換ではなく、介護上の必要性がある場合のみ
⑥ 上記の工事に付帯するもの
- 手すり設置のための壁の補強など
- 工事に必要な範囲の改修も認められる
住宅改修の流れ
申請から給付までの基本的な流れは以下のとおりです。
- ケアマネージャーに相談
▼ - 改修業者と打ち合わせ、見積書作成
▼ - 市区町村に「事前申請」(申請書・理由書・見積書・写真などを提出)
▼ - 市区町村から承認通知
▼ - 工事の実施
▼ - 工事後の完了報告・領収書提出
▼ - 給付金の受け取り(償還払い)
※一部自治体では「受領委任払い」対応の事業者であれば自己負担額のみの支払いで済む場合もあります。
注意すべきポイント
- 必ず「事前申請」が必要です。工事が終わってからでは給付の対象外になるので要注意。
- 引っ越した場合や再度要介護度が上がった場合でも、上限は原則20万円まで(ただし再度の支給が認められる特例もあり)。
- 改修内容は“介護が必要な理由”に基づいている必要があります。単なるバリアフリー工事では不可。
よくある質問Q&A
Q. 住宅改修は自分の持ち家でないとダメですか?
→ 借家でもOKです。 ただし、貸主(大家さん)の承諾が必要です。
Q. 複数回に分けて利用できますか?
→ できます。 上限の20万円の範囲内であれば、数回に分けて工事を行うことも可能です。
Q. リフォーム会社はどこでもいいの?
→ 自治体が指定する「受領委任払い」対応事業者や、介護リフォームに詳しい業者が安心です。ケアマネと相談しながら決めましょう。
まとめ
介護保険の住宅改修制度を利用すれば、最大20万円までの改修費に補助が出るため、高齢者の在宅生活を安全・快適に整えることができます。
申請のタイミングや必要書類には注意が必要ですが、ケアマネジャーや市区町村の窓口に相談しながら進めればスムーズです。
手すりの設置や段差の解消といった小さな改修でも、転倒リスクを大きく減らし、本人や家族の安心につながります。
ぜひこの制度を上手に活用して、安心して暮らせる住環境づくりを進めていきましょう。















