要介護と要支援の違いは?分かりやすく解説します!
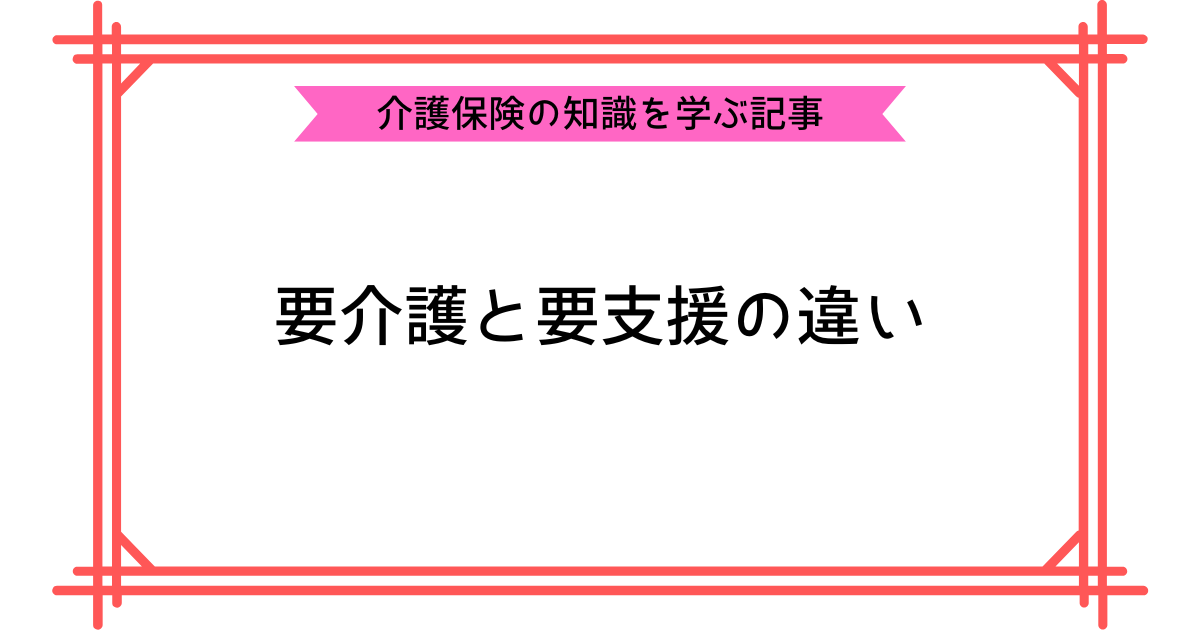
介護保険の認定を受けると、「要支援」または「要介護」といった区分が付けられますが、「この2つの違いがよくわからない…」「うちはどちらに該当するの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
実際、この違いは利用できるサービスや支援内容に大きく関係します。
この記事では、要支援と要介護の違いをわかりやすく解説し、それぞれの特徴や支援内容を比較してご紹介します。
要支援・要介護とは?制度の基本をおさらい
介護保険制度では、申請後に認定調査・医師の意見書をもとに、要介護認定審査会が「どの程度の介護が必要か」を判定します。
判定結果は、以下のいずれかに区分されます。
● 要支援1・2
介護が必要な状態ではあるが、比較的軽度な支援で日常生活を送ることができる人。
⇒ 主に「自立支援」「悪化予防」が目的。
● 要介護1~5
介護が日常的に必要な状態。数字が大きくなるほど、介護の必要度が高くなります。
⇒ 「生活支援」「身体介護」が中心。
要支援と要介護の主な違い【一覧で比較】
| 比較項目 | 要支援 | 要介護 |
|---|---|---|
| 認定区分 | 要支援1・2 | 要介護1〜5 |
| 目的 | 自立支援・予防 | 日常生活の支援・介護 |
| 支援計画 | 地域包括支援センターが作成 | ケアマネージャー(居宅)が作成 |
| 利用できるサービス | 地域支援事業中心(予防給付) | 介護保険サービスの本体 |
| 支給限度額(月額) | 約5万〜10万円程度 | 約16万〜36万円(要介護度による) |
| 主な対象者 | 一部介助で生活できる高齢者 | 常時介助が必要な高齢者 |
要支援の特徴と利用できるサービス
■ 要支援の目的
要支援の人に対する支援は、「今よりも悪くならないこと(自立支援)」が目的です。将来的に要介護状態になるのを防ぐため、軽度な支援で生活機能の維持を目指します。
■ 利用できる主なサービス
- 訪問型サービス(予防訪問介護)
⇒ 掃除や買い物などの生活援助が中心。身体介護は原則なし。 - 通所型サービス(予防デイサービス)
⇒ 機能訓練や体操、レクリエーションなどを提供。 - 福祉用具貸与・購入(軽度者向け)
⇒ 歩行器やシャワーチェアなどが対象。 - 住宅改修(手すり設置など)
⇒ 要介護と同様に利用可能(上限20万円)。
※要支援者のケアプランは、地域包括支援センターが作成します。
要介護の特徴と利用できるサービス
■ 要介護の目的
要介護者に対しては、生活全般の支援と身体介護が中心になります。トイレ・入浴・食事などの日常動作に支援が必要な方が対象です。
■ 利用できる主なサービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
⇒ 入浴・排泄・食事の介助、調理・洗濯・掃除など - 通所介護(デイサービス)
⇒ 送迎・入浴・食事・機能訓練を日帰りで提供 - 訪問看護・訪問リハビリ
⇒ 医療的ケア・自宅でのリハビリ - 短期入所(ショートステイ)
⇒ 家族が不在時などに一時的に施設で生活 - 施設サービス(要介護3以上)
⇒ 特別養護老人ホームなどの入所支援 - ケアマネージャーによるケアプラン作成
⇒ 居宅介護支援事業所に所属するケアマネが担当
認定区分が変わるとどうなる?
要支援から要介護に変更された場合、利用できるサービスの種類や量が大きく増えることがあります。反対に、要介護から要支援に下がると、一部のサービスが制限されることもあります。
そのため、本人の状態変化を把握し、必要に応じて「区分変更申請」を行うことが重要です。ケアマネージャーや地域包括支援センターに相談しながら、適切な支援につなげましょう。
まとめ
要支援と要介護の違いは、介護保険の支援をどの程度必要としているかに基づいて区分されます。
- 要支援:軽度な支援で自立を目指す
- 要介護:日常的な介護が必要な状態
この違いにより、使えるサービスの内容や支給限度額、ケアマネの担当者も変わってきます。まずは制度の概要を知り、状態に合った適切な支援を受けることが、ご本人とご家族の安心につながります。
わからないことがあれば、地域包括支援センターやケアマネージャーに気軽に相談してみましょう。















