【ケアマネ向け】医療系サービス開始時の主治医の意見の確認方法や文例、頻度を解説
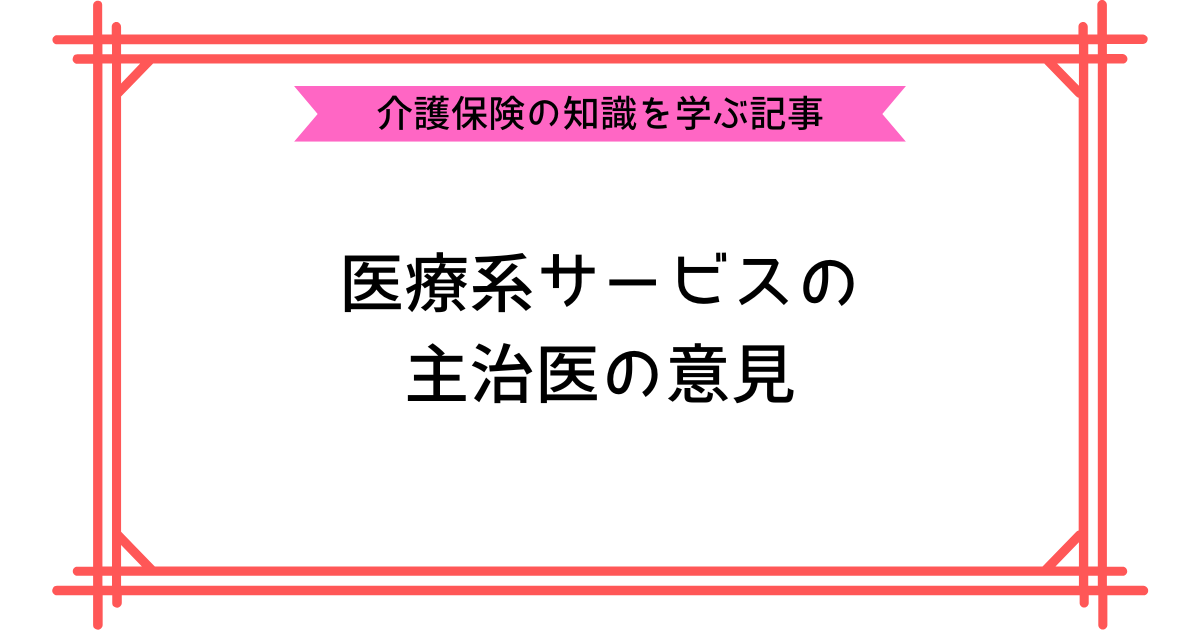
訪問看護や訪問リハビリテーションなど、医療系サービスを開始する際に欠かせないのが「主治医の意見の確認」です。
介護支援専門員(ケアマネジャー)として、医師とスムーズに連携を取るためには、正確な確認方法と適切な文書のやり取りが不可欠です。
この記事では、医療系サービス開始時における主治医の意見確認の流れや頻度、文例などを、現場で実践しやすい形で解説します。
医療系サービスとは?確認が必要なサービス一覧

医療系サービスとは、介護保険における医療職(看護師・リハビリ職など)が提供するサービスを指します。
開始には主治医の指示や意見が必須とされている場合が多く、以下が代表的です。
| サービス名 | 主治医の指示の必要性 |
|---|---|
| 訪問看護 | 必須(指示書) |
| 訪問リハビリテーション | 必須(指示書) |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 必須(指示書) |
| 短期入所療養介護(医療型ショート) | 医師の情報提供が必要 |
※「訪問介護」「通所介護(デイサービス)」などの生活支援系サービスは医師の指示不要です。
主治医の意見の確認方法(ケアマネの実務)

1. まずは本人・家族から医療機関情報を聴取
- 主治医の氏名、医療機関名、連絡先を確認
- 診療科や通院頻度も併せて把握しておくと良い
2. 医療系サービス提供事業所と連携
訪問看護・訪問リハなどを導入する際は、サービス事業所が主治医に「指示書」を依頼するため、ケアマネからもその旨を共有しておくことが重要です。
- 「〇〇訪問看護ステーションが指示書依頼予定」と伝達
- 医師側が事業所名を把握しておくことで、対応がスムーズになる
3. 医師に意見を求める方法
主治医に意見を求める方法は以下のとおりです。
- 医師宛に「照会文書」「情報提供依頼書」をFAXまたは郵送
- 本人が通院する際に、家族経由で意見書依頼文を渡してもらうこともある
- 地域によっては「医療介護連携シート(医介連シート)」を活用
主治医への照会文書・意見確認の文例(テンプレ)
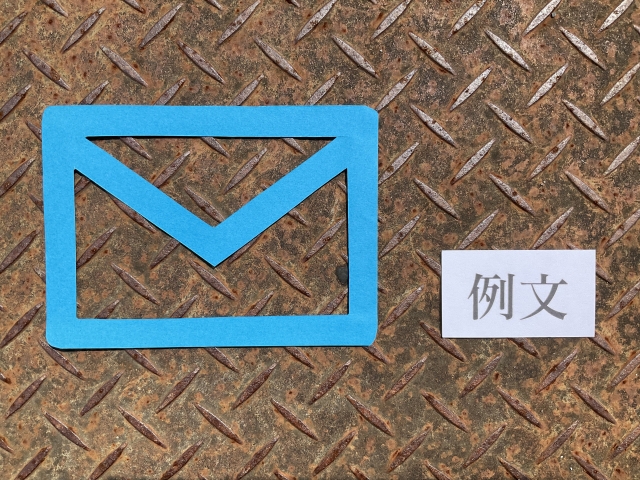
◆例文:訪問看護開始にあたっての照会文
〇〇クリニック 〇〇先生
いつもお世話になっております。
居宅介護支援事業所〇〇の介護支援専門員、〇〇と申します。
このたび、〇〇様(要介護3)に訪問看護サービスの導入を検討しており、主治医である先生のご意見を伺いたくご連絡いたしました。
差し支えなければ、以下の点についてご教示いただけますと幸いです。
- 訪問看護導入の適否
- 現在の医療的な管理内容(服薬・血圧・インスリンなど)
- 指示書作成のご対応可否
ご多忙中とは存じますが、よろしくお願い申し上げます。
令和〇年〇月〇日
介護支援専門員 〇〇〇〇
連絡先:〇〇-〇〇〇〇
※地域連携ルールに応じて文面を調整してください。
医療系サービスにおける主治医意見確認の頻度とタイミング
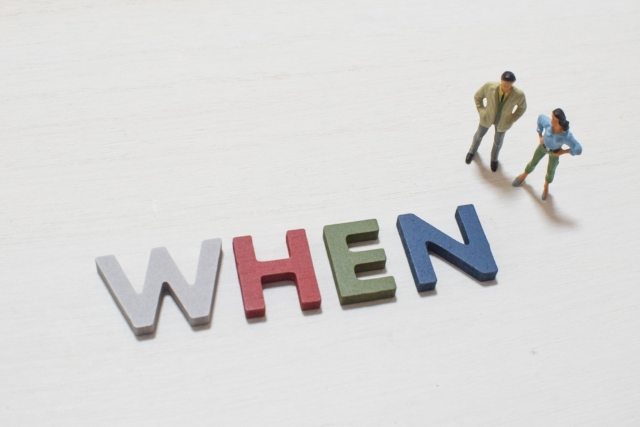
● 新規導入時
- 訪問看護・訪問リハ開始時は必ず指示書が必要
- ケアプラン作成前後で、事業所との連携を取りながら確認
● サービス継続時(定期更新)
- 指示書の有効期限は原則6ヶ月間(180日)
- 更新タイミングに合わせて再確認が必要
● 状態変化時
- 入退院、急性疾患、リハビリの中止・再開時などは随時確認が望ましい
注意点と現場での工夫

● 医師への配慮を忘れずに
医師は多忙なため、照会は簡潔に・要点を絞って依頼することが大切です。
FAXを使う場合は、A4用紙1枚で完結するように工夫すると好印象です。
● 書類の控えを残す
確認文書・指示書などは、介護支援専門員の記録として保管が必要です。モニタリング記録にも反映しましょう。
● 地域連携を活用する
医療と介護のスムーズな連携のため、地域によっては「医療・介護連携手帳」や「ICT連絡システム」などを活用している場合もあります。地域資源を積極的に活用しましょう。
まとめ
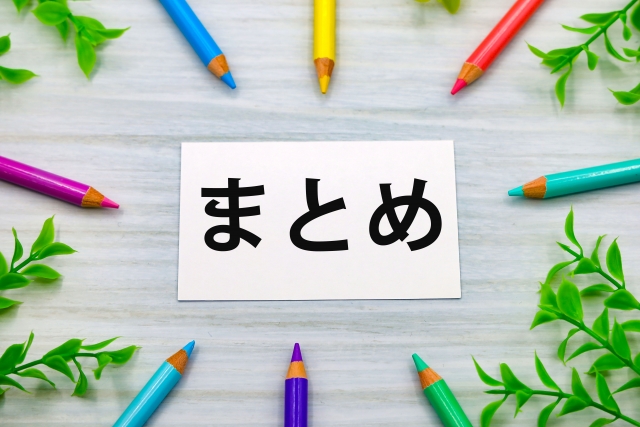
医療系サービスを導入・継続するうえで、主治医の意見確認はケアマネジャーにとって欠かせない実務です。
確認方法や頻度、文書の作成についてしっかり把握し、主治医・家族・事業所とのスムーズな連携を心がけることで、利用者にとって最適な医療・介護支援が実現できます。
本記事を参考に、日々の支援にぜひ役立ててください。















