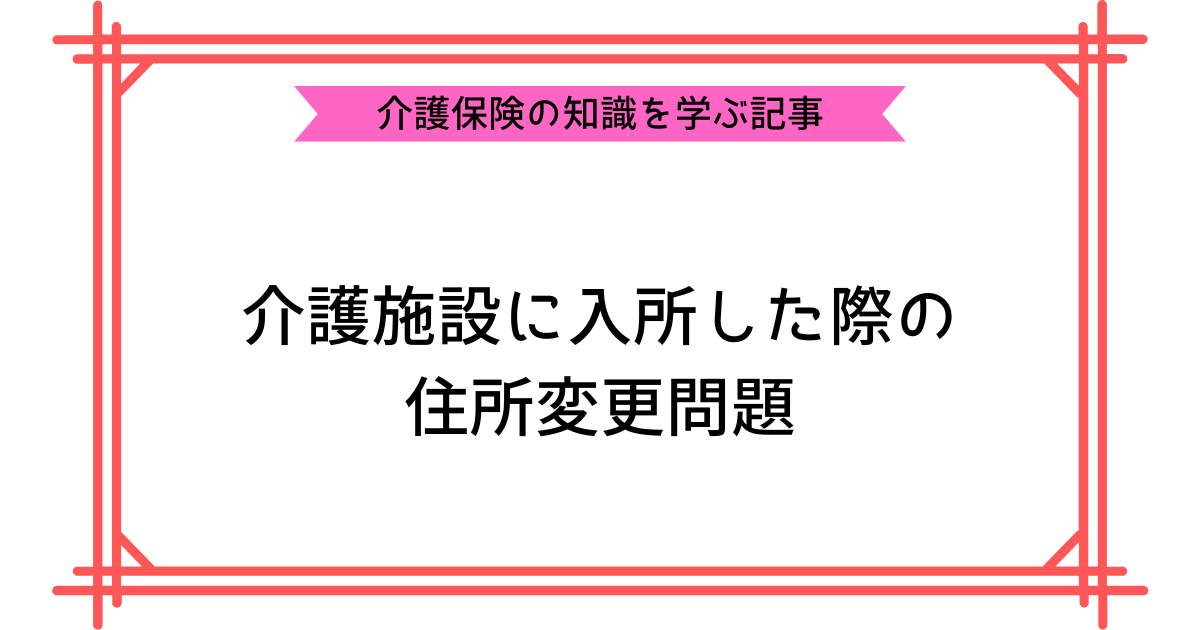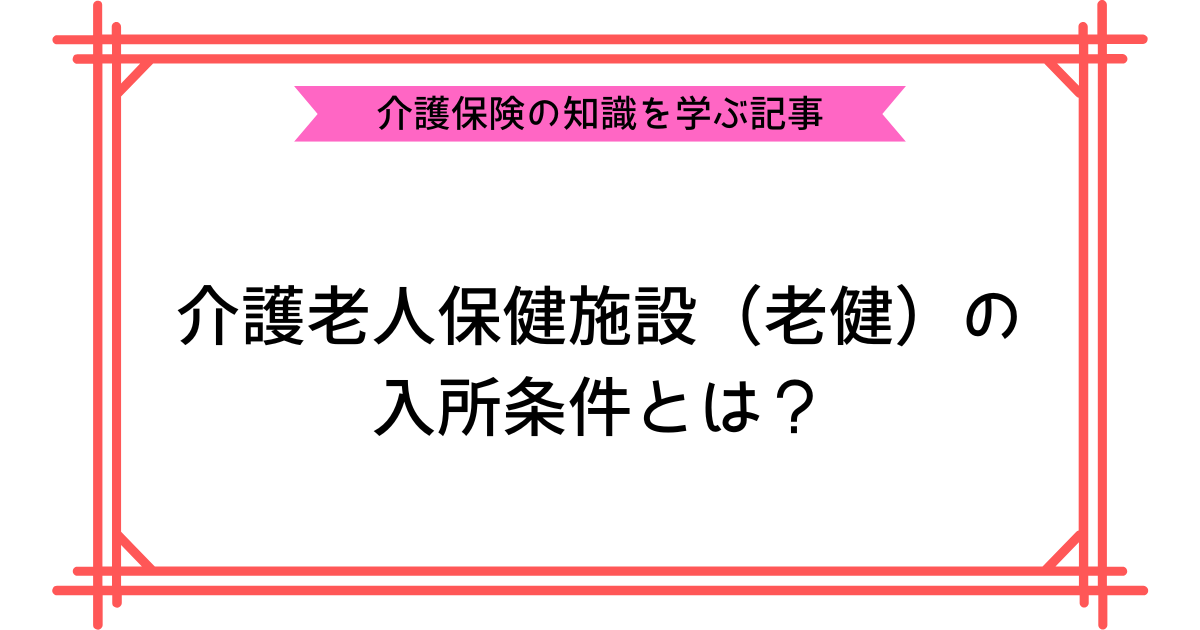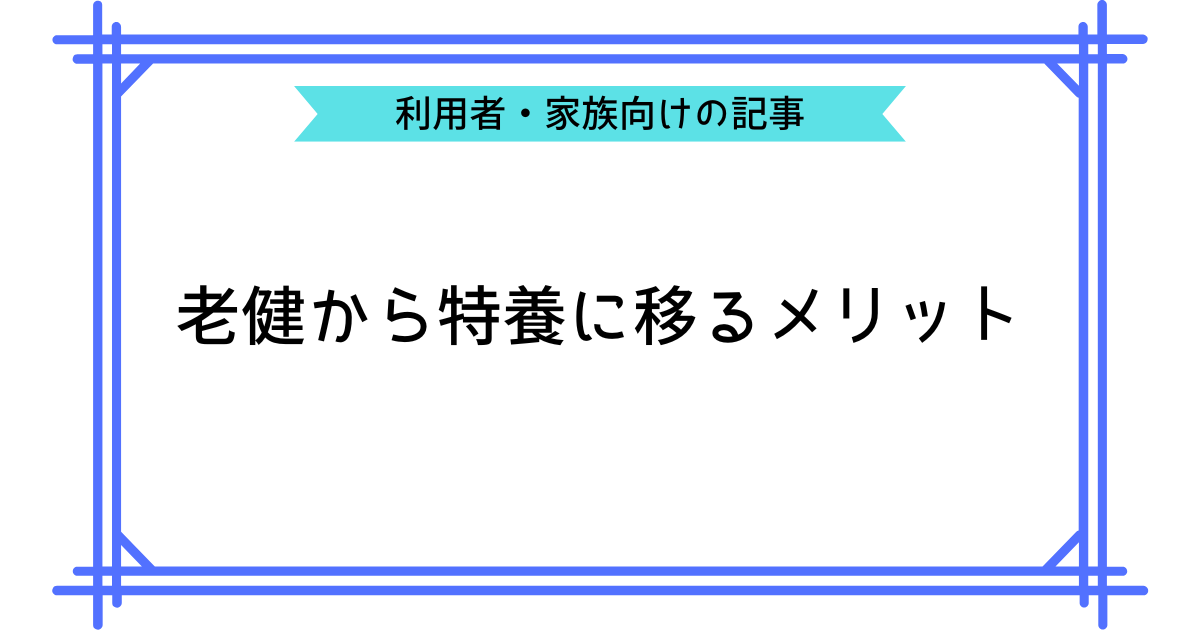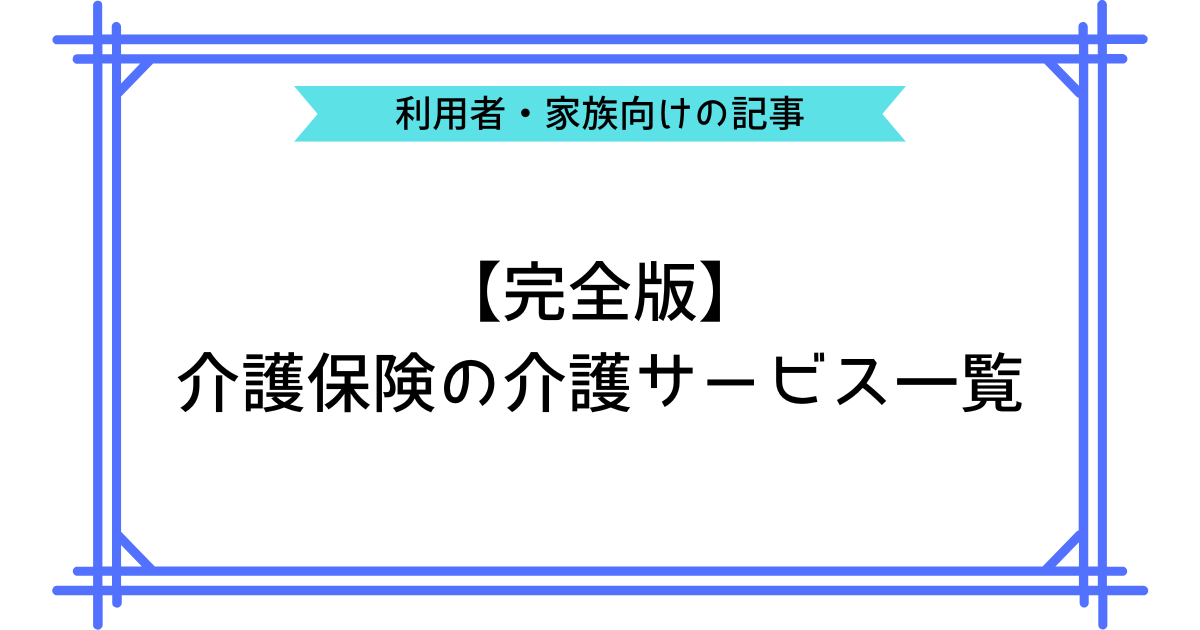介護老人保健施設(老健)とは?わかりやすく解説
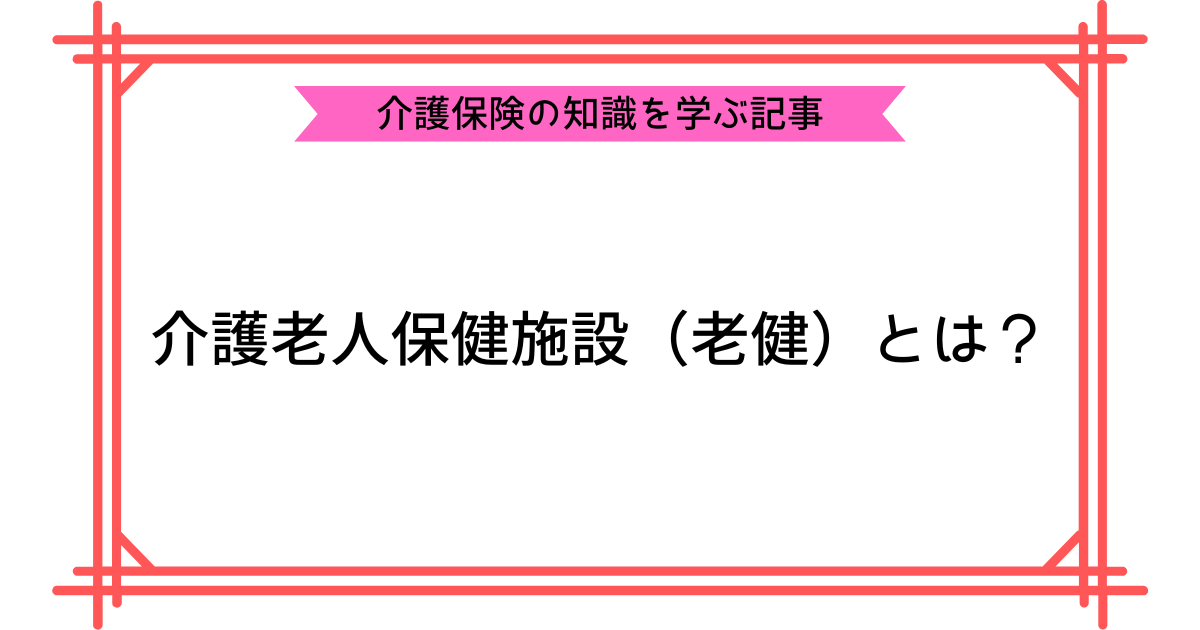
介護保険サービスの中で「特養(特別養護老人ホーム)」と並んでよく耳にするのが介護老人保健施設(老健)です。
通称「老健(ろうけん)」は、在宅復帰を目指す高齢者が一時的に入所し、医療やリハビリを受けながら生活する施設です。
しかし「特養とどう違うの?」「誰が利用できるの?」「費用は?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、介護老人保健施設の特徴や対象者、利用料金、メリット・デメリット、入所までの流れをわかりやすく解説します。
介護老人保健施設(老健)とは?
概要
介護老人保健施設(老健)は、病院と在宅の中間に位置づけられる介護保険施設です。医師、看護師、リハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)などが配置されており、退院後すぐに自宅に戻るのが不安な高齢者や、在宅生活が一時的に困難な人が入所します。
老健の目的は「在宅復帰」。医療管理のもとでリハビリを行い、できるだけ早く自宅生活に戻れるようにサポートする施設です。
サービス内容
医師・看護師による健康管理
日常の体調管理、服薬管理、必要に応じた医療処置を行います。病院ほどの高度医療は行えませんが、慢性疾患の管理や緊急対応は可能です。
リハビリテーション
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による機能訓練を提供。歩行練習、日常生活動作訓練、嚥下訓練などを行います。
介護サービス
入浴・食事・排泄などの日常生活援助を受けられます。
相談・支援
退所後の生活に向けて、ソーシャルワーカーやケアマネジャーが家族と連携し、在宅復帰に必要な環境整備を支援します。
対象者
- 要介護1〜5の認定を受けた人
- 病院を退院したが、自宅生活に不安がある人
- 集中的なリハビリを必要とする人
- 在宅生活が一時的に困難な人
※要支援の人は原則利用できません。
利用料金
自己負担の仕組み
介護保険が適用され、介護サービス費の1〜3割が自己負担となります。これに加え、居住費や食費、日常生活費がかかります。
自己負担額の目安(1割負担の場合)
- 介護サービス費:約25,000〜35,000円/月(要介護度による)
- 居住費:20,000〜50,000円/月
- 食費:40,000〜50,000円/月
- 日常生活費(おむつ代、理美容代など):数千円〜
合計で 月額8万〜15万円程度 が目安です。
老健のメリット
1. リハビリが充実している
理学療法士や作業療法士によるリハビリを継続的に受けられるため、身体機能の維持・回復に効果的です。
2. 医療と介護の両方を受けられる
医師・看護師が常勤しており、慢性疾患のある方も安心して生活できます。
3. 在宅復帰に向けた支援
退所後の生活を見据え、住宅改修や福祉用具導入の相談にも対応。家族への介護指導も行われます。
4. 比較的低額で利用可能
民間の有料老人ホームと比べ、自己負担額が抑えられています。
老健のデメリット・注意点
1. 入所期間は原則3〜6か月
老健は「在宅復帰」が目的のため、長期入所には向きません。原則は3〜6か月程度で、自宅や他施設への移行を前提としています。
2. 医療対応は限定的
病院のような高度な医療は提供できません。点滴や軽度の医療処置は可能ですが、重度の医療依存がある人は介護医療院や病院が適しています。
3. 特養に比べて安定性が低い
老健は「一時的に利用する施設」という性格が強いため、終の棲家としては不向きです。
4. 待機者がいる地域もある
特養ほどではありませんが、地域によっては老健の入所待ちが発生する場合もあります。
入所までの流れ
- 要介護認定を受ける
市区町村に申請し、要介護1〜5と認定される。 - 老健へ申し込み
希望する施設に直接申込書を提出。医師の診断書が必要な場合もあります。 - 面談・判定
施設の医師や職員が本人・家族と面談し、健康状態や生活状況を確認。 - 入所判定会議
医師・看護師・リハビリ職員などが入所の可否を判定。 - 契約・入所開始
契約後、入所が決定。入所期間は原則数か月単位で調整されます。
他施設との違い
- 特養(介護老人福祉施設):終の棲家として長期利用が前提。要介護3以上が対象。
- 介護医療院:医療と介護を長期的に受けられる。医療依存度が高い人向け。
- 有料老人ホーム:民間施設で、費用は高いがサービスの自由度が高い。
老健は「退院後すぐに自宅へ戻るのは不安」「リハビリを集中的に受けたい」という人に最適です。
まとめ
介護老人保健施設(老健)は、病院と自宅の中間施設として位置づけられ、在宅復帰を目指すリハビリと医療・介護を一体的に提供する施設です。費用が比較的安く、リハビリが充実している点がメリットですが、長期入所には向かない点や医療対応の限界もあります。
利用を検討する際は、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、自宅復帰を見据えたケアプランを立てることが大切です。