軽度者(要支援1・2、要介護1)に対する福祉用具の例外給付の理由書の記入例
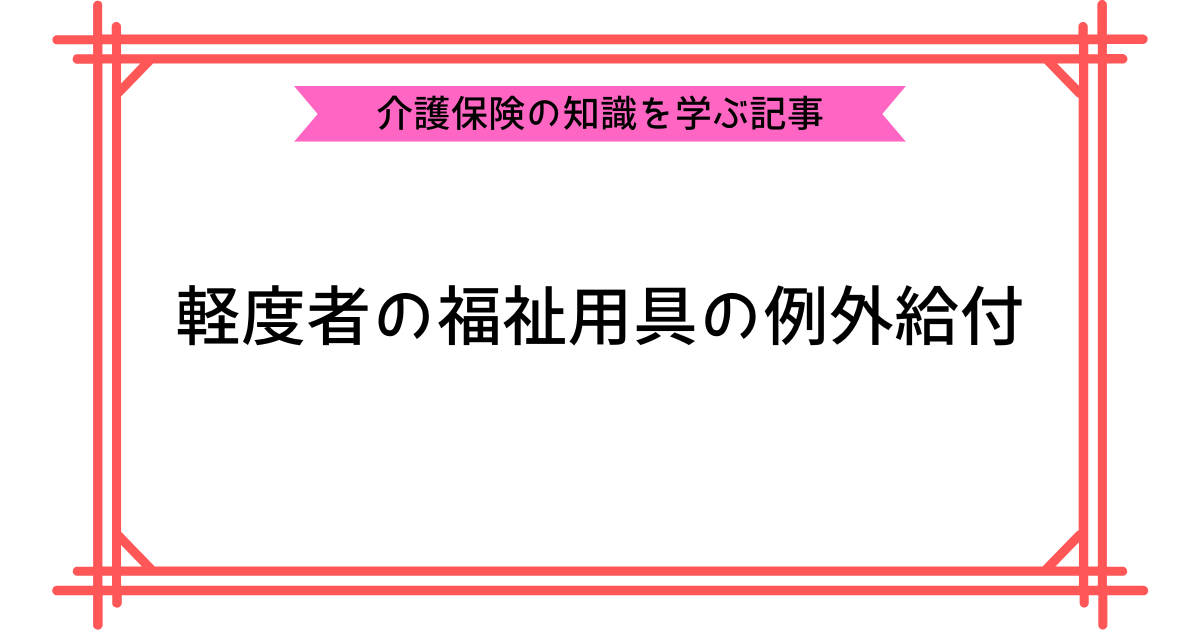
介護保険制度では、原則として要支援1・2および要介護1の「軽度者」に対して、特定の福祉用具の貸与が制限されています。
しかし、利用者の身体状況や生活環境によっては、例外的に福祉用具の給付が認められるケースもあります。
その際に必要となるのが「理由書」の提出です。
この記事では、軽度者への福祉用具例外給付についての概要と、理由書の記載例を5パターンご紹介します。
実務での記入の参考にぜひご活用ください。
軽度者における福祉用具の「原則貸与除外」とは?

介護保険制度では、要支援1・2および要介護1の方(軽度者)に対しては、「車いす」「特殊寝台」「床ずれ防止用具」など一部の福祉用具は、原則として貸与の対象外とされています。
これは、比較的自立度の高い方に対しては、これらの用具の必要性が少ないとされているためです。
しかし、実際には軽度者でも転倒リスクが高い・介助が困難・疾患がある等の理由で、一定の福祉用具が必要となる場面もあります。
そのようなケースでは、「例外給付」として福祉用具の貸与が認められる場合があり、ケアマネージャーが作成する理由書の提出が必要です。
例外給付の対象となる主な福祉用具

以下の用具は、軽度者には原則として貸与が制限されていますが、例外的に必要性が認められた場合は給付の対象となります。
- 特殊寝台(介護用ベッド)
- 特殊寝台付属品(サイドレール・マットレスなど)
- 車いす(普通型・介助型)
- 車いす付属品
- 床ずれ防止用具(エアマットなど)
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
理由書作成時のポイント

理由書作成時のポイントは下記の通りです。
- 具体的かつ客観的な記載を心がけましょう(例:ADLの状態、転倒歴、介護者の有無など)。
- 利用者本人だけでなく、介護者の負担にも触れると説得力が増します。
- 単なる希望ではなく、医学的・生活的必要性を説明することが重要です。
軽度者に対する福祉用具・例外給付の理由書 記入例【5パターン】

以下に、よくある例外給付申請時の理由書の記載例を紹介します。
【記入例①】特殊寝台(ベッド)+サイドレールの貸与希望(要介護1)
利用者は、パーキンソン病による筋固縮が進行しており、起き上がりや立ち上がりに介助を要する状態。布団からの起居動作が困難であり、転倒リスクも高い。特殊寝台により高さ調整や起き上がりが可能となることで、本人の自立支援と介護者の負担軽減が図れるため、貸与が必要と判断する。
【記入例②】車いすの貸与希望(要支援2)
利用者は脊柱管狭窄症により、屋外歩行時に間欠性跛行が見られ、100m以上の歩行が困難。歩行器の使用歴あり。外出時に転倒リスクが高く、通院やデイサービス利用に支障をきたしている。安全な移動のため、車いすの貸与が必要と判断する。
【記入例③】床ずれ防止用具(エアマット)貸与希望(要介護1)
利用者は糖尿病性神経障害があり、感覚鈍麻が進行。仰臥位で過ごす時間が長く、既に臀部に発赤が見られる。現状の一般マットレスでは除圧が不十分であり、エアマットの使用が褥瘡予防に必要と判断する。
【記入例④】体位変換器の貸与希望(要支援1)
独居の利用者で、脳梗塞の後遺症により左片麻痺がある。夜間の寝返りが自力で困難で、朝方に肩や腰の痛みを訴えることが増えた。家族の同居はなく、介護者のサポートも受けにくいため、体位変換器の貸与が望ましい。
【記入例⑤】認知症老人徘徊感知機器の貸与希望(要介護1)
アルツハイマー型認知症により、深夜や早朝に玄関から外出しようとする行動が複数回確認されている。家族は就寝中で対応が間に合わない状況があり、事故防止のために徘徊感知機器(センサー等)の設置が必要と判断する。
まとめ

要支援1・2や要介護1の「軽度者」に対しても、状況によっては福祉用具が必要なケースは少なくありません。
その際には、例外給付の仕組みを利用することで、必要な支援を確保することが可能です。
理由書は、単なる申請書ではなく、「なぜ必要なのか」を具体的かつ客観的に説明する重要な書類です。
今回ご紹介した文例を参考にしながら、利用者の実態に即した内容を記載し、適切な支援につなげていきましょう。















