介護保険の自己負担割合(1割、2割、3割)とは?分かりやすく解説
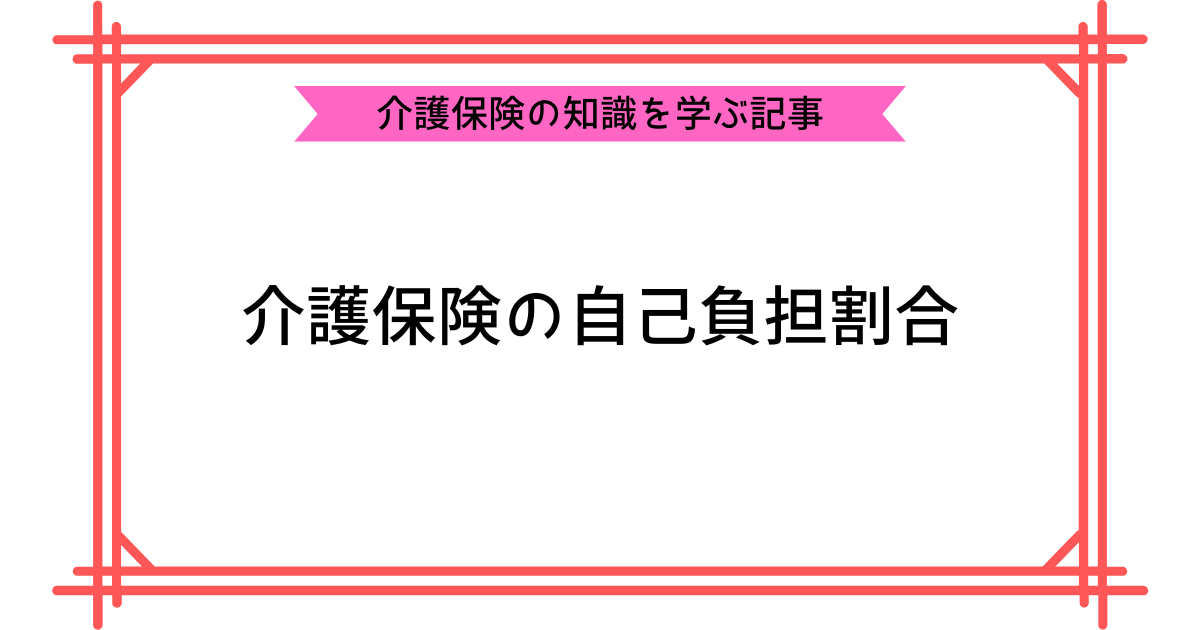
介護保険サービスを利用する際、多くの方が気になるのが「自己負担はいくらかかるの?」という点ではないでしょうか。
実は、介護保険の自己負担割合は1割だけでなく、2割・3割と人によって異なります。
この記事では、自己負担割合がどう決まるのか、1割・2割・3割それぞれの対象者や計算方法、注意点までをわかりやすく解説します。
介護保険の自己負担とは?

介護保険は、要支援・要介護認定を受けた人が、介護サービスを受けた際にかかる費用の一部を自己負担する仕組みになっています。
原則として、かかったサービス費用の一部を利用者が負担し、残りを保険でまかなうという形です。
たとえば、訪問介護に1万円かかった場合、自己負担が1割の人は1,000円、2割の人は2,000円、3割の人は3,000円を支払います。残りの費用は介護保険から給付されます。
自己負担割合の種類と対象者
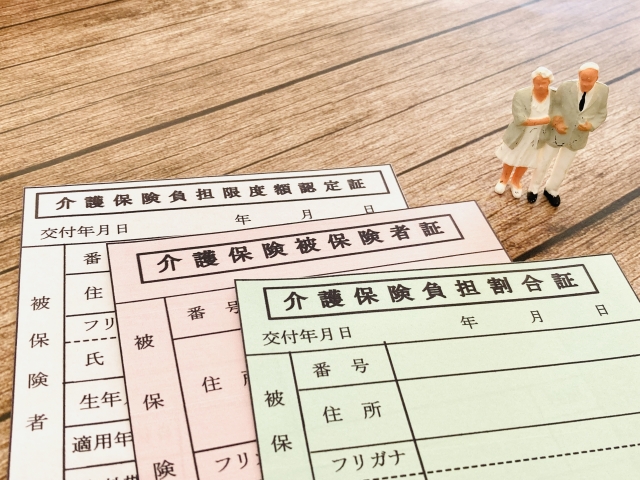
介護保険の自己負担割合は、以下の3つに分かれています。
| 割合 | 対象者の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1割負担 | 多くの方(所得が比較的低い方) | 原則的な負担割合。 |
| 2割負担 | 一定以上の所得がある方 | 2015年の制度改正で導入。 |
| 3割負担 | 高所得者 | 2018年から導入された新しい区分。 |
※この割合は「自己負担割合証」に記載されており、市区町村から毎年送付されます。
自己負担割合はどうやって決まるの?

自己負担割合は、本人および世帯の所得に応じて決定されます。正確には、以下の情報がもとになります。
- 本人の合計所得金額(年金や給与など)
- 世帯内に同じ医療保険(後期高齢者医療制度など)に加入している人の所得状況
- 市区町村が確認する前年の所得情報
判定は「前年の所得」に基づいて行われ、毎年7月頃に新しい「負担割合証」が届きます。
自己負担割合の目安(2024年現在)

● 1割負担の対象者(多くの方)
以下のすべてに該当する人は、自己負担は原則1割です。
- 年間の合計所得金額が160万円未満
- 世帯内の他の同一保険加入者も全員が1割対象の場合
つまり、一般的な年金生活者の多くがこの対象になります。
● 2割負担の対象者
以下の条件に当てはまると、2割負担となります。
- 本人の合計所得が160万円以上で、かつ
- 世帯全員が1割対象ではない(一定以上の所得がある世帯)
主に、比較的高めの年金収入や、退職後も収入のある人が該当します。
● 3割負担の対象者
2024年現在、以下の条件に当てはまる人は3割負担です。
- 本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ
- 同じ医療保険の加入者の年収合計が346万円以上(単身)または463万円以上(2人世帯)
現役並みの所得を得ている高齢者が対象となります。
介護保険の自己負担割合の具体例

具体的なサービスごとの負担額を比較してみましょう。
| サービス内容 | サービス費用 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護(30分) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| デイサービス(1日) | 7,000円 | 700円 | 1,400円 | 2,100円 |
| 福祉用具貸与(1ヶ月) | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 |
※上記は一例です。地域やサービス事業所によって差がある場合があります。
自己負担が高額になったときの「高額介護サービス費制度」

自己負担割合が上がると、「介護費用が高くなりすぎるのでは…」と心配になる方もいるかもしれません。
そんなときに役立つのが「高額介護サービス費制度」です。
これは、ひと月あたりの自己負担が一定額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
所得に応じた「上限額」が決まっており、1割~3割負担にかかわらず、負担軽減が図られます。
まとめ

介護保険の自己負担割合は、1割・2割・3割と所得に応じて異なります。
ほとんどの方は1割負担ですが、収入や世帯の構成によって2割・3割になるケースもあります。
自分がどの割合に該当するかは、「介護保険負担割合証」で確認ができます。
サービスを上手に利用しながら、費用の見通しも立てることが、安心した在宅生活を続けるためにはとても大切です。
不明な点がある場合は、地域包括支援センターや担当ケアマネージャーに相談してみましょう。















