区分変更申請とは?区分変更申請理由の文例も5パターン紹介
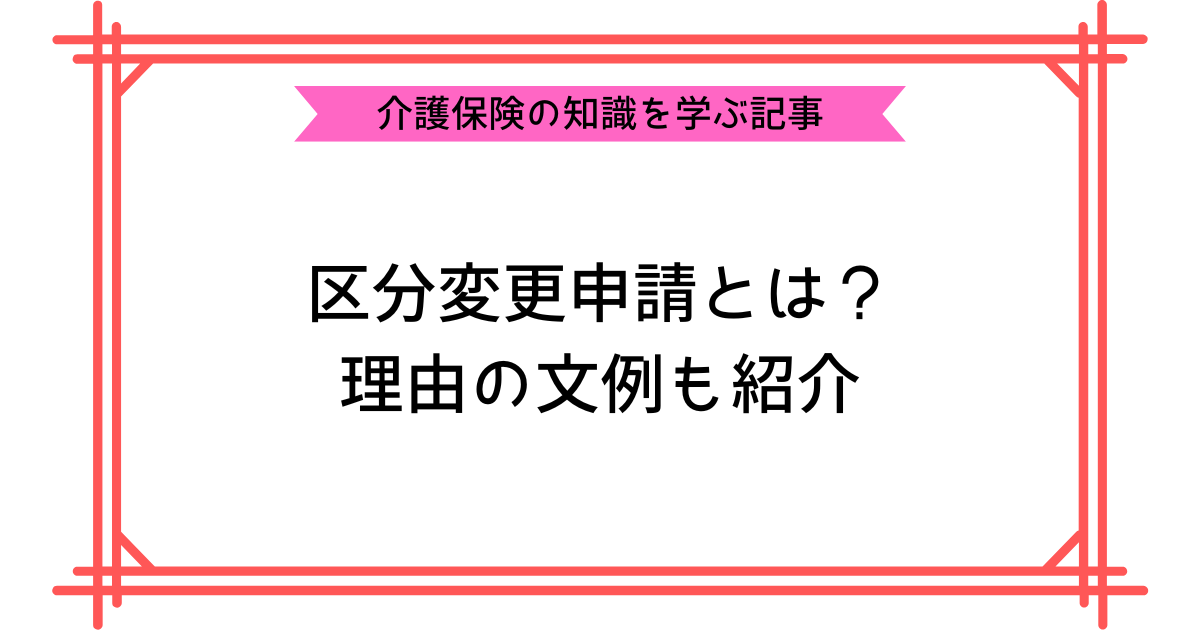
介護保険制度において、要介護度は利用者の心身の状態に応じて定められます。
しかし、状態が変化したときには、現在の要介護度では必要なサービスを受けるのが難しくなることもあります。
そんなときに活用できるのが「区分変更申請」です。
この記事では、区分変更申請の基本的な仕組みや流れを解説し、実際に申請する際に役立つ「理由の文例」を5パターンご紹介します。
区分変更申請とは?
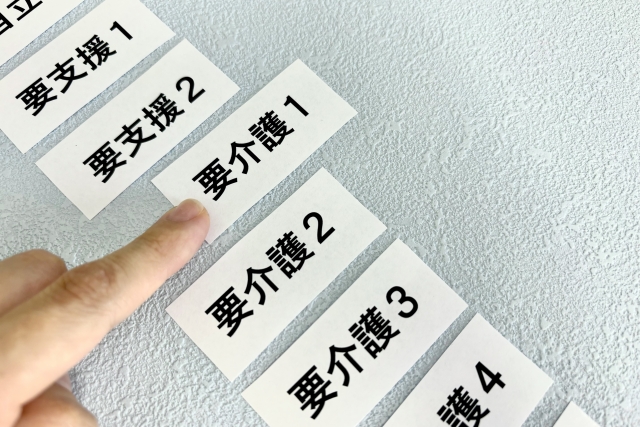
区分変更申請とは、要介護認定をすでに受けている方が、心身の状態の変化により「現行の要介護度では適切なサービスが受けられない」と判断された場合に、改めて要介護認定の見直しを申請する制度です。
たとえば、要支援2の方が転倒により歩行が困難になったり、認知症が進行して日常生活に大きな支障が出るようになったときなどが該当します。
このようなケースでは、現状の介護度では利用できるサービス量や種類が足りなくなる可能性があるため、区分変更によって適切な介護度を再設定する必要があります。
区分変更申請の流れ
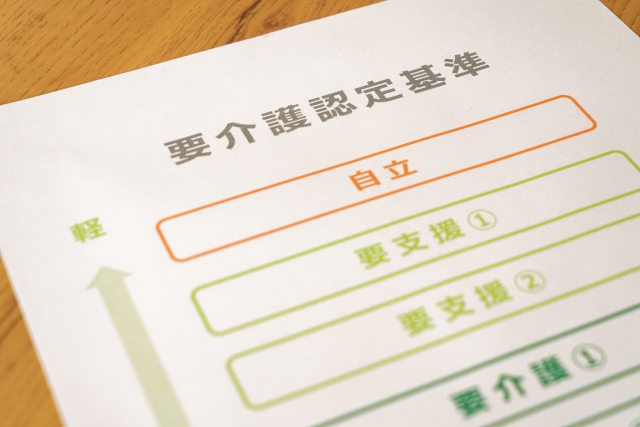
申請は、市区町村の介護保険担当窓口に対して行います。
基本的な流れは以下のとおりです。
- 状態変化の把握:ケアマネージャーや家族が、利用者の状態の悪化や変化を確認します。
- 主治医の意見書の再作成:申請にあたり、主治医の診断書が必要になります。
- 区分変更申請書の提出:市区町村の窓口に必要書類を提出します。
- 認定調査の実施:訪問調査員による聞き取りと観察が行われます。
- 介護認定審査会による審査・判定
- 結果通知と新たな認定の適用
結果が出るまでには概ね30日程度かかります。
結果が出るまでは、原則として現行の要介護度に基づいたサービス提供が続きます。
区分変更申請が必要な主なケース

- 転倒・骨折によりADL(日常生活動作)が著しく低下した
- 認知症の進行により徘徊や夜間の介助が必要になった
- パーキンソン病やALSなどの進行性疾患の悪化
- 急激な体重減少や食事摂取量の低下による衰弱
- 退院後、在宅生活が困難で生活支援が増加した
このような状況では、現行の介護度ではサービスが不足するため、区分変更を検討する価値があります。
区分変更申請理由の文例 5パターン
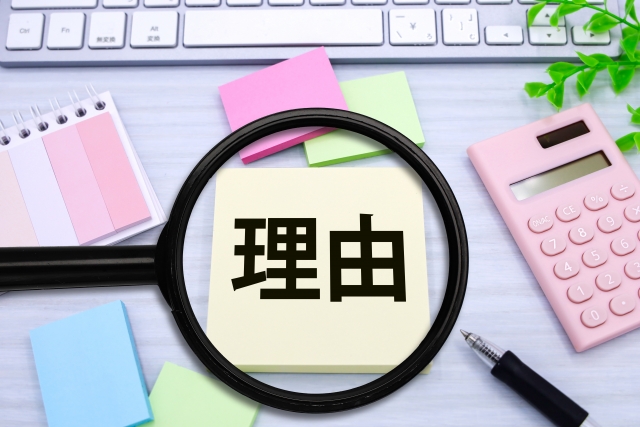
ここでは、実際に申請書に記載する「状態変化の理由」の文例を5つ紹介します。
状況に応じて参考にしてください。
文例①:転倒による骨折・ADL低下
令和○年○月に自宅内で転倒し、大腿骨頸部骨折と診断され入院。手術を受けたものの、歩行が困難となり、自宅内でも常時の介助が必要な状態。日常生活動作全般に著しい制限が出ているため、現行の要介護度ではサービスが不足している。
文例②:認知症の進行による徘徊・夜間対応増加
最近になって認知症が進行し、昼夜の逆転や夜間徘徊が頻発するようになった。自宅内でも場所の認識ができず、常時見守りが必要となっており、家族の介護負担も増している。
文例③:退院後の状態悪化により支援が必要
脳梗塞で入院し、退院後に在宅介護へ移行。片麻痺と失語症の後遺症があり、移動・排泄・食事など全般に介助を要する状態。従来の要介護度では必要なサービス量が確保できないため、区分変更を希望。
文例④:進行性疾患の悪化(パーキンソン病など)
パーキンソン病の進行により筋力の低下が著しく、移乗や更衣にも全面的な介助が必要となっている。振戦や姿勢反射障害も顕著で、転倒リスクも高く、支援体制の強化が必要な状態。
文例⑤:急激な体重減少と全身衰弱
食欲低下が続き、ここ1か月で5kg以上の体重減少あり。食事摂取量が大きく落ち込み、全身状態が不安定。ベッド上での生活が多く、寝たきり状態に近づいているため、早急な支援強化が求められる。
区分変更申請時の注意点

区分変更申請時の注意点は下記のようなものがあります。
- 主治医と早めに連携する:主治医の意見書が必要になるため、状態変化を早めに伝え、記載内容との整合性を保つことが重要です。
- ケアマネとの連携を大切に:ケアマネは申請手続きや記録作成をサポートしてくれる頼れる存在です。状況を詳細に共有しましょう。
- 書類の記載内容は正確に、具体的に:漠然とした表現より、「いつ・どんな変化があったか」を明確に記載することで、審査の理解が得やすくなります。
まとめ

区分変更申請は、要介護者の状態変化に応じて、より適切な介護サービスを受けるための大切な手続きです。
申請に際しては、主治医やケアマネージャーと密に連携し、現状に即した具体的な理由を伝えることが重要です。
今回ご紹介した文例も参考にしながら、しっかりと準備を進めて、必要な支援が適切に届くよう対応していきましょう。
適切なサービスが受けられることは、本人の生活の質(QOL)や家族の介護負担軽減にもつながります。















