要介護度が上がるとどうなる?メリットとデメリットを解説
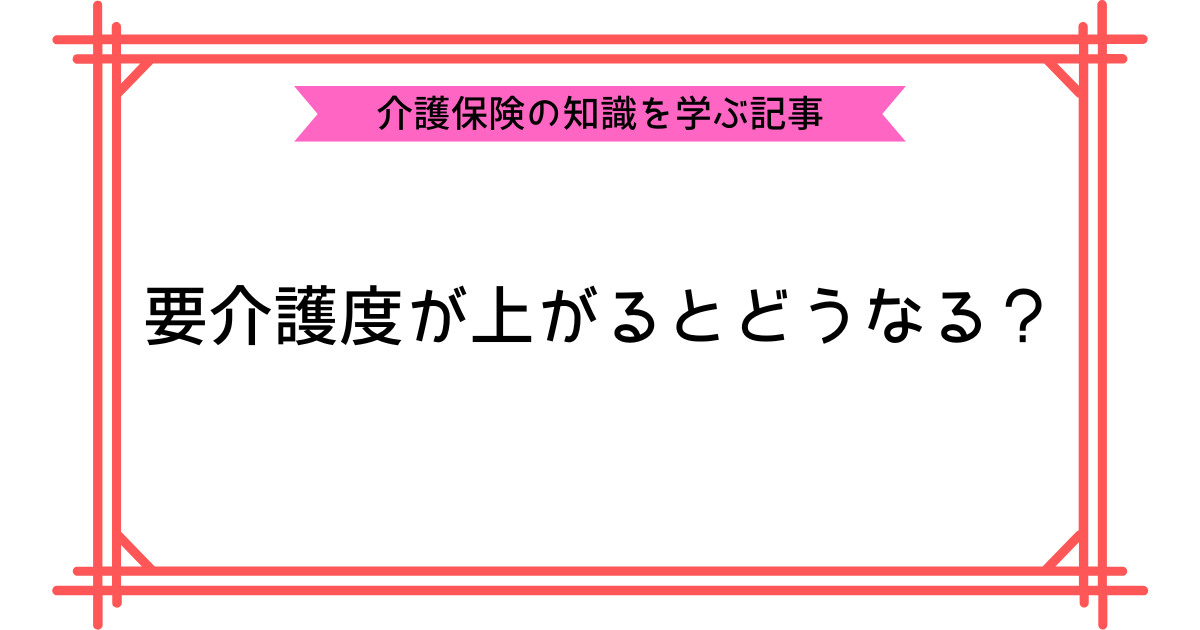
介護をしていると、「最近、介助の手間が増えた気がする」「このままでは今の介護サービスだけでは足りないのでは?」と感じることがあります。
そうした場合に検討されるのが「要介護度の変更」、いわゆる区分変更申請です。
しかし、要介護度が上がるとどう変わるのか、メリットや注意点を知らないまま手続きを進めるのは不安ですよね。
本記事では、要介護度が上がった場合に何が変わるのか、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
要介護度が上がるとは?基礎知識を簡単におさらい
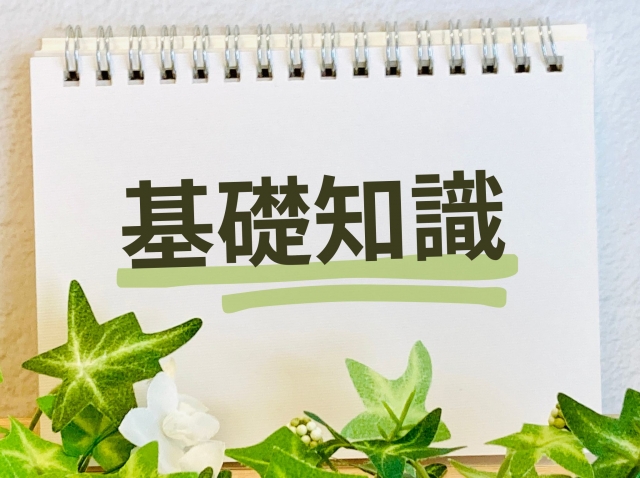
介護保険制度では、要支援1・2と要介護1〜5の7段階の認定区分があります。
要介護度が上がるとは、「要介護2から要介護3に」「要支援2から要介護1に」など、心身の状態の変化に応じてより重度な認定を受けることを指します。
この認定は、本人の状態を市区町村が調査・審査して決定するもので、必要な介護サービス量に影響する重要な指標です。
要介護度が上がるとどうなる?【メリット編】

1. 利用できるサービスの幅が広がる
要介護度が上がると、利用できるサービスの種類が増えることがあります。たとえば、ショートステイの回数が増やせる、訪問介護を週に何回も利用できるなど、現状の支援では不足していた部分を補うことが可能になります。
2. 支給限度額が増える
介護保険サービスには、要介護度ごとに「月額で使える上限(支給限度額)」が決まっています。要介護度が高くなると、この上限が上がるため、より多くのサービスを自己負担を抑えて利用できます。
| 要介護度 | 支給限度額(月額・目安) |
|---|---|
| 要介護1 | 約167,650円 |
| 要介護3 | 約270,480円 |
| 要介護5 | 約362,170円 |
※実際の金額は自治体により異なる場合があります。
3. 福祉用具や住宅改修の対象が増える
たとえば、車いすや特殊寝台などの「原則、軽度者には貸与できない福祉用具」も、要介護2以上であれば原則貸与対象になります。また、必要に応じた住宅改修の提案もしやすくなります。
要介護度が上がるとどうなる?【デメリット編】

1. 介護保険の自己負担額が増えることがある
利用できるサービス量が増える=使う費用も増える可能性があります。自己負担は原則1割ですが、所得に応じて2割・3割負担となることもあるため、トータルの費用負担には注意が必要です。
2. 利用者本人の心理的な負担
「要介護度が上がった=自分は悪くなっている」と感じ、自信や意欲を失うきっかけになってしまうケースもあります。家族やケアマネは本人の気持ちに寄り添い、前向きな声かけが大切です。
3. 介護者の負担感も増す可能性がある
要介護度が上がるということは、生活の中での介助量も増えるということです。サービスを使って支援を強化できる反面、家族の協力や見守りが必要になる場面も増えるかもしれません。
要介護度が上がったときのポイントと対応策

● ケアマネージャーとよく相談を
要介護度が変更された後は、ケアプランの見直しが行われます。どんなサービスを増やすか、負担をどう分散するかなど、ケアマネと相談しながら進めましょう。
● サービスの「使いすぎ」に注意
限度額が増えたからといって、必要以上のサービスを詰め込むと、自己負担が増えたり、本人の自立を妨げる恐れも。バランスのとれた支援が大切です。
● 高額介護サービス費制度の活用
自己負担が高くなったときには、「高額介護サービス費制度」を利用して1か月の自己負担額に上限を設けることが可能です。所得に応じて上限が決まっており、超えた分は後から払い戻されます。
まとめ
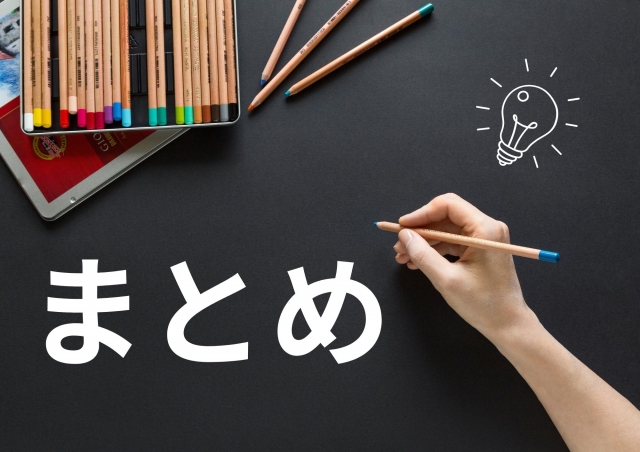
要介護度が上がると、サービスの利用枠が広がり、より手厚い介護を受けられるというメリットがあります。
一方で、費用負担や心理的な影響といったデメリットもあるため、制度の仕組みを理解したうえで、必要なサポートを「適切に使う」ことが重要です。
判断に迷った場合は、ケアマネージャーや地域包括支援センターに相談してみましょう。
状況に合った支援で、本人も家族も無理なく介護と向き合える環境づくりを目指していきましょう。















